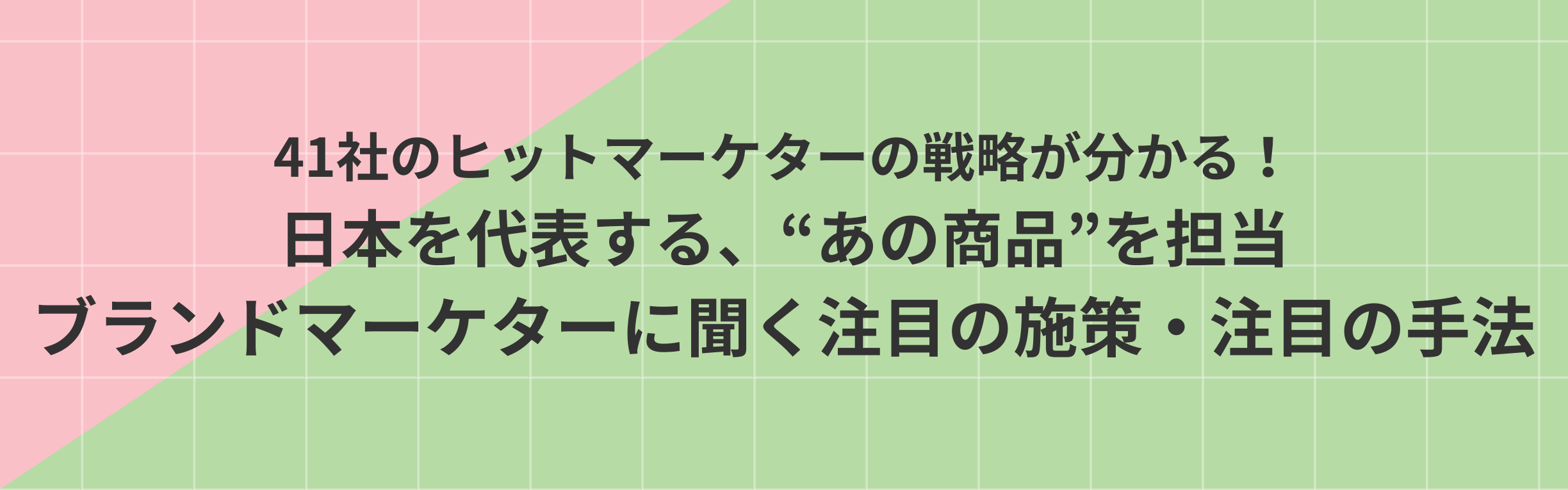1990年代、機能競争から価格競争へと市場環境が変化するなか、日本企業にも広がったブランドマネージャー制度。しかし縦割り組織や短期ローテーションなどの壁で十分に機能せず、“名ばかり”に終わるケースもあった。しかし今、デジタルや生成AI、サステナビリティの潮流が企業のブランド経営を再び変えつつある。ブランドマネージャーの役割の進化と今後の課題について、ニュースケイプ代表取締役の小西圭介氏が解説する。
機能の競争から価格の競争へ ブラマネ制が採用された背景
「ブランドマネージャー(ブラマネ)」という職種の黎明は、P&Gに始まる。1931年当時、若手宣伝マンだったニール・H・マッケロイが上司宛てに綴った3枚の社内メモは、のちに“ブランド・マネジャー制”と呼ばれる組織原理の礎となった。このメモでは「単一ブランドごとに、販売、広告、流通、消費者調査までをひとりが統合管理すべきである」と提案された。機能別縦割りの摩擦を超え、ブランドという単位で意思決定の速度と一貫性を確保するという思想がその核心であった。これは、顧客接点から逆算して、ブランドを軸に製品提供とコミュニケーション活動を循環させる手法でもあり、企業経営に「顧客中心」の概念を根付かせたとも言える。
戦後の大量生産・大量消費がピークを迎えると、欧米企業ではブラマネが広告の枠を超え、4Pのみならずサプライチェーンや財務指標をも俯瞰する“ミニCEO”へと権限を拡大。ブランド単位でP/L責任を持たせることで、迅速な意思決定と投資配分の適正化が両立し、ブランドという「無形資産」を通じて価値を獲得する経営作法が定着していったのである。
日本でも1960年代には一部企業でブラマネ制的な導入は始まっていたが、当初はプロダクト・マネジャー(新製品開発の推進)色が濃かった。しかし1970~1980年代に各企業の基幹ブランドが育つにつれて、ブランド単位の収支管理へと重心が移動する。そしてブラマネ制が真正面から論じられるようになったのは、バブル崩壊後の1990年代である。日本...