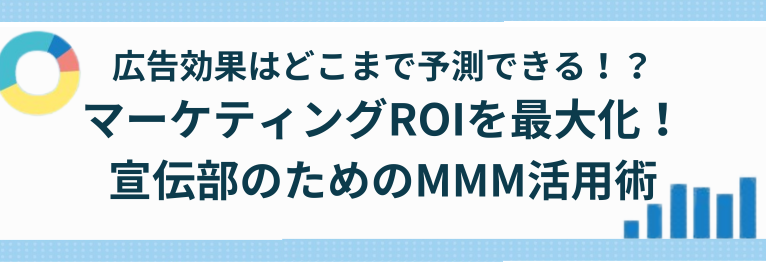モバイル通信サービスの「au」に加え、auPAY、auじぶん銀行など、多様なサービスを提供しているKDDI。今後、データ整備を迅速かつ簡易化できるソリューションや技術の開発によって、MMMのさらなる拡大が見込めると話す、KDDIブランド・コミュニケーション本部コミュニケーションデザイン部長の山中雅貴氏に、同社の現在のMMMの活用について話を聞いた。
単なる予算配分ツールではなく効果分析に重要な役割果たす
マーケティング・ミックス・モデリング(MMM)は、デジタル広告の台頭以前から、企業がメディア配分や広告効果を評価するために活用されてきた。しかし、近年ではその利用方法に変化が見られる。特に、メディアの多様化が進むなかで、MMMは単なる予算配分のツールにとどまらず、企業やブランドにとってのコミュニケーション効果の分析にも重要な役割を果たすようになった。
近年のDX推進や新たなメディアの台頭により、企業は広告の単なる費用対効果だけでなく、ブランド力や顧客との関係性を強化することにも焦点を当てるようになった。こうした背景から、MMMはその分析機能を強化し、企業の全体戦略における意思決定をサポートする有力なツールとして再び注目されている。マーケティング活動が多様化するなかで、企業はどのメディアをどのタイミングで使うべきか、また、どの施策がどれだけブランド価値向上に貢献しているかを把握するために、MMMのようなデータ駆動型の手法が欠かせなくなった。

2月4日から放映を開始したPontaパスのテレビCM「あげすぎ謙信」篇。本CMはau三太郎シリーズのひとつで、「Pontaパスなら...