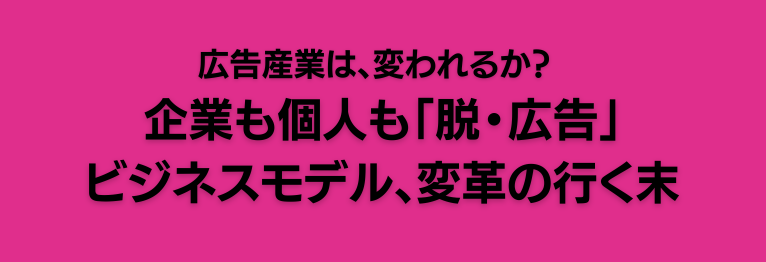いま「広告」は、従来の枠組みを超え幅広い役割が求められ、広告会社が担う領域も広がっている。そこでこれから求められるスキルとはどのようなものか。本座談会で集まったのは、これまで「宣伝会議賞」に応募し、受賞した経験を持つ4人。広告会社で働き始めてこの4月で3年目になる2人と、これから働き始める2人に、30年後の広告界を想像してもらった。
プロダクションマネージャー
Hさん
2022年4月、映像制作会社に入社。
コピーライター
Kさん
2022年4月、総合広告会社に入社。
大学4年生
Nさん
2024年4月、総合職として総合広告会社に入社予定。
コピーライター志望。
大学4年生
Yさん
2024年4月、総合職として総合広告会社に入社予定。
コピーライター志望。
情熱を注ぐ人たちに惹かれ広告会社への入社を決めた
広告業界に進みたいと思ったきっかけや、決め手はなんでしょうか。
H:高校生のころに「宣伝会議賞」に応募して、中高生部門で賞を取ったことから、広告界がグッと身近になりました。大学生の間も広告会社でアルバイトやインターンをしながら、今に至ります。
N:そんなに前のことがきっかけになっているんですね…。他の業界をめざしたいとは思わなかったのですか?
H:多趣味で音楽やファッションも好きだったので、広告業界ならいろいろな趣味を生かせるかもと思ったんです。制作のメインはCM動画ですが、ショートドラマやMVに携わることもあり、好きなことが生かせていると思います。
N:広告業界に入りたいというよりは映像をつくりたかったのですか?
H:元々はコピーライターをめざしていましたが、考えている時間が楽しくもあり、つらくもありました。その頃映像関係の会社のインターンに参加して、興味を持ちました。
N:僕は3年生の時に、インターンで広告会社に行きました。その経験を通じて面白いことに価値があって、人が興味を持ってくれたら、それでご飯が食べられること。そしてそこに並々ならぬ情熱を注いでいる人がたくさんいることが分かったんです。またその頃、僕は個人で漫画のレビューサイトを運営していて、合計で2000冊くらいの漫画が売れていたんです。自分の言葉で魅力を伝えて…
"