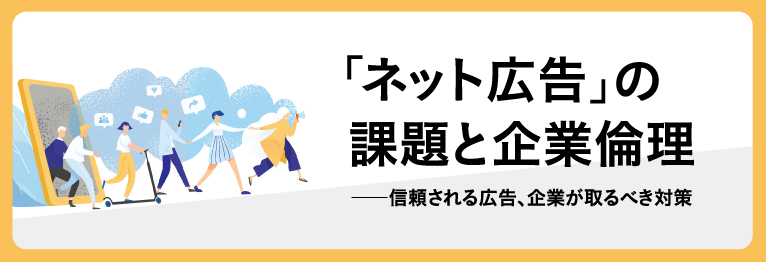10月1日から、ネット上やSNSなどで広告と明らかにせず口コミや感想を装って宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制が始まります。消費者庁が取り組むステマ規制をはじめとしたデジタル広告の品質向上に向けた対策について、表示対策課 課長の高居良平氏と同課 課長補佐の藤原衣穂氏に話を聞きました。
抜け穴となっていたステマ 法規制の目的・背景は
10月1日から、ネット上やSNSなどで広告と明らかにせず口コミや感想を装って宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制が始まる。違反した場合は再発防止を求める措置命令の対象となり、措置命令違反などの悪質な場合は懲役刑や罰金などが科される可能性もある。施行前に掲載されたものであっても、10月1日以降はステマ規制の対象になる点に注意が必要だ。
ステマ規制は新たに景表法の不当表示として追加される。同法は消費者の利益を保護するための法律で、商品・サービスについて実際より著しく優良または有利であると誤認される表示(不当表示)を禁じている。
従来の景表法では、性能や品質などの内容を実際より著しく優良に見せる「①優良誤認」、価格などの取引条件が著しく有利であると見せかける「②有利誤認」、おとり広告や原産国を偽るなど「③その他の不当表示」の3種類を不当表示としてきた。広告であることを隠す行為であるステマ自体が①~③のいずれにも該当しない場合は規制の対象外で、ある種の“抜け穴”となっていた。
成長を続けるインターネット広告市場の中でも、SNSやブログ、動画共有サイトなどのソーシャルメディア上で表示される広告市場の伸びは著しい。広告主がSNS上で行うソーシャル広告以外にも、第三者であるインフルエンサーなどが広告主から依頼を受けて広告主の商品・サービスをSNS上で広告をするインフルエンサーマーケティングも増加している。
消費者庁表示対策課 課長・高居良平氏は「消費者は、広告だとわかっていれば『ある程度誇張・誇大が含まれる可能性があるな』と理解して商品選択の判断をしています。しかしネット上やSNSの口コミは『広告じゃないから本当にいいものなんだ』と信頼する人が多く、ステマはこういった消費者心理につけ込んだ問題で、近年顕在化してきました。OECD加盟国でステマ広告の規制がないのは日本だけという状況下、法整備への流れと進んでいきました」と語る。
消費者庁は2022年12月に有識者検討会の報告書を公表。規制強化を求める声をまとめ、2023年3月28日にステマに関する記載を「③その他の不当表示」に新たに追加する形でステマ規制を始めたというわけだ。
規制対象の表示媒体は全メディア 規制に当たらない表示とは?
そこで新たに景表法の不当表示として追加されたのが「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」。これが、広告業界では“ステマ規制”と言われているものだ。具体的にどのような表示が該当するかは、消費者庁が3月に公表した運用基準に詳しい記載がある...