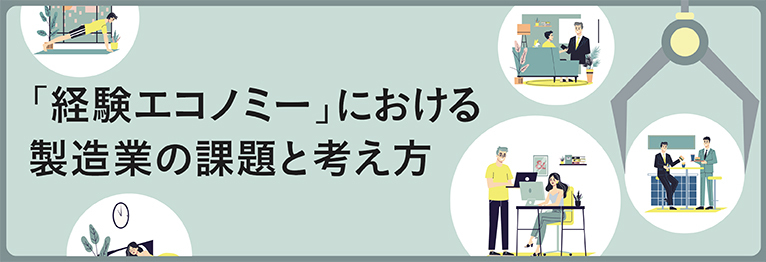便利さ、使い心地の良さなど、プロダクトデザインで重視すべき要素は様々あるが、使った後の体験価値まで含めると、プロダクトデザインにはどのような価値が提供できるのか。奈良県の東吉野村を拠点にプロダクト開発を行う菅野大門氏が考えを述べる。
柔軟性のある少量生産が叶える 持続性のあるものづくり
私は奈良県の東吉野村を拠点に、「A4/エーヨン」というプロダクトデザインレーベルを運営し、少量から中量生産のプロダクトを発表しています。試作したものを、ひたすら自分や周囲の人で使ってみて、試行錯誤を重ねてから発表するため、半年~5年、ときに10年と長い時間をかけてプロダクトを世に送り出しています。
私は大学卒業時にそのまま独立してプロダクトデザイナーとして活動していますが、もともとは企業から依頼された案件を手掛けるケースがほとんどでした。以前であれば、プロダクトを開発しようとなると、原料調達から製造、販売チャネル開拓など多様な要素が必要で、個人で実現するのが難しい分野でした。
しかし、インターネットをはじめとするテクノロジーの発達により現在では、個人がプロダクトをつくることも売ることも、容易になった。さらに、現在は多様な価値観が認められる時代。大量に生産して、大量に販売することは、ひとつの価値観を大量に届けることにもなります。そうではなく、少人数の人に合わせて柔軟に価値を届ける方が、今の時代には合っている気がしています。これが、長い時間をかけて少ロットでセルフプロダクトを生産している私のベースとなる考えです。
また、「A4/エーヨン」では、「製作する人」「販売する人」「使う人」それぞれに対価があることを重要視しています。つくってお終い、売ってお終い、使ってお終いの繰り返しは、たとえ良い物を生み出していても、どこかで歪が生まれ、持続性のあるサイクルにはならないからです。
持続できないということは、お客さまに体験や価値を提供し続けられないということにもなります。長く、プロダクトを通して幸せを届け続けるためにも、「つくって良し」「売って良し」「使って良し」の持続性のあるものづくりがこれからの時代のものづくりだと考えています。
価値観が多様化する時代 プロダクトの“体験”も自由に
「A4/エーヨン」では、プロダクトをつくる際、まずは兎に角、自分自身が欲しいと思ったものを試作します。価値観が多様化しているからこそ、多くの意見が集まれば集まるほど、核がぼやけていく。なので最初の段階では...