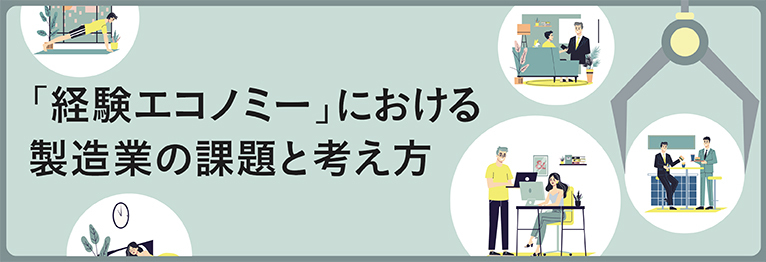商品の利便性や価格だけではなく、企業の社会貢献活動はどのように消費者の購買に影響を与えているのか。エデルマン・ジャパンの森田尚子氏が、同社が実施している調査「エデルマン・トラストバロメーター」の結果をもとに、グローバルの潮流も交えて解説する。
企業の社会課題に対する姿勢 半数以上の生活者に影響
コロナ禍を経て、世界中の人々の価値観が劇的に変化し、企業やブランドの在り方にも変革をもたらしました。日本では江戸時代から「三方よし」という価値観が存在していますが、パンデミックが世界的にステークホルダー・キャピタリズムを加速させ、企業やブランド、そしてそのリーダーたちが社会的課題を解決することへの生活者からの期待はますます高まっています。
つまり社会貢献活動はもはや企業による単なる慈善活動ではなく、企業やブランドの存在意義そのものであり、社会的課題を解決していくことがビジネスそのものの目的となっていく時代を迎えています。
エデルマンでは、約20年にわたり、世界各国で定点的に人々の様々な信頼に関する調査「エデルマン・トラストバロメーター」を実施しています。生活者とブランドの信頼についても調べており、その調査結果からも、ブランドに対する生活者の要求が高まっていることが見受けられます。
具体的には、「ビリーフ・ドリブン」な購買者の台頭です。今では、世界平均で62%、日本でも53%の生活者が、社会的課題に対するブランドの姿勢に基づいて、ブランドを選んだり、避けたりしていることがわかっています。日本の数値は世界平均に比べると低いですが、2017年に実施した調査では39%だったことを考慮すると、ブランドが社会的課題に対する姿勢を示すことが、生活者にとってどれほど重要になったか想像に難くありません。
ここでいう「ブランド」は、単なる製品やサービスを意味しているのではなく、企業ブランド全体も含んでいます。どんなに素晴らしい製品やサービスを世の中に提供しても、それを提供している企業の社会的課題に取り組む姿勢が見られなければ、生活者の過半数はその製品を信頼できず、購買につながらないことになります。今後は、製品ブランドと企業ブランドのアライメントがますます重要になっていくことが、うかがいしれます。
「好き」よりも「信頼」で購入 信頼感の醸成は従業員から
また今の時代、生活者にとって重要なのが「信頼」です。2021年5月から6月に実施した調査結果によると、生活者は購買決定において、ブランドへの「愛」よりも「信頼」を重視しており、世界平均で68%、日本では43%の生活者が...