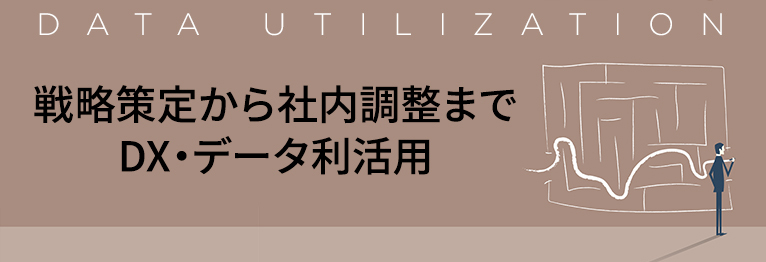人々の生活に欠かすことができない「食」。しかし、人の「おいしい」という感情には非常に多くの要因が関わっており、その解明は難しかった。ニチレイはデータを活用し「個人にあったおいしさ」を可視化するシステム「conomeal」を構築。「おいしさ」の可視化でどのような価値が生まれるのか、技術戦略企画部 事業開発グループの関屋英理子氏に話を聞いた。

大学と協力しAIを開発「食の嗜好性」を可視化する
ニチレイは個人の食の好み(食の嗜好性)を、AIを用いて分析し、好みにあったレシピや情報提供を可能にするシステム「conomeal(このみる)」を開発。同システムを個人向けに活用したサービスとして、レシピやつくりおき献立を提案するスマートフォン用アプリ「conomeal kitchen」のβ版を9月よりテスト配信している。
「conomeal」を開発した経緯について、同社技術戦略企画部で新規事業の企画・開発に携わる関屋英理子氏は、個人の「食の嗜好性」を知ることが、より充実した「おいしい」を届けるために必要だと考えたと話す。
「ニチレイは、『くらしを見つめ、人々に心の満足を提供する』をミッションに、おいしさの充足や、おいしいものの品質向上を行ってきました。これまでは、広くマスに向ける視点で人々の『おいしい』を捉え、商品を開発してきましたが、より磨かれた『おいしさ』を届けるためには、一人ひとり異なる『おいしい』を捉える手段が必要になると予想。まずは個人の食の嗜好性を分析しようと考えたのです」と関屋氏。
「当社の知見により、食の嗜好性、つまり『おいしい』という感覚は、食品そのものの質のほかに、五感で得る情報や、その人が育ってきた文化など、感情に関わる多くの情報に起因することがわかっていました。また、同じ人でも、その時々の環境で嗜好性は変化します。この複雑な情報をいかに分析するのかを検討し、着目したのがAIでした」。
同社は北海道大学で...