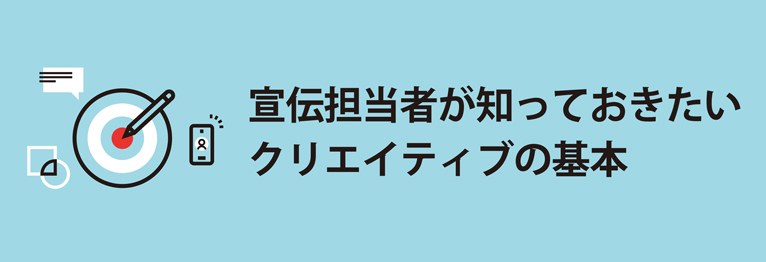今月のテーマ:テレビやWeb、チャネルが広がる現代
映像広告のクリエイティブディレクション
以前は「映像広告」というとテレビCMが主流でしたが、現在は動画サイトやSNSで流れるWebCMも増えてきています。それでは、どちらも「映像広告」ですが、クリエイティブの使い分けやディレクションに違いはあるのでしょうか。広告主の視点と、動画制作クリエイターの視点から「映像広告」について解説します。
- オリエン以上の提案はないと思うべき。オリエンでクリエイティブの方向性を示そう。
- マス広告では"愛される広告"を。デジタル広告では"奇抜なクリエイティブ"にも試験的に挑戦できる。
- 広告会社、お客様相談室、品質管理部門の3者の目でリスクを洗い出す。
映像広告におけるクリエイティブのポイント
最も重要なのはオリエン 相手との関係で内容を変える
映像広告を発注する際に、完成度に影響を与える最も重要な要素は、「オリエン」です。広告主が「オリエン」で提示した内容以上の提案はないと考えているからです。広告会社と違って、私たち広告主企業は広告のプロではありません。そこで、自社の市場環境、目的、メインターゲットを提示。そのうえで、アウトプットのイメージを共有するようにしています。すでに放送されている他社の映像広告を見せたり、キーワードを提示することもあります。
例えばカルビーの「じゃがりこ」のテレビCMの場合、オリエンでは2つのクリエイティブの方向性を共有しました。1つめは「食感(音)」と「ブランド名」。2つめは「リズム・音楽・シチュエーション」でした。しかし、それ以上の表現の指示は出しません。クリエイターの皆さんの創造力を奪わないためです。
ちなみに、私は広告会社に発注する際、何社かに声をかけて競合プレゼンを行いますが、その際、一度に複数の会社を呼ばずに、1社ずつに対してオリエンを行います。それは、広告会社によって関係性が異なるからです。関係性が異なる人に同じ内容でオリエンをしてしまうと、関係性が深い企業のほうが当社のトーン&マナーや意向をすでに理解してくれている場合があるので、不平等になってしまいます。そこで、各社との関係性に応じてオリエンで伝える内容も調整しているのです。
マス広告は"愛される"もの デジタル広告は"奇抜な"ものも
最近は、「映像広告」と一口に言ってもテレビCMなどのマス広告だけでなく、TwitterやYouTubeなどWebで流れる広告も多くなっています。また映像広告には、販売店の店頭で流れるものもあります。
テレビCMなどのマス広告では制作費が高く、複数素材はつくれないため、慎重に制作する必要があります。また、テレビは老若男女問わず多くの人が見ます。コアターゲットを決めてCMを制作はしますが、ターゲット以外の人も視聴するのがテレビCMです。そこで、ブランドや商品が嫌われたくないので、「愛される広告」を目指します。
一方のWeb広告では、ターゲティングしたうえで広告を配信します。そのため、テレビCMではリスクがあるような、多少奇抜なクリエイティブにも挑戦することができます。むしろインパクトのあるクリエイティブでないと、視聴者の印象に残らないとも言えます。さらに配信に際してテレビよりもコストがかからないので、複数のクリエイティブをつくり、A/Bテストを行うこともできます。
このような特徴を踏まえて当社では、最重要ブランドについてはテレビCMを、ターゲットが絞られているブランドについてはWeb広告を、と使い分けしています。ひとつのブランドでも立体的にテレビCMとWebを使い分けるほうが有効かもしれないとも思いますが、現在のベストの案として、先のような使い分けをしています。
また、テレビCMは「世の中を動かすCM」にすることを心がけています。Webはターゲティングされるので、マスにリーチすることはできません。ですがテレビCMだと、消費者となるターゲットだけでなく流通の担当者さんにも届くので、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの店頭も変えていくことができます …