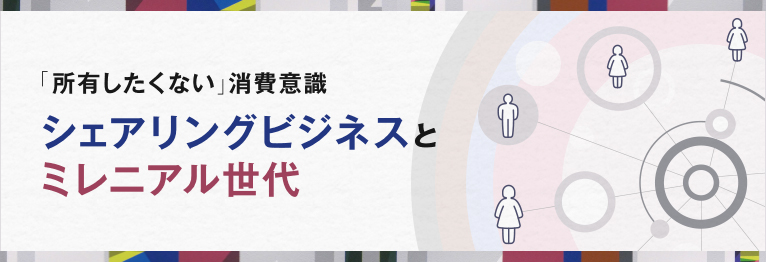モノを極力、持たないで暮らす「ミニマリスト」の生活が、若者から支持を集めている。その考え方を紹介した書籍『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』は16万部を突破し、世界17カ国で発行された。著者であり、自らも「ミニマリスト」である佐々木典士氏の考えから、現代の消費者の新たな価値観が見えてきた。

佐々木氏が東京在住時に、ミニマリストになっていく過程。
スマホとクラウドサービスが「持たなくて済む」環境を準備した
ミニマリストとして、ぼくが東京に住み、モノをカリカリに削っていた頃、欲しいと思っていたリュックはアップルの「MacBook Air」しか入らない薄いリュックでした。その頃は、探してもありませんでしたが、「ONFAdd」というブランドから実際に発売されることになりました。スーツの下にも着られるという薄さしかなく、重さも200グラム程度。満員電車でも邪魔にならず、軽いので一緒にどこまででも歩いていけそうな自由さがあります。
なぜ持ち歩くモノが、こんな量で済むのかと言えば、一つひとつのモノが高機能になったからです。パソコンと言わず、スマホがあれば、カメラも辞書も懐中電灯も預金通帳もいらない。いまやスマホの音声入力で本の執筆さえ行われているような時代です。
以前のぼくは、コレクター気質でたくさんのモノに囲まれていました。数千冊の本、数百枚のCDやDVD。フィルムカメラに凝り、キッチンを暗室に改装したりもしていました。今や暗室で行っていた複雑な作業は、カメラアプリのフィルターに置き換わってしまいました。Amazonプライムに入会すれば、読み放題の本も見放題の映画もあり、Spotifyで音楽も聴き放題。
かつてレコードを何万枚持っているということがステータスになった時代もありましたが、クラウド上には個人が所有できる量とは比較にならないほどの膨大なアーカイブがあり、必要なときに引き出すことができるようになったのです。
ミニマリストがアメリカで誕生したのは2010年前後なのですが、スマホの登場とDropboxなどのクラウドサービス、Kindleなどのデジタル化の進展と時期が一致します。
まずはモノとサービスの発展自体が、モノを持たなくて済む環境を準備したと言えます。
モノの大きなプロセスの一環に必要な時だけ参加する感覚
さらにインターネットによる個人間売買は「所有」という概念すら変えていきそうな勢いです。
ぼくは最近、「メルカリ」でリュックを手放しました。使用頻度も少なく、人気のメーカーでもあったため2万円で買ったものが1万5千円で売れました。うまくすれば買ったときの値段と売るときの値段が限りなく小さくなっていきます。このリュックは1年半ぐらい持っていたのですが、こうしてみると「所有していたものを売った」のではなく「5000円のレンタル代を払って1年半借りていた」感覚になっていきます。
最近、自家用車もSNSを通して売買しました。ぼくが乗っていたのは電気自動車なのですが、TwitterとFacebookを通して引き取り手を見つけたのです。値段はかなりお得にしましたが、それでも買い取り業者の見積もりと比べると2~3倍高かった。これもまた「買ったものを売った」のではなく「一定の金額を払って、半年間のレンタカー契約をしていた」感覚です。
ぼくはこのクルマでペーパードライバーを卒業し、今の過渡期に一足早く電気自動車に乗りました。買ったのはクルマではなく、その勉強代であり、経験だという気がするのです。シェアリングサービスを使わずとも、個人間売買を通じて社会全体でシェアしているような感覚です。
こうしてみると、持っているモノが多い、少ないということも単純には言えなくなってきていると思います。手元にはいつも10着の服しか残さない。けれど、メルカリを通じて1シーズンに30着の服に袖を通しては売り、循環させるということも考えられるからです。もはや所有して終わりではなく、モノの大きなプロセスの一環に、そのときだけ参加するようなイメージです …