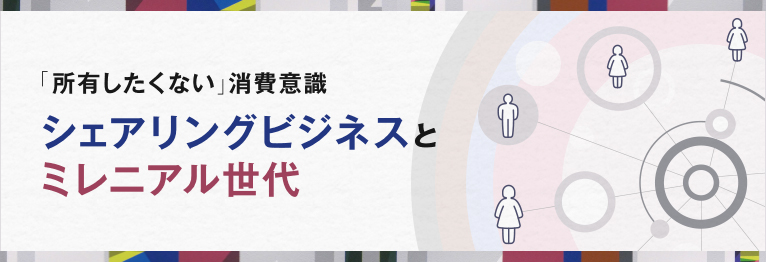モノが主語ではない、消費者視点の体験の場であるトヨタ自動車の「DRIVE TO GO BY TOYOTA」(詳細記事はこちら)。

(左)INAMOTO & Co. Founding Partner レイ・イナモト氏
(右)Archicept city 代表取締役 クリエイティブディレクター 室井淳司氏
Story TellingからTrust Buildingへ
──今回の企画は、どのような背景から生まれたのですか。
レイ:ここ10年ほど、コミュニケーションデザインという言葉が使われてきましたが、僕はその言葉の意義が薄れてしまったと感じています。コミュニケーションだけでは消費者からの信頼を築けなくなっているし、ブランドもつくれなくなっているからです。
今、世界で最も強力な会社Google、Facebook、Amazonなどを見ると、広告という手段にさほど固執していないし、自分たちの物語をそこまで積極的に語ろうとはしていない。特にアメリカでは日本と違い、あまり広告に頼っていません。それよりも、サービスを提供することにより、消費者からの信頼を築くことに力点を置いています。
ブランドのストーリーを伝えるストーリーテリングから、サービスの提供へと大きく移り変わっていると思います。今回の「DRIVE TO GO BY TOYOTA」もこの文脈上にあるもので、広告キャンペーンでブランドのストーリーを伝えるだけでは通用しない時代だからこそ、サービスを体験できる場をつくろうと企画したものです。
室井:日本の企業、特にメーカーの場合は、どうしてもモノを主人公にしたコミュニケーションを考えてしまいがちですよね。そこを、消費者を主人公に頭を切り替えてみると、モノではなく、そのモノが提供しうる体験に目が向くようになる。そういう発想の先に「DRIVE TO GO BY TOYOTA」のような、モノが主語ではない、ブランド体験の場がつくられるのではないでしょうか。
──消費者からの信頼はどのように築いていけばよいと思いますか。
レイ:日本でも、ユナイテッド航空が乗客を機外に引きずりおろそうとする映像が多く視聴されたのではないでしょうか。皮肉なことにユナイテッド航空は「Fly the Friendly Skies」というタグラインを使っていました。これからもストーリーテリング的な広告があってもよいとは思いますが、そこで語られていることと現実が乖離していた時の痛手はより大きくなっています。
誰もがスマートフォンで撮影し、世界に発信できる時代にあって、虚構はすぐに見破られてしまいます。打ち上げ花火的なキャンペーンではなく、毎日コツコツと信頼を築いていく ...