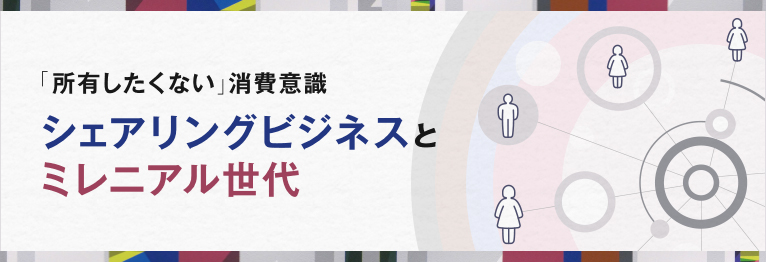世界中で普及が進むシェアリングビジネス。その代表的なサービスと日本における動向や課題について、シェアリングエコノミー協会 事務局長の佐別当隆志氏が解説する。
中国では50兆円を超える規模に代表的な5つのシェアサービス
シェアリングエコノミー(共有型経済)は、モノや空間など、様々なサービスを個人間で共有することで成立する経済概念を指します。インターネット上のプラットフォームを介すという特徴があり、人のスキルを含む遊休資産の有効利用が促されることで、新たな価値を生むことが期待されています。
「所有から共有へ」という広義の意味で捉えると、カーシェアリングやシェアサイクルなどBtoCのサービスを含んだり、シェアハウスやシェアオフィスなどインターネットを活用しないサービスが含まれることもあります。
近年、世界中でこれらの市場が拡大し、中でも中国の市場規模は昨年50兆円を超えたとも言われています。今後は欧州でも50兆円規模になると予測されており、移民など雇用の受け皿としても期待されているほどです。
シェアリングエコノミーは、主に「空間シェア」「移動シェア」「スキルシェア」「モノシェア」「お金シェア」の5つの領域に分けられます。まずは、それぞれの代表的なサービスを紹介しましょう図1。
1.空間のシェア
自宅の空き部屋を観光客などに貸し出す民泊が挙げられます。代表的なサービスは、世界各国で急成長を遂げている「Airbnb」や、家を使わない期間に一棟貸しをするバケーションレンタルの「HomeAway」でしょう。
日本でも2018年に住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が施行され、国内企業の参入も増加しています。また宿泊を伴わない、企業のセミナースペースや飲食店、古民家などを貸し出す「スペースマーケット」や、個人や企業が所有する空き駐車場を時間単位で貸し出す「軒先パーキング」も人気を集めています。
2.移動のシェア
いわゆるライドシェアサービスの、自家用車による配車サービスとして代表的な「Uber」や「Lyft」、長距離移動の目的地まで相乗りし、かかったコストをシェアする「notteco(のってこ)」などが挙げられます。個人が所有する自動車をシェアする個人間カーシェアリングでは「Anyca」が代表的です。また、東京都心では、飲食店の宅配注文をバイクや自転車による個人デリバリーする「UberEATS」や、通勤や観光目的でシェアサイクルの利用も増えています。
3.スキルのシェア
ライティングやデザインなど、自分のスキルや経験を生かして好きな時間に働くことができるクラウドソーシングサービスです。「クラウドワークス」や「ランサーズ」の会員数が100万人を超えるなど、都市部だけでなく地方でも利用者が拡大しています。農家が観光案内人として農業体験を提供する「TABICA」や、外国人が自宅で料理教室を開催する「Tadaku」も主婦層をはじめ女性に人気を集めています。
4.モノのシェア
雑貨や本など個人間で売買するフリマアプリの「メルカリ」が代表的です。ファッション関係のシェアリングが成長中で、高級バッグのシェアをする「ラクサス」は、BtoCからサービスを伸ばし、個人間レンタルも2017年に開始しました。クローゼットに眠っているバッグで、小遣い稼ぎする人が増加中です。
5.お金のシェア
銀行が融資しないようなプロジェクトも、企画次第で個人から資金調達ができるクラウドファンディングが当てはまります。寄付型・投資型・購入型の大きく3つに分けられます。投資型は金銭的なリターンがあり、不動産投資に特化した「クラウドリアルティ」、購入型では「Makuake」などが挙げられます。地方の町工場の電動自転車のプロジェクトで、それぞれ1億円以上の資金調達にも成功しています。
相互評価による信頼性が担保評価が低いと利用できないことも
このように様々な分野で、シェアリングエコノミーのサービスが広がっている背景には、スマートフォンやソーシャルメディアが普及したことと、テクノロジーの進化によって本人確認や決済が容易になり、簡単に安心してサービスを利用できるようになったことがあります。
また、シェアサービスの特徴でもある相互評価の仕組みによって、蓄積された情報の信頼性が、シェアではない企業の提供するサービスよりも優れているという理由もあります。企業がマニュアルに基づいて提供する画一的で安定したサービスではなく、多様でニッチなニーズにも対応し、人の温かさを感じるサービスを、場所を選ばず誰もが受容・提供できるようになっているのです。
空いている部屋や自家用車、自分のスキルといった遊休資産を活用するため、個人事業としてスケールすることはありませんが、大きな初期投資や社員を採用する必要もありません。サービスを一度、利用した人が「これなら自分もできそうだ」と思って、サービス提供者側に回ることも容易に起こります ...