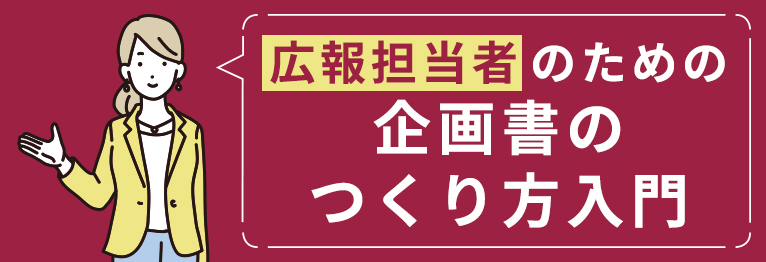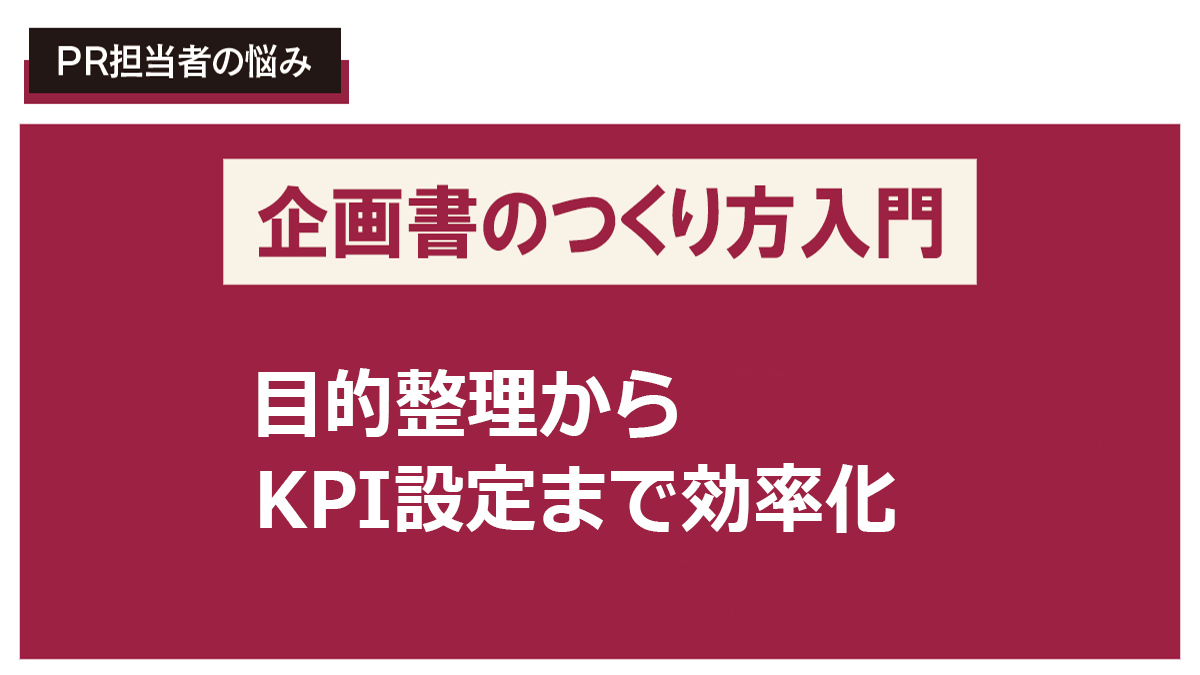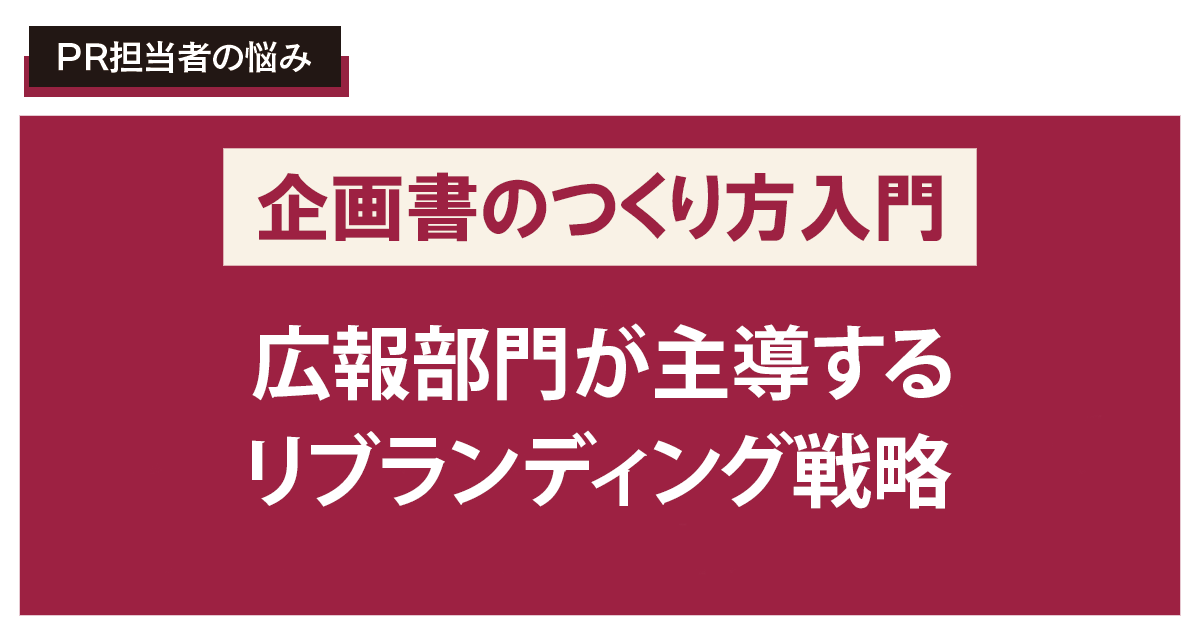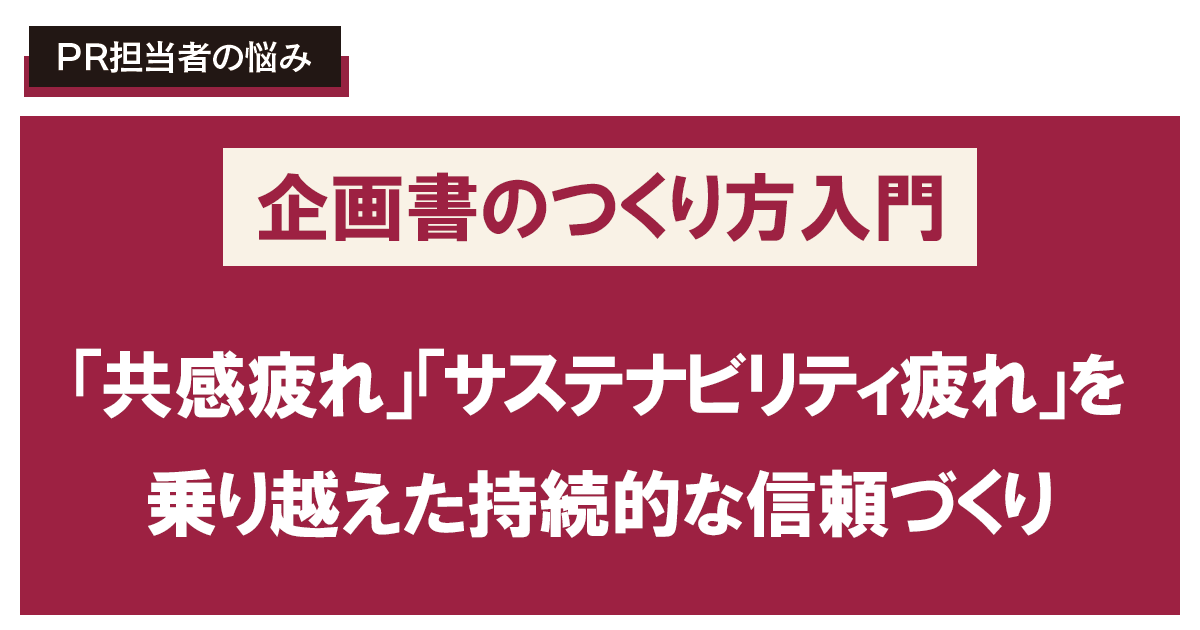「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。
共感を生み出す糸口
短い動画で強い印象や共感を生む事例はここ数年で急増している。多忙な人々が「すぐに理解できるコンテンツ」を求めるようになった今、数十秒から数分程度のショートムービーは、ブランドとの距離を一気に縮める効果的な手段だ。ただしメッセージを凝縮し、視聴者の心を動かすには、戦略的な仕組みづくりが欠かせない。今回は、ショートムービーを軸とする広報企画書のつくり方を考えていきたい。誰に、何を、どのように伝えるべきか。プラットフォームごとの特徴から、短い尺でも物語を構成する手法、さらにトラブル対策についても考えていく。短尺動画は視聴者との新たな接点を築き、口コミ拡散や好感度向上を狙える強力なツールである。企業と消費者を結びつけ“共感”を生み出す糸口になることを期待したい。
視点1
ショートムービーを使った広報戦略
短尺で瞬時に興味を引きつける
多忙な視聴者にとって短尺動画で瞬時に興味を引きつけるコミュニケーション手法は、集中を維持しやすく完視聴まで到達しやすい。さらに数十秒~数分の動画はSNS上で拡散されやすく、コメントやシェアによるユーザー参加型の動きが活発化しやすいという特徴がある。
短い動画を制作する際には、余計な装飾や冗長な説明を排し、要点のみを的確に盛り込む編集技術が重要となる。SNS上では、わずか数秒の冒頭で視聴を続行すべき理由を示せなければ、すぐ離脱されてしまう。メッセージを最短距離で届けるためのデザイン(設計)が求められる。
また動画そのもののクオリティーだけではなく、公開のタイミングやサムネイル、メッセージ設計などの複数要素を総合的に最適化していく必要がある。
BtoBとBtoCで異なる訴求
短尺動画は「誰に、何を、どう伝えるか」という設計次第で、企業向け(BtoB)にも一般消費者向け(BtoC)にも活用できる。ただし、視聴者が期待する情報の質や感情の動き方は両者で大きく異なる。
図1 BtoBとBtoC、短尺動画の活用例と演出の違い
BtoB企業の技術解説
専門的な製品の特徴やシステムの仕組みを、アニメーションなどを用いて分かりやすく整理し、3分以内にまとめるのが好ましい。長いマニュアルをすべて読まなくても理解できる形で専門家の目を引き、商談や問い合わせにつなげる狙いがある。
BtoCブランドの感情喚起
ブランドイメージを鮮明に伝えるため、物語性や季節感、ユーザーの体験エピソードなどを用いると効果的。視聴者の日常を彩るような「ちょっとした幸せ」や「憧れ」を短時間で演出し、共感を誘発することで拡散力を高める。
コラム
短尺VS中尺の境目 ~3分以上撮るか、以下で攻めるか~
ショートムービーは3分以内が鉄板と言われる。一方で、実務では「実際のところ4~5分かけないと伝えきれない」というジレンマに陥ることも少なくない。私自身もあるメーカーの新製品をプロモーションする際に「2分で収めてほしい」と監修を依頼されながら、技術説明だけで2分を超えてしまうことが分かり、結果的に3分半程度の映像になった経験がある。ところが、社内モニターでは「全部見てもらえた」ものの、いざSNSで公開してみると離脱率が最初の90秒付近で急増するという結果となった。
そこで、思い切って1分40秒前後に短縮したバージョンを別途制作したところ、視聴完了率が大幅に改善した。特に20代・30代の視聴者の多くは、短い動画だと初めから最後まで見切ってくれる傾向が強いと判明した。その後のキャンペーン施策では、最初から2パターンをつくる方針に切り替え、3分弱の「詳しく知りたい層向け」と90~120秒の「さらっと概要を把握したい層向け」を併用した。その結果、新規顧客の問い合わせ数と既存顧客の再購入率の両面で向上が見られた。
ポイントは「動画の完成尺」だけでなく、「どこで・誰が・何のために視聴するか」の状況を細かく想定する点にある。展示会やイベント会場で見せるなら少し長めでもよいかもしれないが、SNS閲覧ではさらに短いほうがよい場合がある。じっくり見てもらうための中尺を否定するつもりはないが、最初の30秒で視聴者の興味をしっかりとつかむ設計にし、短いバージョンも併用することで、大きな成果につながることがあった。「3分を超えるかどうか」は単なる数字の問題ではない。視聴環境とターゲットの集中時間を見極める作業でもある。
企画書の骨格設計
ショートムービーの広報企画において重要なのは、「目的」「ターゲット」「KPI」の3つの要素を整合性のある形で定義することだ(図2)。
図2 企画書に必須の3要素
① 目的の明確化
認知度向上やブランドイメージの確立、売上拡大、社会的メッセージの発信など、最終的に目指すゴールを定める。
② ターゲット設定
性別や年齢などの基本的属性に加え、ライフスタイルやSNS利用状況、興味関心などを分析する。ペルソナを作成し、映像表現の方向性を絞り込む。
③ KPIの設定
再生数やエンゲージメント率、SNSでの言及数、問い合わせ数など、定量的かつチーム全体で共有可能な指標を選ぶ。
KPIを定めたら「計測方法」「報告頻度」「改善アクション」を必ずセットで企画書に盛り込みたい。週次で視聴完了率をダッシュボードに可視化し、「目標値との差が5%以上開いた場合はサムネイルのABテストや尺の再編集を即時実施する」といった運用ルールまでを記載しておく。そうすると企画書が “PDCAを回す実務的なマニュアル” へと進化する。
動画ストーリーの構成
短尺動画で視聴者を引き込み、行動変容を促すにはストーリーテリングが欠かせない。「目的・ターゲット・KPI」が固まったら、〈起・承・転...