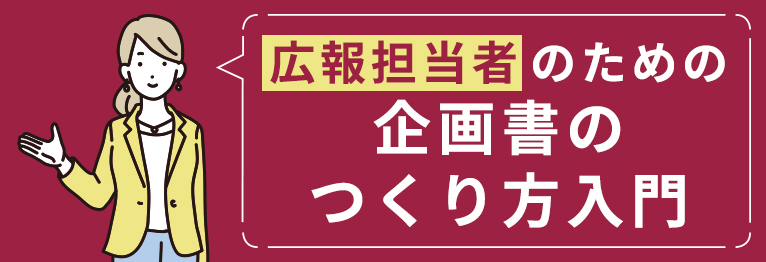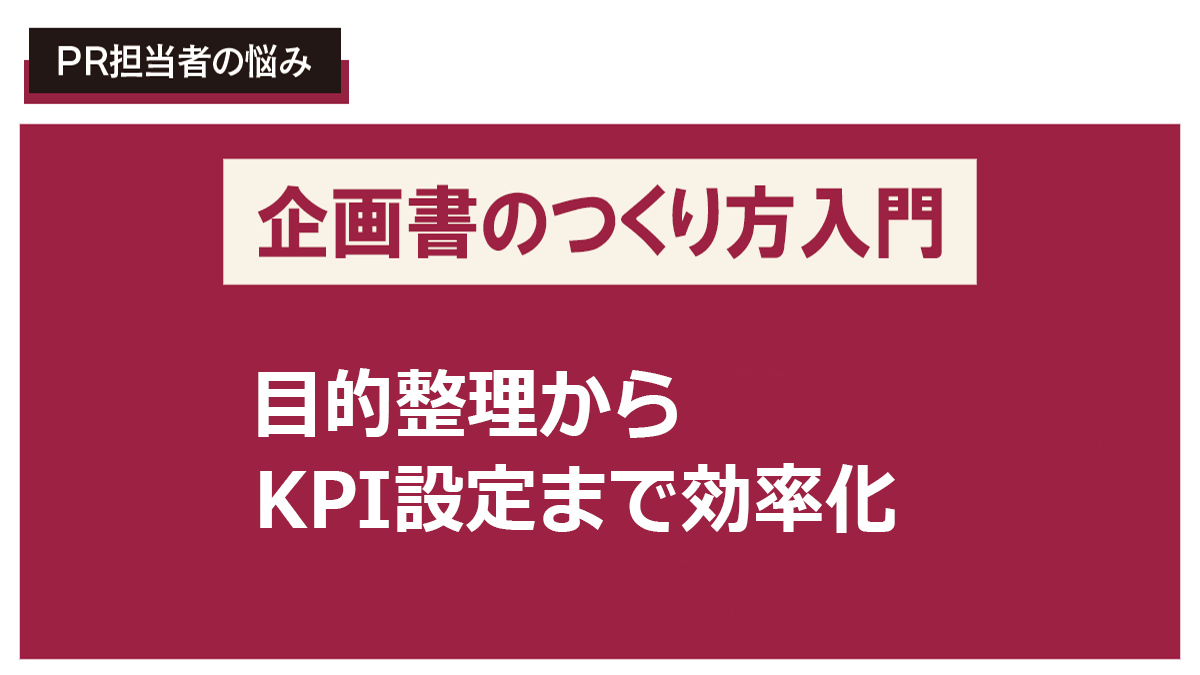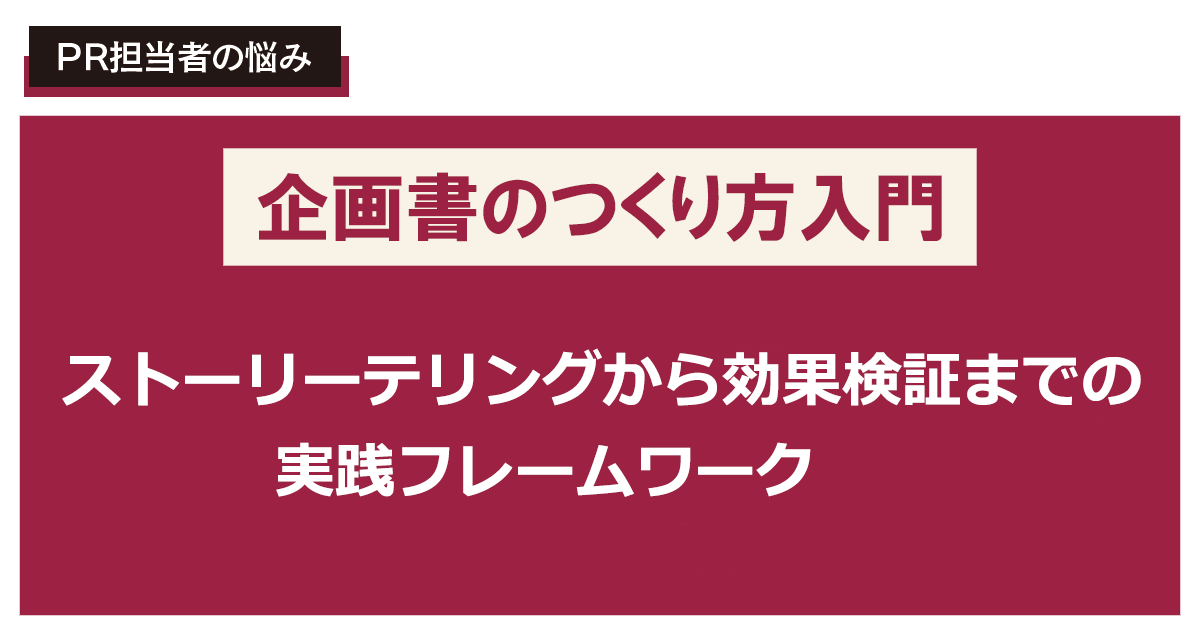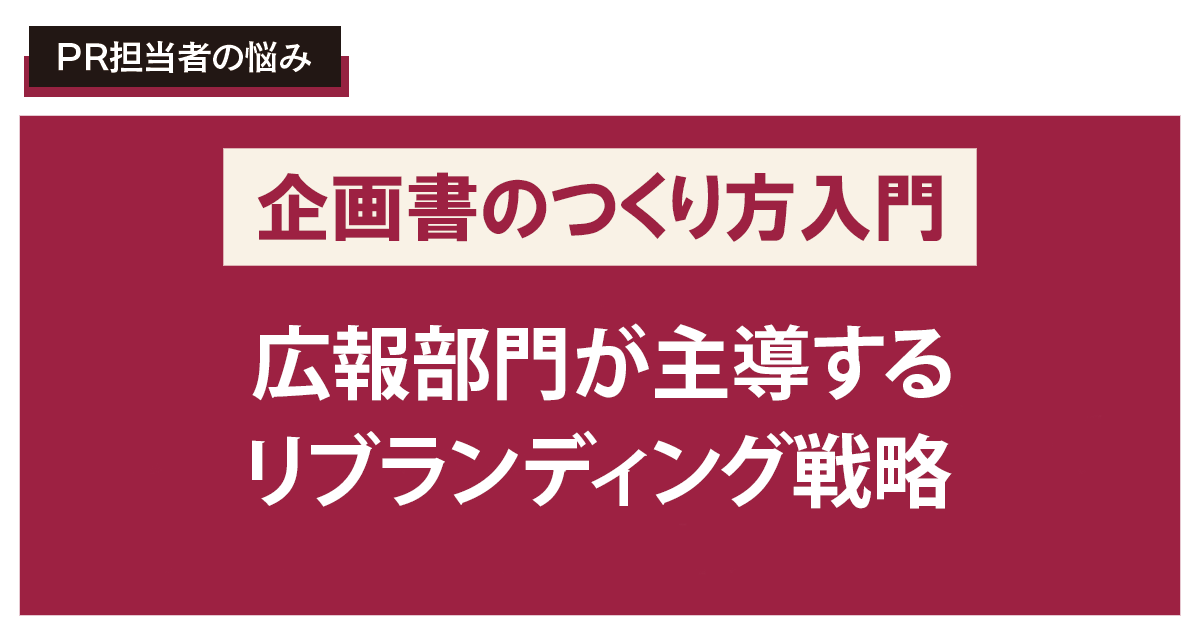「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。
経営と不可分になった広報部門
広報部門が担う役割は今、大きく変わりつつある。SNS運用やメディア対応などの「現場レベルの施策設計」だけでなく、経営層が議論する中期経営計画(中計)や事業計画そのものに広報戦略を組み込むことが求められるようになったからだ。もはや広報部門は経営と不可分で、営業戦略や人事戦略、IR戦略と並列で語られるようになった。一方で、多くの広報担当者にとって経営企画との「統合設計」は未知の領域だろう。経営会議でどのように広報成果を示し、経営トップのメッセージをどう構築・運用するかという問題に対しては、現場でも戸惑いが多い。今回は、広報部門が経営企画部門と協働し、経営戦略そのものに深く関与するための具体的な企画書づくりについて考える。
視点1
広報が経営に組み込まれる理由とは?
広報部門に求められる「統合設計」の時代
従来、企業の広報部門は、「製品の認知を拡大したい」「メディア露出を増やしたい」といった要求に応える存在として位置づけられてきた。その評価指標も多くは広告換算値(AVE)や記事掲載数など、あくまで広報視点に限定されたものだった。しかし近年、広報に対する経営層からの期待が大きく変わり始めている。
今、広報部門に求められるのは、経営が設定した目標や事業戦略そのものと深く連動した広報施策の立案と運用、すなわち「統合設計」である。これが実現しない限り、組織の中での存在意義が揺らぎかねない。
「攻め」と「守り」を兼ね備える広報戦略とは?
経営統合型の広報とは、単に危機発生時のリスク管理やネガティブ報道への対処といった「守り」だけではない。積極的に企業ブランドを構築・強化し、経営戦略や中計の浸透を促進するという「攻め」の側面も併せ持つ。
例えば、新規市場への参入や業態転換、企業価値向上に向けた施策は経営層が描く事業計画に示されているが、それらがステークホルダーにしっかりと伝わらなければ経営的な効果は薄れる。その伝達と浸透を担うのが統合設計型の広報部門の役割であり、そのためには経営計画の策定段階から広報担当者が関与する必要がある。
経営とのズレが生むリスク
一方で、事業戦略と広報施策が一致しない場合に起きるリスクも無視できない。具体的には、事業部門が力を入れたい製品群と広報部門が重視する製品群がズレる、あるいは経営層が重要視する指標と広報が追いかける指標が乖離するなどの問題が発生することがある。実際、私もかつて、「SNSでの話題化(いわゆる『バズる』)」ばかりを追い過ぎ、肝心の重点事業の露出が抜け落ちていると指摘を受けたことがある。
こうした乖離が続くと、「広報は何をしているのか」「経営戦略にどう貢献しているのか」といった疑問や不満が経営会議で噴出し、広報部門の信用が失われる可能性もある。広報担当者としては、こうした事態は絶対に避けるべきである。
これらを防ぐためには、広報担当者に、「広報の視点」だけでなく「経営の視点」から企画書を作成する能力が求められる。
コラム
広報の企画書はなぜわかりやすいのか?
ある企業の経営会議で、財務、営業、人事など各部門が次々と企画を提案した。どれも具体的な数字が並ぶ中、ある広報担当者の企画書を見て、社長がふとつぶやいた。「広報の企画書はなぜいつもわかりやすいのだろう?」
この「わかりやすさ」とは、単に情報が整理されているという意味ではない。誰に何を伝え、結果として会社の何がどう変わるかが冒頭から明示されている点を指している。これは、広報担当者が意識的に取り組んだ成果である。
広報は「伝わること」を目的とするが、社内向けの企画書も本質は同じだ。経営企画との協働を進める中で、「経営者に最も伝わるのは『結果』から逆算したストーリーだ」と確信するに至った。つまり、「この施策で企業の何が向上し、それが経営戦略のどこに寄与するのか」というロジックである。
この意識を徹底することで、経営層とのコミュニケーションが格段にスムーズになる。広報企画が経営企画の資料として採用されることも珍しくなくなった。「この企画書ならそのまま経営会議に出せる」と言われたときほど、広報担当者として嬉しい瞬間はない。広報企画書に求められるのは、単なる詳細な説明やビジュアル重視のテクニックではなく、経営視点とコミュニケーションの本質を理解した「構成力」だと私は考えている。
視点2
経営計画と広報戦略を接続する企画書
広報企画書は「経営計画の翻訳書」である
経営計画と広報戦略の接続が求められる時代において、広報企画書に必要なのは、経営企画部門が策定する中計や事業計画を、ステークホルダーに向けて「翻訳」し、効果的に伝えるための具体的な施策を提示することである。
企画書を書く際には、冒頭に必ず「経営上の目的」を明示するように、私は勧めている。例えば、年度事業計画の中で設定された売上拡大目標、新規事業領域への進出、顧客満足度の向上、企業価値の最大化など、「広報活動の出発点」を明確にすることで、経営層にとってこの企画書が「自分たちが決めた目標に直結する内容だ」と直感的に理解してもらえるからだ。
「中計」や「事業計画」とのリンク方法
広報企画書には、まず中計に書かれたキーワードや具体的な数値目標を整理して記載する。例えば、3年間で「認知度を15%向上」「若年層顧客の割合を20%増加」など、具体的な数値目標を明記する。そのうえで、それらの目標を達成するために広報が果たすべき役割を、「具体的な施策」として書き出す。広報活動が経営戦略実現に直接貢献していくうえでの役割を明確にすることで、経営層から承認を得やすくなる。
図1 企画書作成のフロー
Step1 中計または年度事業計画の目標を冒頭に記載する
例:「2026年度までに認知度を現状比15%向上させる」「新規顧客層(30代以下)の獲得を30%増やす」
Step2 その目標達成のために、広報が担うべき具体的役割を記載する
例:「新規参入する若年層向け市場に対して、企業ブランド認知を拡大する」「顧客満足度の向上を狙ったエンゲージメント施策を設計・実施する」
Step3 役割に基づき設定するKGI(重要目標達成...