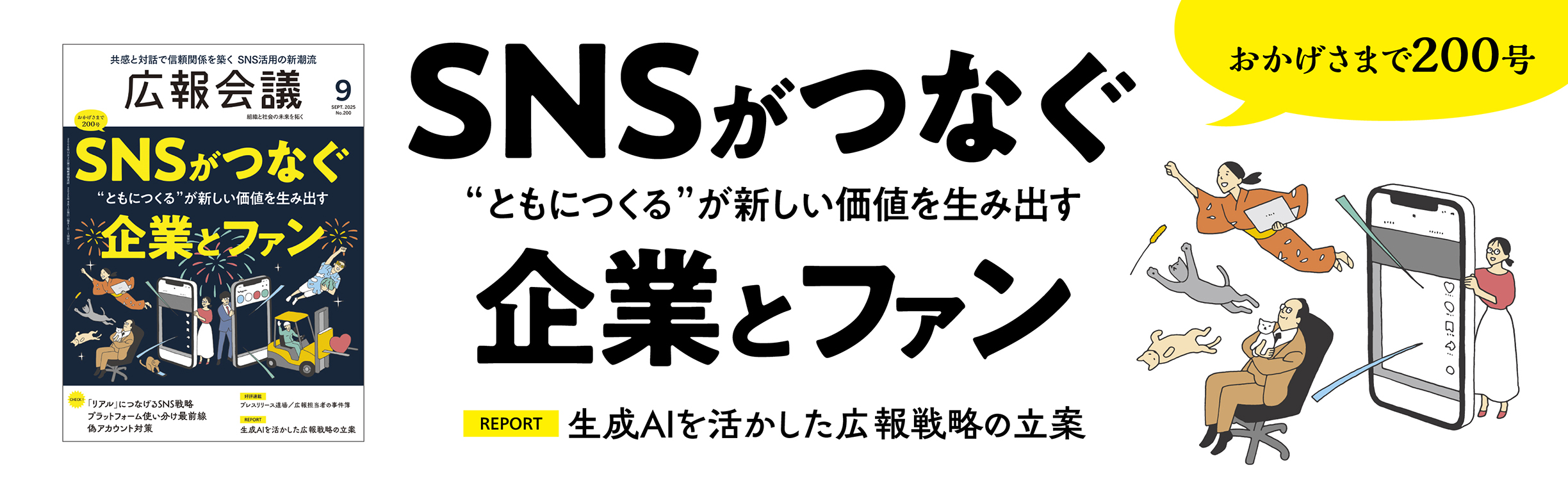成蹊大学経営学部・客員教授の高橋暁子氏は、「SNSと情報リテラシー/ソーシャルメディア研究」が専門。「SNSを安全に楽しく活用するため、現代人に必須の情報リテラシーを実践的に学ぶ」をテーマに講義をしている。企業の公式SNSアカウントの運用について、戦略のコツや炎上対策などを聞いた。
なんでもSNSで検索する時代
─現代社会における、SNSの利用状況をどのようにご覧になっていますか。
大学で学生たちの声を聞くと、現代は「なんでもSNSで検索する時代」だと言えます。SNS上の投稿を見るのはもちろんですが、検索も検索サイトではなくSNSを使うのです。
この傾向は、若年層だけにとどまりません。中高年層やシニア層でも、SNSの利用時間が増えている印象です。
─そうした中、企業の広報活動における公式SNSアカウントの運用は必要不可欠だと言えるでしょうか。
そうですね。あらゆる世代がSNSを活用するようになった現代においては、企業が自社の製品やサービスの認知を図ったり、リーチしたりするためにSNSは欠かせません。
最近のSNS利用者は、検索の際、自らの欲しいもの、気になったもの、「こうなりたい」という理想像など、なんでも入力する傾向があります。そのため、人々のニーズや気になっているワードをベースに、タッチポイントを設けやすくなっています。
─他方で、あえてSNSから撤退する企業もあります。この現象はどう見るべきでしょうか。
「自社のポリシーや考えにそぐわないので撤退する」という明確な考えがあれば、それも有効だと思います。逆に、撤退しなければその企業の本当のファンたちは、「この企業はSNS活用とは相容れない考えを持っているはずなのに、なぜSNSを使い続けているのだろう」と考えてしまいます。そのため、そうした齟齬や矛盾を解消するために必要なことです。
また、高級ブランドでもSNSから部分的に撤退している事例もあります。「憧れの対象であること」で高い価格を払って製品を購入してもらったり、「他の人たちとは違う自分になれる」ということでブランド価値を構築したりしている企業などです。これは、あえてSNSと距離を置くことでブランドイメージを保っていると考えられます。
図1 現代におけるSNSの特徴
●若年層にとどまらず、あらゆる世代がSNSを活用するようになっているため、企業広報にSNSは必要不可欠。
●SNSでなんでも検索する時代なので、タッチポイントを設けやすくなった。
●自社のポリシーやブランド戦略にそぐわなければ撤退するケースもある。
理解と共感と対話の心がけ
─SNS運用にあたり、企業は何を心がけるべきでしょうか。
キーワードは「理解」と「共感」と「対話」です。
例えば、自社の製品やサービスを買った顧客が困りごとを投稿しているのを見つけたら、「こうすればよい」とアドバイスをしたり、サポート部門につなげたりする。あるいは、顧客の怒りに対して、自社が悪いのであれば謝罪をする。「買ってよかった」などの喜びの声に対しては一緒に喜ぶ、などです。
このように顧客に寄り添って気持ちを汲むことから、対話につなげられるのが理想です。そうすることで、どのように自社の製品やサービスが使われているのかや、問題や困りごとが分かることでその後...