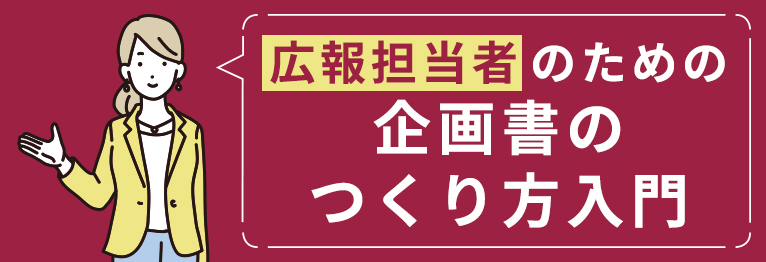「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。
「届ける前の設計力」を高める
情報発信の手段が多様化した現在、広報活動に「届ける前の設計力」が求められている。広報企画書は広報戦略の方向性と優先順位を整理し、チーム全体で共有・実行するための土台となる。加えて近年では、広報の現場でも生成AIの活用が急速に広がっている。生成AIにより、時間と人手が必要だったアイデア出しやKPI設定などが、効率的に進められるようになった。特に、「0➡1」の工程や、選択肢の比較などで大きな力を発揮している。一方で、人間ならではの判断や感性、現場経験の掛け合わせがますます重要になりつつある。今回は、広報企画書を構成する6つの主要項目(目的・ターゲット・訴求ポイント・施策・スケジュール・評価指標)について、生成AIの活用ポイントと具体的なプロンプトを考えていく。
視点1
目的・背景の言語化で論理構造を明確に
背景情報から目的を導く
広報企画書における「目的」と「背景」は、全体の論理構造を支える中核である。目的が曖昧であれば施策の正当性が揺らぐ。また、背景が弱ければ説得力を欠いてしまう。
しかし、実務において、この項目でつまずくケースは少なくない。「なぜこの施策を行うのか」を整理しきれず、漠然とした理想論や、冗長な現状説明に終始してしまう企画書も多い。
ここで有効なのが、生成AIの活用だ。特に、背景情報から「目的」を導く上では役立つ。たとえば図1のようにプロンプトを入力することで、文章の起点となる「背景➡目的」の接続モデルを即座に生成できる。ただし、「課題感」「価値訴求」など抽象的な言葉をそのままAIに投げるだけだと、的外れな出力になることもある。あらかじめ、言いたいことの「意味の芯」を人間の側で整理しておく必要がある。
図1 背景情報から目的を導く
プロンプト例
「地域住民の参加率が低迷している」という状況を背景に、広報企画の必要性を論理的かつ簡潔に説明してください。
出力例
少子高齢化により地域の担い手が減少し、従来型の告知方法では生活動線上に届かなくなっている。よってSNSや動画コンテンツなど、新たな接点による広報施策が急務である。
目的に至る論拠や必要性が言語化されることで、企画書の骨格が大幅に整理される。また、複数のバリエーションを生成させて並べることで、文案ごとのトーンや伝わり方の違いを比較できる。関係者と「現場で使いやすいのはどれか」を検討することで、主観的な違和感や部門間のズレを事前に抑えやすくなる。なお、目的が複数ある場合は、AIに「主目的と副目的に分けて書いて」と明示するのが有効だ。
論理のブレを防いだ文案整理にも応用できる。
図2 構造的な背景を踏まえた目的
プロンプト例
以下の3点を背景として、企画実施の目的を200字以内で書いてください。
①若年層との接点が希薄化している
②SNS告知の反応率が前年比20%減少
③従来イベントは高齢者層中心に固定化
出力例
若年層との接点が希薄化し、SNS告知の反応率が前年比20%減少している現状を打破するため、デジタルとリアルを融合した新たな顧客体験の創出を目指す。従来のイベントが高齢者層中心に固定化していることを踏まえ、若年層の興味関心に合致したコンテンツ開発とSNSを活用した双方向コミュニケーション戦略を展開。世代間の垣根を越えた参加型プログラムにより、多様な年齢層が共創できる場を構築し、ブランドとの継続的な関係性構築と顧客生涯価値の向上を実現する。
生成AIは文章を「整えてくれる」だけでなく、「考えを構造的に引き出す」ツールとして活用できる。特に、書き手の頭の中にある情報を咀嚼し、可視化し、骨格にしていく過程において、有力なパートナーといえる。
コラム
企画名(タイトル)のつけ方
企画タイトルは意思決定者の第一印象を左右する重要な要素だ。事務的すぎれば埋没し、キャッチーすぎれば内容との乖離が生じる。このジレンマを解消するツールとして生成AIが有効である。
企画の核となるキーワード(例「サステナビリティ」「新卒採用」「周年イベント」など)を入力し、「広報企画タイトルの案を10個」と指示すれば、多様な表現案が即座に得られる。生成AIの強みは、「想い」に訴えるもの、「行動喚起」を促すもの、「数字」で具体性を持たせるものなど、異なる訴求軸の案を短時間で提示できる点にある。人間はこれらから企画の本質に合致するものを選別する役割を担う。
また、文末表現を「◯◯プロジェクト」「◯◯キャンペーン」「◯◯チャレンジ」と変えることで、企画の性質や規模感の印象を調整できる。タイトルの検討は創造的思考と分析的判断の両面を要する。生成AIを活用することで、この過程を効率化し、より本質的な議論に時間を割くことが可能となる。
視点2
ペルソナ作成から媒体選定まで
ストーリーのある人物像
広報企画において、ターゲットの明確化による訴求力向上は重要である。「20代女性」や「子育て世代」といった属性だけでは、行動特性や価値観にまで踏み込めず、効果的なメッセージ設計や媒体選定には至らない。大切なのは、より詳細な人物像(ペルソナ)の設定である。
従来のペルソナ作成は、調査やインタビュー、社内議論などを通じて多くの時間とリソースを要していた。しかし、生成AIの活用によってこの工程は飛躍的に効率化される。
図3 具体的なペルソナの作成
プロンプト例
地方在住で芸術系大学を志望する高校生女性のペルソナを、行動習慣・悩み・SNS利用傾向・価値観を含めて作成してください。
出力例
● 名前:あかり(仮名)/17歳/山形県在住
● 行動習慣:平日は高校の美術部活動、休日はYouTubeでメイク動画やVlogを視聴。通学中はSpotifyで音楽を聴く。
● 悩み:周囲に進路の相談相手が少なく、都心との距離に不安。親と進学費用の話もしづらい。
● SNS利用傾向:Instagramで進学先のオープンキャンパス情報を検索。X(旧Twitter)では美術系アカウントをフォロー。広告色の強い投稿は嫌い。
● 価値観:「自分らしさ」を重視し、地域に貢献する生き方にも関...