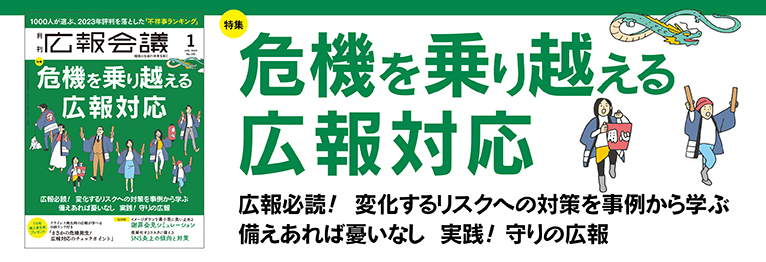2023年は、不祥事に関する記者会見での不適切な対応や準備不足により、さらなる企業(組織)イメージの悪化につながった事案が目立った。本内容を参考に、平時からのシミュレーションがその後の明暗を分けることを留意したい。
組織のクライシスが発生すると、矢面に立たなければいけないのは広報担当者だ。発生直後からひっきりなしに鳴る電話でメディアの詰問に耐え、また必要だと判断した場合は記者会見を開催する。すべての質問に誠意をもって対応し、分かりやすく答えきらなければならない。
企業の印象は広報で決まる。広報が曖昧な回答しかできず、何を聞かれても「少々お待ちください」「分かりません」「お答えできません」を連発していると「あの組織はだめ」のレッテルを貼られてしまう。何事も「逃げずに」「すべて答え」「分からないことは分からない」「言えないことは言えない」と言い切る力をつけることが求められる。
ただし「分からない」「言えない」理由をしっかりと説明するためには、初動の際にいかに早く、社内での対応方針を定めることができるかにかかっている。
対応方針の明確化を
クライシスの対応は、時間との勝負ともいえる。発生から3時間以内に情報収集・集約を終えることが、その後の企業イメージに大きく関わってくる。過去のクライシス事例が証明するように、表面的な対応に終始したり、隠蔽を重ねた末、内部告発などにより不祥事が次々と発覚したりすることで、企業価値の失墜を招いてしまうこともある。
このためにできるのは、クライシス発生後に「どのようなプロセス」で、「いつ」「どんなこと」を遂行すべきかを頭に入れておくことだ。いざクライシスが発生したら、冷静さを欠き不適切な対応を招きやすい。日頃より大まかな対応プロセスを頭に入れ備えておくことで、有事での企業イメージの低下を最小限にとどめたい。
ここでは、不祥事が発生した後、記者会見を開いて事後対応をするまでのシミュレーションを見ていきたい。
❶初動対応(直後~3時間)
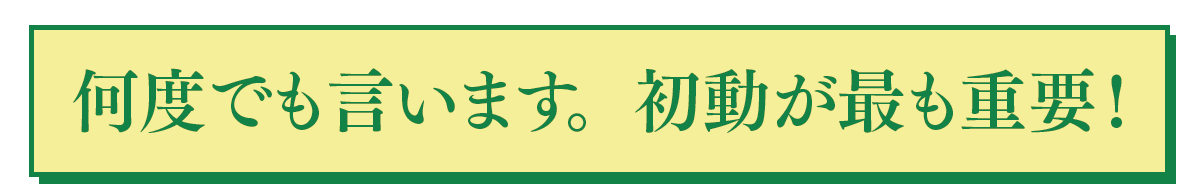
広報の責任者と危機管理担当者が中心になり、行動開始。何が起きたのか、正確に把握する。
①全社の対応方針の決定
●対策本部設置の号令後、関係者は30分以内に集合すること(出張等で不在のときは、代理が出席)。
●対応方針は、発生した(または認識した)直後から3時間以内に決める。対策本部長(大概の企業は社長)を中心に状況把握に努め、即断・即決が重要。迷いは最大の敵!
●メディアへの対応方法を決める。
【電話対応】の対応者を徹底
メディア対応は広報および発生部署の社員で一元化し、他の社員には対応させない。とくに、会社の敷地外でのコメントを求められるインタビュー等には「広報に訊いてください」で統一するよう社内に徹底する。
【公表方法】の方向性確認
この時点では、資料配布にするか記者会見を行うかは決められない場合がある。被害の程度、社会的影響度等で判断していくことになる。
NG
当事者意識のない対応や責任転嫁がにじむ対応
②情報収集、情報集約、情報整理の開始
●下記3班に分けて対応する。
情報収集班→すべての情報を迅速に集める
情報集約班→情報収集班が集めた情報を、時間、対象者、事象内容等に整理する
情報整理班→集約された情報をもとに、想定問答(Q&A)を作成する
●対策本部で決めていくが、要は平時に役割分担を決めておくこと(各班は広報だけでなく他部署も一体となって対応する)。
NG
「これは関係ない情報だから」と無視することがひとつでもあってはならない
NG
「俺は仕事が忙しいから手伝えない」などと忙しいふりをする社員はもってのほか!