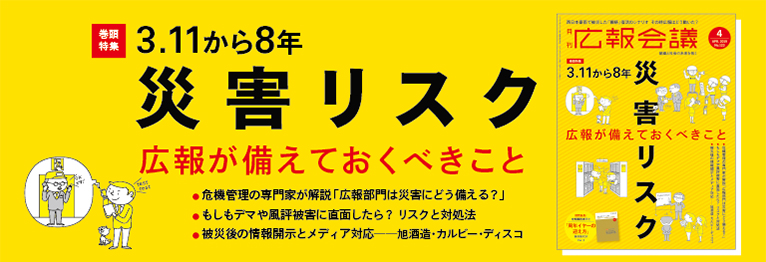2017年、前年の台風の影響で店頭から一部のポテチが消える"ポテチショック"が発生。カルビーは、その後傾いた世論を立て直し、地域に恩返しをするプロジェクトにつなげた。優れた広報対応だとして、第34回企業広報大賞も受賞した、一連の取り組みの裏側に迫った。
「またポテトチップスがなくなるのでは……」。2018年9月6日、最大震度7を記録した北海道胆振東部地震が発生。北海道内に2つの自社グループ工場を持つカルビーは、停電の影響でそのすべての操業を停止した。その時、世間が連想したのが2017年4月の"ポテチショック"だった。
実際には、同社のポテトチップスの製造拠点は他地域にもあるため、商品供給に支障はなく、9月10日には工場を再開することができた。それでも、地震発生当初は"ポテチショックの再来"を不安視するメディアからの問い合わせが相次いだ。
コーポレートコミュニケーション本部の川瀬雅也氏(広報部 広報課課長)は「広報部門は本社にしかなく、情報を集約するのが大変だった。現地の従業員と連携しながら冷静に対応した」と話す。
基本的には、社員の安否や工場の被災状況、得意先や物流の状況などを、各部門から集約し、問い合わせに対応した。その際、再び"ポテチショック"が起きないように、「生産」に関する発信は、消費者の誤解を生まない伝え方を意識したという。
現地スタッフからの発信もあり、例えば北海道工場では、社内のイントラ(9月18日)や一般向けブログ「ポテトな毎日」(9月20日)に従業員らの写真を掲載。社内外に復興の様子を伝えた(図1)。

図1 北海道工場のスタッフブログ「ポテトな毎日」
2018年9月20日に「元気です北海道!」と題した記事を公開。消防訓練の様子とともに、従業員らが「元気ですCalbee 元気です北海道」という紙を持って復興の様子を伝える写真を掲載した。
川瀬氏は、「被害の大きさの違いはあるので並列に語ることはできないが、地震による工場の操業停止が社会に大きな不安を与えなかったのは、"ポテチショック"での反省と、その後の戦略的な情報発信の積み重ねによるものがある」と分析する。
消費者の混乱を抑える
「"ポテチショック"の際には、私たちが発信した情報で、お客さまにご心配とご迷惑をおかけしてしまった」と川瀬氏。
"ポテチショック"は、2016年8月末に発生した台風10号の影響で北海道産のジャガイモが不作となったことが原因で起こった騒動。カルビーは2017年4月10日のリリースで「ピザポテト」「ポテトチップス BIGBAG」などポテトチップス15商品を販売休止とすることを発表。すると、メディアは一斉に品薄状態になったスーパーの棚や、不作になったジャガイモ畑の写真や映像を流した。
TwitterなどSNS上でも「最後に食べておかないと」などと、危機感を煽るような投稿が拡散した。そして、ポテトチップスが永久的に入手できなくなると勘違いした消費者が商品をたくさん買い込んだり、オークションサイトに高額出品したりと、パニック状態に発展した。「商品が完全になくなってしまうわけではないのに、間違った情報が独り歩きし、市場の混乱を招いてしまった」と川瀬氏 …