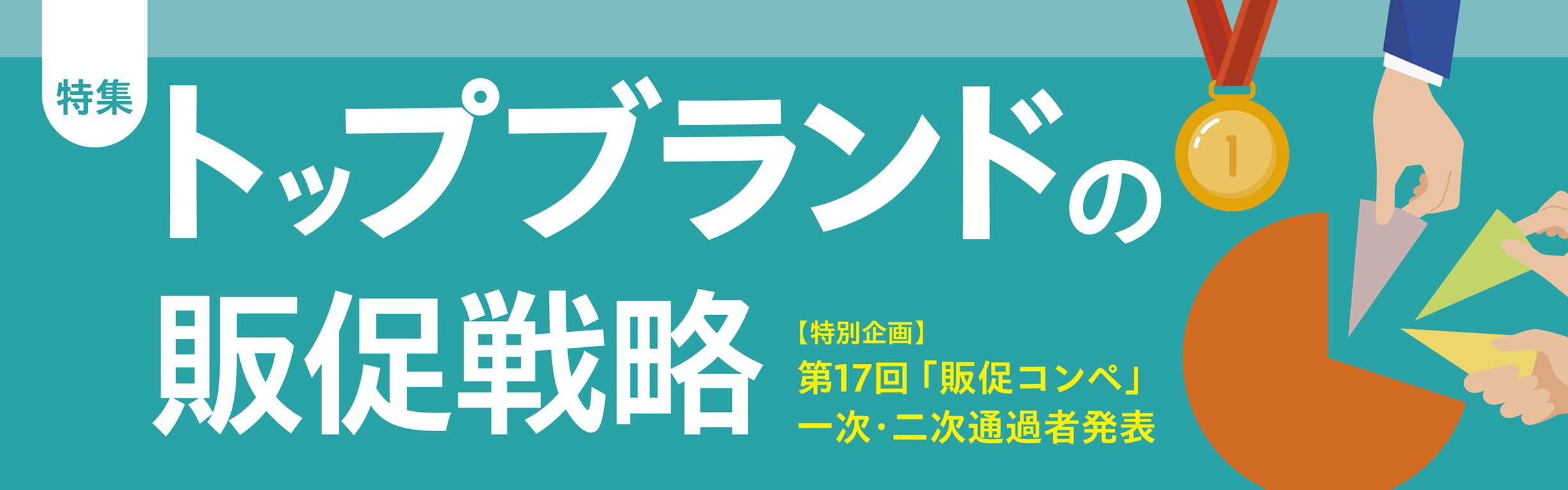SNS時代には、計画通りに進めるだけでなく、予測不能な偶発的広がりを設計する視点が不可欠だと言われている。そんな偶発購買を利用して、新興ブランドが下剋上シェア拡大を実現する方法について、『偶発購買デザイン「SNSで衝動買い」は設計できる』(宣伝会議刊)の著者である宮前政志氏が、「企業ブランド」と「ユーザーブランド」の視点から解説する。
新しいアイデアやこだわりを込めて商品を世に出したのになかなか話題化しない、SNSで話題にしたいのに拡散されず、広告やPRを頑張っても大手ブランドの壁が厚い──そんな経験はありませんか?その背景には、「企業ブランド」と「ユーザーブランド」どちらかに偏った設計になっているという課題があるかもしれません。企業が伝えたいことばかりを強調し、ユーザー視点の“共感”や“拡散されやすさ”の設計を怠っていることが、強者に勝てない大きな原因なのです。
ここで有効なのが、「企業ブランド」と「ユーザーブランド」の“サンドイッチ設計”。前者の「企業ブランド」の設計では企業側主語の価値・存在意義を伝え、「ユーザーブランド」設計ではユーザー主語の共感・愛着やトレンドを育むイメージです。両者をバランスよくサンドイッチのように重ねて設計することが、強いブランドを生み出す“布石”となります。
話題の種を仕込む5つの視点「CRISP」
ここで、企業として押し出したいブランド価値を...