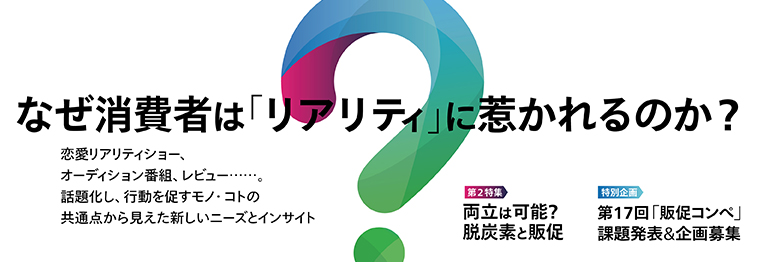恋愛からアイドルオーディションまで、人々のリアルな反応や予測不可能な展開を楽しむリアリティ番組。動画配信サービスを中心に人気を集めている一方で、視聴者から「これはやらせでは?」と一度疑いの目を向けられると、視聴者の信頼を失うリスクも存在する。リアリティ番組が人気になり、視聴者の目が肥えているからこそ重要なのは、制作者と視聴者の間で、どこまでが「演出」で、どこからが「リアル」なのかという共通理解を成立させることではないだろうか。本稿では、メディア論を専門にする昭和女子大学人間社会学部准教授の村井明日香氏が、リアリティ番組の現在地とリスクを解き明かし、コンテンツ制作や販促における「誠実な演出」のヒントを探る。
人気が加速するリアリティ番組のこれまで
2020年、恋愛リアリティショー『テラスハウス』に出演していた女性が自ら命を絶ち、リアリティ番組の制作方針やその社会的影響について議論が巻き起こりました。しかし、リアリティ番組の人気は現在もなお衰えることなく、むしろさらに広がりを見せています。
例えば、Amazon Prime Videoで配信されている『バチェラー・ジャパン』は、1人の男性を約20人の女性が奪い合うという独自の設定が人気を集め、シリーズ化。また、Abema TVで配信されている『オオカミには騙されない』シリーズは、10代の恋愛模様を描き、特に若年層の視聴者を中心に支持を集めています。さらに、デビューの瞬間までを追いかけるサバイバル・オーディション番組も人気が高く、グローバルで活躍するスターの誕生を見守るプロセスに、多くの視聴者が釘づけになっている状況です。
これらリアリティ番組の最大の魅力は、出演者が設定された状況下で見せる「リアルな反応」や「予測不能な展開」を視聴者が“のぞき見”できる点です。こうした形式の番組は、『元祖どっきりカメラ』や『はじめてのおつかい』、『大改造!!劇的ビフォーアフター』『逃走中』シリーズなど、これまで放送されてきた数多くの人気番組にも見られます。
しかし、それらの番組と比較して、現在注目を集めるリアリティ番組は、複数の参加者たちによるゲーム的要素が特徴的です。この先駆けとなったのが、1999年にオランダで放映された「Big Brother」でした。番組は、外界から遮断された男女のグループが、一定期間、一定の場所で生活をしている様子をカメラが24時間記録するというものです。この番組の大ヒットをきっかけに、リアリティ番組のフォーマットが世界的に普及したとされています。
周知の通り、日本でもネット配信を中心に、多くの人々が視聴しているリアリティ番組。これほどまでにその人気が高まっているのは、動画というメディアの特...