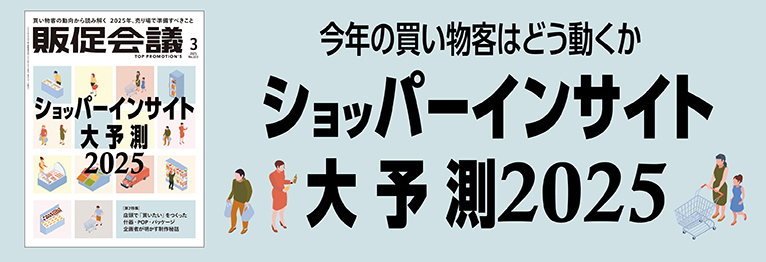メーカーの商品が小売によって「売り場」に陳列され、そこで、ショッパーが商品を購入する。商品購入の最終的な意思決定の場である「売り場」で「買いたい」をつくるための方法として、今注目されているのがトレードマーケティングだ。フェズの事業企画部長であり、キャプロ代表取締役社長/トレードマーケターも務めている井本悠樹氏がトレードマーケティングの実践方法について語る。
近年、メーカーの小売企業を通じた販売活動、売り場提案の難易度が急激に高まってきています。もはや、いわゆる大手メーカーのマスブランドから発売された新商品ですら、必ずしも配荷が確約される状況ではありません。さらに、これまで高頻度で定番棚以外のアウト展開を獲得できていたブランドであっても、その獲得や継続が以前より難しくなってきているのです。
この「販売活動・売り場提案の難易度上昇」を俯瞰して捉えると、それが単なる「商品力の差」では片づけられない問題だと理解できるはずです。ここで強く影響しているのが近年の小売業界を取り巻く大きな環境変化。具体的には「メーカー環境」「小売環境」「消費者・ショッパー環境」の変化です。
モノが売れない時代にトレードマーケティングを
まずはメーカー環境の変化です。近年、円高・原油高・原料高など、製造原価を上昇させるマクロ環境の変化が継続的に起こっており、多くのメーカーでは利益を確保するために、変動費である広告宣伝・販促投資を優先して削減せざるを得なくなっています。これが結果として「物を売るための武器」である投資自体の直接的な減少を招くことになっているのです。
また、小売環境も大きく変わってきました。従来、小売企業の国内の成長戦略においては、出店戦略がメインでしたが、近年では「M&A」という手段が一般化しました。それにより小売企業のバイイングパワーが拡大し、メーカーにとって取引条件の難化が生じています。
さらに昨今は、DtoCからスタートしたブランドが店頭販売されるケースも増えており、店頭での「ブランド・商品数の急拡大」を引き起こしています。単に良い商品を発売するだけでなく、これまで以上に売れる・儲かる根拠、メリットを提示できないと配荷を獲得できない状況なのです。
そして消費者・ショッパー環境においても、コロナ禍で強いられた「新しい生活様式」により、買い物頻度が大きく減少しています。ただ、根本的に必要なモノが減少するわけではないため、買い忘れを防ぐ目的の計画購買(事前に買うものを想定した買い物)を急速に促進する結果となりました。
また、コロナ禍におけるデジタル化の影響もあり、計画購買同様に買い物の前のデジタル上での事前の情報収集が当たり前になっています。ショッパーは店頭で買いたいものを見つけるだけでなく、…