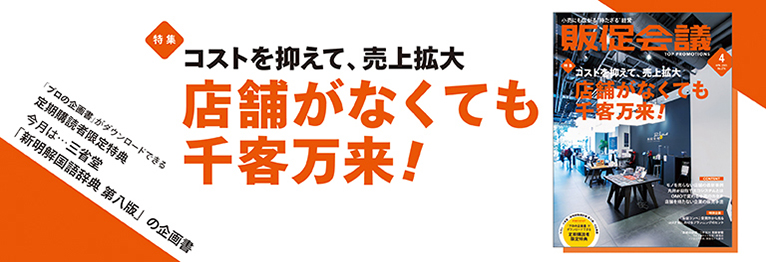小売業に大きな変化が求められる中、丸井グループは従来とは異なる舵をきってきた。どのような変化を起こしてきたのか、レポートする。

新宿マルイ 本館
丸井グループは、創業時から行われてきた小売・金融(フィンテック)一体の独自のビジネスモデルが特徴だ。金融事業ではクレジットカード、つみたて投資などの事業を推進している。小売事業では、若者向けの衣料品店が売場の中心だったが、世の中の変化に合わせ、ビジネスモデルの革新、進化をさせ続けている。その直近の流れについて見ていこう。
百貨店型から不動産型へ
同社は2014年から、これまでの商品を仕入れて販売する「百貨店型」の店舗から、ショッピングセンター(SC)のようにスペースを貸す「不動産型」への転換を進めてきた。そのため収益構造も、消化仕入売上高から賃貸収入へと変化。同時に社会のニーズの変化をとらえて食や体験などのテナントを増やし、業態の転換を進めた。
その結果、丸井グループの小売事業の営業利益は増加していき、大幅に収益改善していった。しかし、デジタル化の波が大きくなっている状況において、これだけでは不十分だと同社は考えた。商品をネット上で購入する流れが加速し、リアル店舗ならではの価値を付加していく必要があったのだ。
「売ること」を目的としない店舗
同社は不動産型に転換し、機動的な店づくりが可能になったことにより、モノやサービスを売ることを目的としない、体験やコミュニティという価値を提供する「未来の店舗」の創造に向けて動き出し始めた。
現在推進しているのが、「売らない店」への転換だ。リアル店舗を主体とした従来の小売のビジネスモデルから、デジタル主体の店舗運営への移行を目指す。D2Cやシェアリング、サブスクリプションなどを手がけるデジタル・ネイティブなブランドの出店を強化。リアル店舗を持っていない、ネットで急成長している有望な企業をいち早くテナントに誘致しているのだ。
丸井グループは「デジタル・ネイティブ・ブランド」の共通点として次の3点をあげている。
①リアルとデジタルの主従が逆転=アフターデジタル