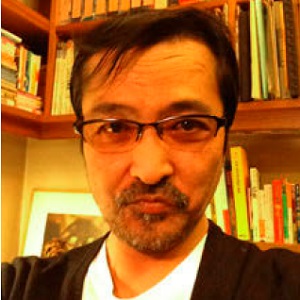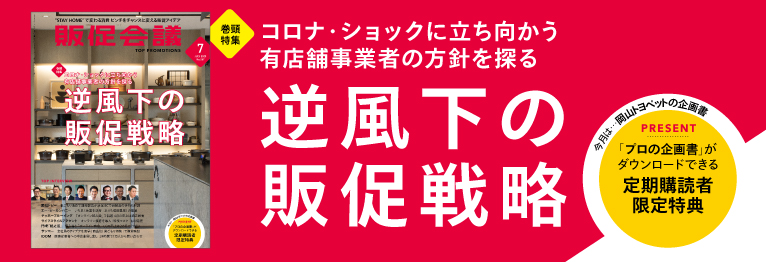「新しい生活様式」の提案とともに、ネット通販の利用が伸長している現在。「リアル店舗にあって、ECにないもの」の追求が、今こそ必要とされている。その解決策のひとつが、選ぶ楽しさを提案する「メディアコマース」だ。
ECサイト メディア化のためのポイント
1 商品を「オリジナル」化して、他店との差別化を図る
2 トップページを「目次」化して、雑誌のような楽しさを
3 複数のサイトを「ペルソナ」で、つくり分けして運用する
新型コロナの影響で外出ができず、家での生活を余儀なくされる中、SNSでユニークな動画をシェアする人が増えたり、“リモート帰省”で実家に孫の顔を見せてあげたり……。多くの人が日々ストレスを抱える中、インターネットは確実に私たちの日常に“癒やし”を与えてくれました。ふた昔前、テレビと黒電話しかなかった時代を想像するとゾッとします!
「待てる買い物は通販で」の流れ
さて、本題。今回のコロナ禍で、政府が設置した専門家会議は、「人との接触を8割減らす、10のポイント」を掲げ、その中で“待てる買い物は通販で”と呼びかけました。これに便乗するかのようにネット通販は売上を伸ばしたようです。
しかし、ひとつ気になることがあります。“ステイホーム”を強いられ、外へショッピングに出かけられない消費者たちのストレスを、ネット通販は少しでも和らげることができたのでしょうか。
先日、テレビの情報番組で「ネットでよく売れている商品」を伝えていました。想像通り、巣ごもりのための商品が多くランクイン。ゲーム機、ホットプレート、フィットネスマシン、ケーキづくりの道具や材料、テレワークのためのウェブカメラなどです。しかし考えてみると、これらは刹那的に売上をアップさせるものの、あくまで一過性の“コロナ特需”と言えるものでしょう。普通に街のお店が開いていれば、そちらでも売れる。つまり、消費者需要を市中の店とネット通販で食い合っている状況です。
今回、「緊急事態宣言」で盛んに外出自粛が叫ばれましたが、当初は繁華街の人混みがなかなか減りませんでした。しかし、百貨店やブランドショップ、家具や家電の量販店などが休業し始めた途端に、人の姿が消えました。道行く人たちが皆ショッピングをしていたわけではないと思いますが、やはり“街のお店”には「ちょっと楽しそうだから覗いてみようか!」といった吸引力があるのですね。
店舗にあって、ECにないもの
例えばユニクロは、老若男女の幅広い層のお客さんで賑わいます。もちろん同店の知名度も強みでしょうが、品揃え、品質の良さ、安さ、接客、店内の清潔感など、ユニクロファンにとって、そこは家族や友人を誘い合って出かけたい“気持ちのよい場所”なのでしょう。
コロナによる外出自粛が解除となれば、早速、あちこちから「ユニクロにでも行く?」の声が聞こえてきそうです。「無印良品」もフリークの多い店として有名です。ミニマリストやすっきり暮らしたい派の“ムジラー”たちは、同店の商品を使ってどんな風にアクセサリーを収納したかをInstagramで報告したりします。コミュニティに参加する彼女らにとっては、避けて通れない店になっています。
黄色い建物でおなじみの「ドン・キホーテ」の売り場にも工夫があります。あえて商品の陳列を雑多にして、宝物探しのような買い物を演出しているのだそうです。たしかに若いカップルなどは、これといった買い物がなくても各フロアを歩き回り、デートスポットのように楽しんでいる気がします。
一方、ネットショップはどうでしょう? 現在のネット通販は「検索」によって商品を探す買い物が主流。サイトはシステム制御され、即座に目的の商品が見つかるし、カートに入れる導線もスムーズです。ムダのない合理的な売り場ではあるのですが、その買い物が“楽しい”か?と言われると少し疑問が残ります。
サイトへの集客に関しても、ポータルサイトから検索する際のSEO対策やリスティング広告に頼りがちなので、そもそも“店”としての存在感が希薄。街のリアル店舗のように「退屈だからあのお店でも覗いてみようか!」とはなりにくいのですね。消費者はネット通販で、もっと“楽しい”買い物ができないのか。そのためにはやはり、ショップの“箱(サイト)”に手を加えないとならないでしょう。
一部の膨大な商品数を扱うECサイトの場合は、“商品の豊富さ”という圧倒的なアドバンテージがありますから、現状通りデータベースのような“検索マシン”としての機能を追求すればよいと思います。
ただし、そうしたニーズはすでにAmazonや楽天といった大手通販モールによる寡占状態です。これから立ち上げるECショップや、中規模ネット店(個人も含む)が同じビジネスモデルで挑むには限界があるでしょう。そうであるなら、直接“お店”をめがけて訪問してもらえるような個性的なサイトへのリニューアルを考えてみてはどうでしょうか。
いくつか、リニューアル例のポイントを解説していきます。
point 1
商品を「オリジナル化」して、他店との差別化を図る
ひとつ目は、販売する「商品」をオリジナル化する方法です。先日、テレビのBS放送で「プロが選んだ大吟醸酒5本セット」という商品を見つけました。通販企業の唎酒師バイヤーが、美味しい大吟醸酒を5種類選んでパッケージしたのだそうです。選び方はその唎酒師バイヤーの独断ですが、そこがまた面白い。購入者は家で唎き酒をするように楽しめるというわけです。単品のお酒が並んでいるだけの量販酒店にはないオリジナルの企画。ボクを含めた“左党”にとっては魅力的な商品でしょう。
残念ながらこの時は「この前、友人から旅行みやげに日本酒をいただいたばかりだったなぁ……また今度にしとこ」となりましたが、後日、思い出してネットで調べたら一発で出てきました(これもオリジナル商品のおかげ!)。
ここからは仮定の話ですが、もしもアクセスしたサイトの「唎酒セット」の隣に「一流パティシエ厳選『紅茶シフォンケーキ』3種セット」の商品バナーがあったらどうでしょう。ボクは思わず奥さんに声をかけます。「あら美味しそう!」。“プロが厳選!”という企画につられて、まったく嗜好のちがうAさん(ボク)とBさん(奥さん)が一緒にお店にいます。
「他にどんな“厳選”があるんだろう?」と、しばらくサイト内を回遊していると、今度は隣にいた娘が“干物”の売り場を見つけて「コレ、おばあちゃんに送ったら?」と言い出しました(これは本当の話!)。どうやら母の日を勘違いしたらしく申し込みませんでしたが、娘はこの時、頒布会という商品形態を初めて知ったようです。とにもかくにも、これでCさん(娘)もこのお店を認知したことになります。
ずいぶんと手前ミソな空論で恐縮でしたが、商品をバラバラと陳列しているだけだったら、決してこのような情報伝播や集客は果たせません。オリジナル(個性)の企画は、その店でしか味わえない体験としてインプットされ、次回は顧客の方から直接、お店(サイト)に来てくれるきっかけとなります(最初は偶然テレビで観ただけだったのに……)。
そして一度訪れた際に...