あらゆるコンテンツにおいて、人権やジェンダー、多様性などへの配慮が求められる現在。一方で、厳しいコンプライアンスや炎上を恐れるあまり表現が萎縮してしまう、といった悩みを抱えているクリエイターやビジネスパーソンも多いでしょう。今回の青山デザイン会議に集まってくれたのは、電通のクリエイティブ・ディレクター、コピーライターとして、伊藤忠商事「キミのなりたいものっ展? with Barbie」、世界えん罪の日新聞広告「真実は、曲げられる」などを手がけ、今年2月に『クリエイティブ・エシックスの時代』(宣伝会議)を上梓した橋口幸生さん。成城大学准教授としてメディアのなかに描かれる障害表象や、笑いと規範の問題について研究を行い、映画作品における障害の描かれ方を考察した『スクリーンのなかの障害』(フィルムアート社)などの著書もある塙 幸枝さん。今求められる多様性や表現とは?そして、世界をより良くするための倫理観について考えます。
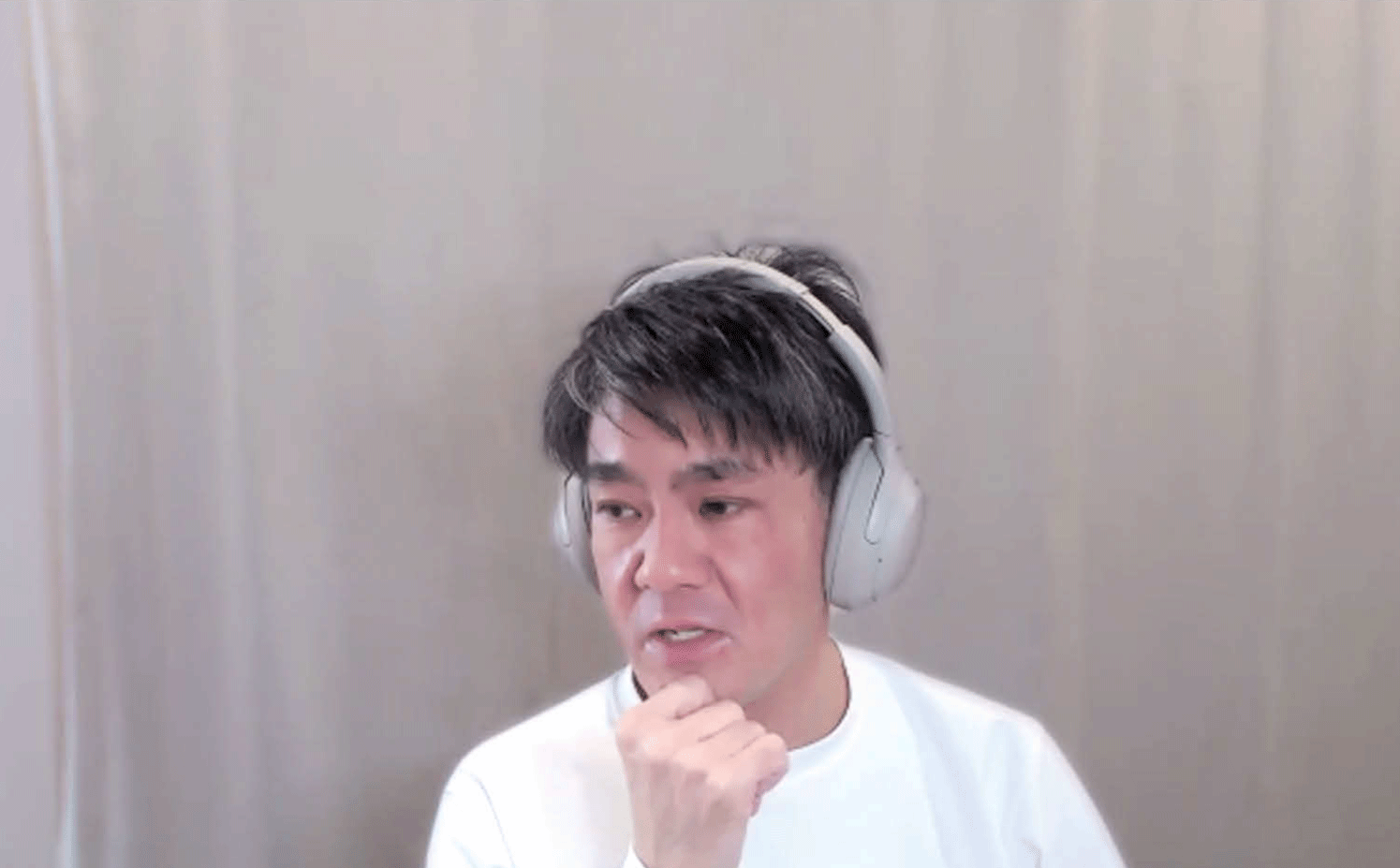
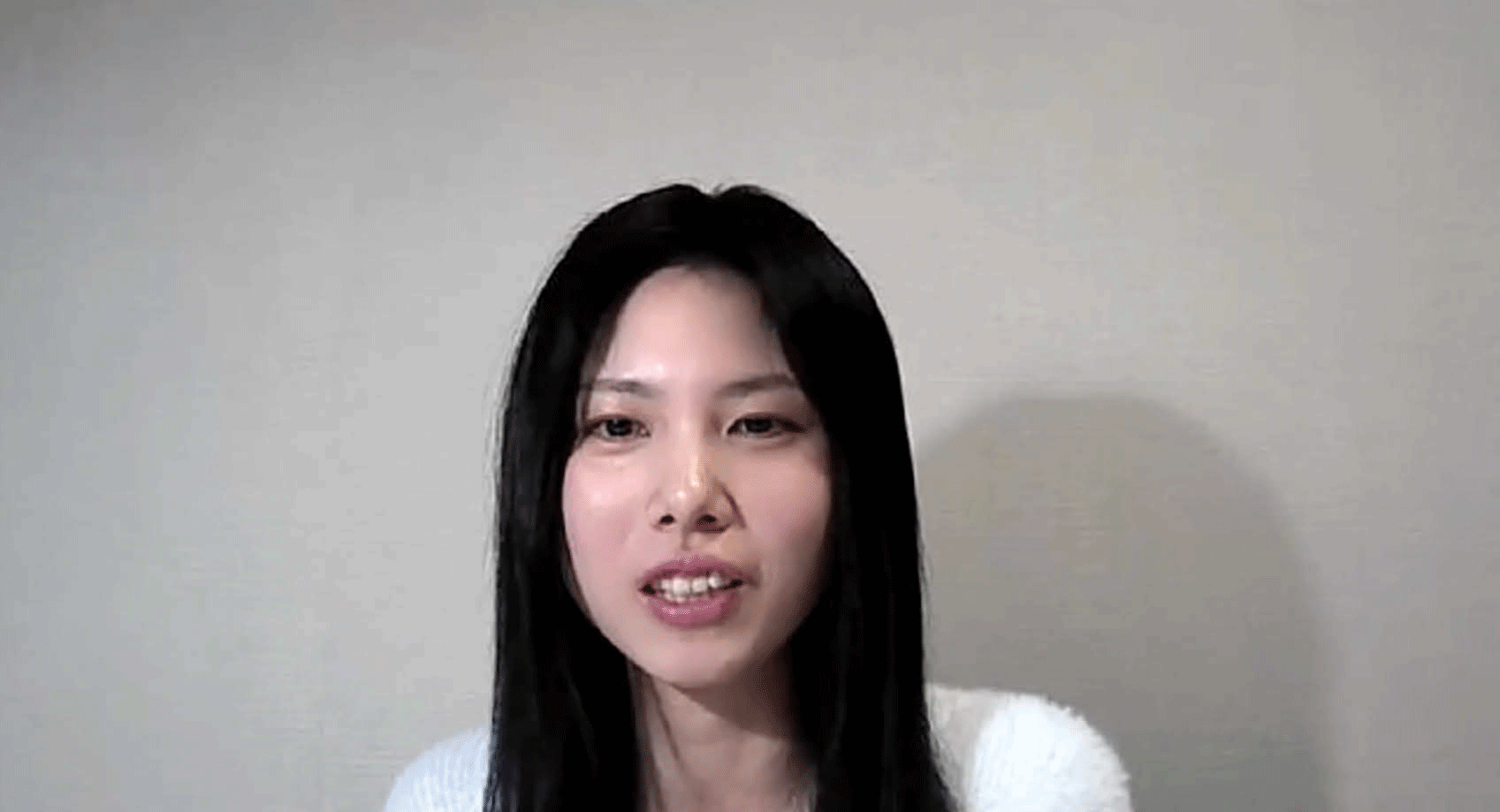
広告や映画における「多様性」
橋口:電通で、広告のクリエイティブ・ディレクターやコピーライターをしています。僕が『クリエイティブ・エシックスの時代』という本を書いたきっかけのひとつは、広告のクリエイターと、塙さんの本にも登場しているような映画やドラマのクリエイターとの間に、意識の差がありそうだと感じたことでした。
塙:私は普段、成城大学で教員をしています。昨年の11月に、映画における障害者の表象がどう変わってきたか、また障害者の当事者俳優がどういう状況にあるのか、といった研究をまとめた『スクリーンのなかの障害』という本を出版しました。
橋口:たとえば、最近のハリウッド映画って、女性や黒人、アジア人、障害者といったマイノリティとされてきた人をキャストに起用するケースが増えていますよね。広告以外のジャンルでは、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)やリプレゼンテーション(多様性を反映した表現)が当たり前になってきているのに、広告クリエイターは「女性を出さないと怒られるんじゃないか」とか「こういう表現をしたら炎上するんじゃないか」とか、すごく後ろ向きな姿勢で仕事をしている。その意識を変えたいと思って、この本を書きました。
塙:実は、私の研究テーマは元々「笑い」だったんです。そのときに、なぜか笑いという事象から障害とか障害者といった存在がつまはじきにされていることに気付いて、障害者表象の変遷を読み解くことに注意が向いていきました。橋口さんの本は、自分の興味関心と重なるところが大きくて、本当に面白くて!
橋口:広告にとって映画は表現の先輩でありお手本なので、とても嬉しいです。
塙:結局、作品をどう読むか、作品とどう対峙するかって、「どうすれば今より良い世界をつくれるか」という倫理の問題にも通じることだと感じて。橋口さんは、もちろんつくり手の視点で書かれていると思いますが、映画の受け手=観客にとっても「エシックス」は必要だよな、と。
橋口:広告的な発想だと、やっぱり「(マイノリティを)出すこと自体」に意義があるんです。それ自体は間違っていませんが、塙さんの本で語られていたのは、そのあとの話。観客はどう捉えているのか、また表現はどのように変遷してきたのかが解説されていて、映画好きでもあるので、めちゃくちゃ面白く読みました。
塙:ありがとうございます。
橋口:多様性って、僕はそれほど難しいものではなくて、「実社会に存在する人々をそのままメディアでも描く」というシンプルな話だと考えています。ただ、これまで映画や広告がつくってきたステレオタイプの表現が「標準」になってしまっていて、マイノリティとされる人をメディアに出した瞬間、「わざとらしい」とか「ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)を意識しすぎている」みたいに言われてしまう。実社会ではなく、表現上のステレオタイプが参照されてしまうんです。
塙:映画の世界では最近、聴覚障害者の両親を持った高校生が主人公の『コーダあいのうた』(2021)のように、ポジティブなメッセージのある作品が注目されています。ただ、かつては障害者が非常に差別的に描かれていた歴史があって、たとえば『フリークス』(1932)ではモンスター化された存在として、その後は『エレファント・マン』(1980)のように同情の対象として、そして『レインマン』(1988)や『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)のように有能力化された存在へと変わっていきました。
橋口:広告の世界でも、…
