巻頭特集でも、さまざまな企業・ブランドのアップサイクルに関わる取り組みやクリエイティブを紹介しましたが、青山デザイン会議では、さらに「地域」にフォーカス。集まってくれたのは、富山と東京を拠点に、50~100年前につくられた和だんすにアクリルを組み合わせたアップサイクル家具ブランド「P/OP」をはじめさまざまなプロジェクトを展開する、家’sの伊藤昌徳さん。日本で初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県

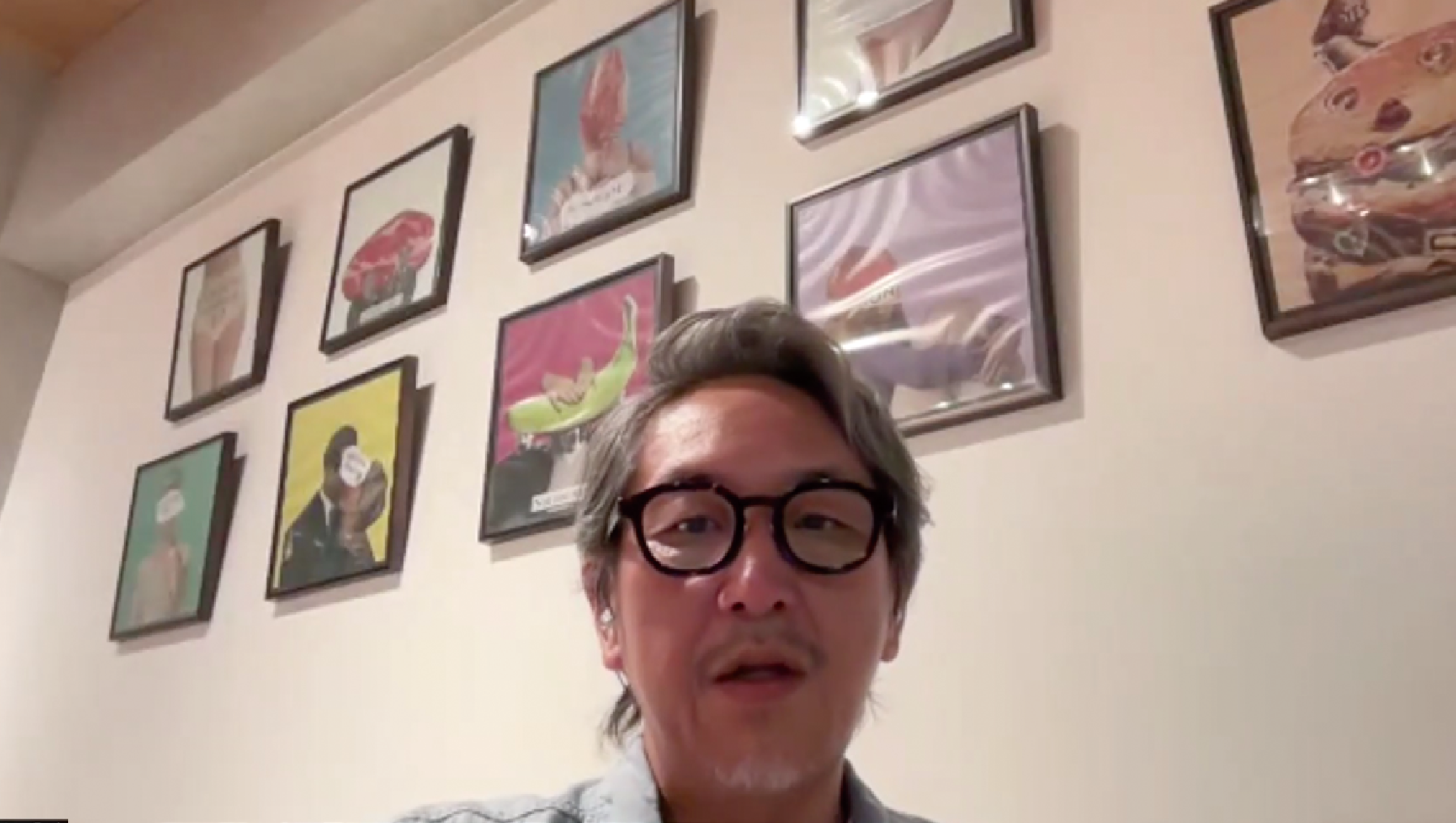

地域の課題をアップサイクルで解決する
伊藤:富山と東京を拠点にして、骨董的な価値がないものにどうやって価値を与えていくかをテーマに、アップサイクル家具の販売など、さまざまな事業をしています。古い和だんすや木彫りの熊といった、デザインが素晴らしいものが捨てられてしまうのは、もったいないと感じて。
田中:我々は、町から出るゴミをゼロにする「ゼロ・ウェイスト」を掲げる、徳島県上勝町で活動しています。クラフトビールをつくったり、上勝町ゼロ・ウェイストセンターというゴミステーションでホテルを運営したり、すごい秘境で、ビジネスをするのはめちゃくちゃ難しい地域なのですが。
山本:廃棄される植物性の原料から衣食住にまつわる素材づくりを行う、Curelaboという会社で代表を務めています。最初は沖縄からスタートして、京都や広島県の福山、山形などを拠点に、日本全国でアップサイクルを軸にしたプロジェクトに取り組んできました。
田中:私は元々、徳島市で創業50年を超える会社を経営していたんです。徳島市の中心市街地がどんどん寂れていくのを目にして、地域の活性化をしたいと考え始めたのが2007~2008年ぐらい。ちなみに上勝町は、環境よりも経済が圧倒的に優先されていた2003年に、日本で初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」をしています。
伊藤:それはすごい!僕が富山県の高岡に移住して事業を始めたのは2017年なのですが、その頃ですら、たんすの再生をしたいなんて「伊藤は頭がおかしくなったんじゃないか」と言われていたくらい(笑)。それが2020年くらいから、ちょっとずつSDGsやアップサイクルが浸透して、「なんかいいことをやってるよね」という反応に変わり始めました。
田中:上勝には本当にクレイジーな人たちが集まっていて、こういう場所なら何かを変えるきっかけが掴めるんじゃないかと考えて、2015年にRISE & WIN Brewing Co.というブルワリーを設立したんです。
山本:私は、2021年にCurelaboを立ち上げる前は、広告会社で長く観光プロモーションの仕事をしてきました。沖縄って年間1000万人以上の観光客が訪れていて、観光産業に人とお金がどんどん流れている一方で、一次産業は圧迫されてしまっている。観光だけでは解決できないことがあると感じて、地域経済だけでなく、地域の産業も活性化できないかと考え始めたんです。
田中:地域をどのようにつくっていくのかというのは、我々もすごく大事にしているテーマです。そもそも、ゼロ・ウェイストばかりが注目されていますが、上勝町の一番の課題って、ゴミじゃなくて過疎なんですよね。とにかく人口減少を食い止めないと、どんなに素晴らしいことをしていても続けていけないので。
伊藤:僕が今いる事務所も、空き家を再生しているのですが、皆さんのようにまちづくりに取り組んでいるかといわれると、そんなことはなくて。ただ、古いものを集めるには地域のおじいちゃんやおばあちゃんが頼りなので、「捨てようとしているものに、実はこんな価値があるんだ」ということは、普段から伝えるように意識しています。
山本:ちなみに、田中さんはなぜクラフトビールをつくろうと思ったんですか?
田中:どうしたらこの町を好きになって、この町に人が来てくれるのかを考えると、若い人たちが直感的に共感できるカジュアルなライフスタイルが必要。…
