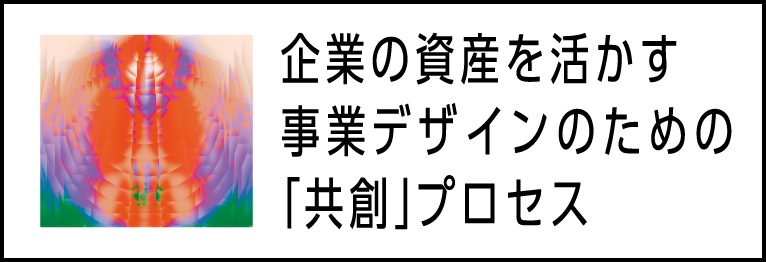プラスチックメーカーの甲子化学工業(大阪市)は、北海道・猿払村のホタテの貝殻を再利用した環境配慮型ヘルメット「ホタメット」を2022年12月から先行予約販売している。TBWA\HAKUHODOが両者の課題をブランドストーリーとして編み、生まれたプロジェクトだ。ビジネススキーム開発にも携わり、事業として動き出している。

甲子化学工業が北海道・猿払村の協力を得て開発した、ホタテの殻から生まれたヘルメット「ホタメット」。
始まりは1件のツイートから
プロジェクトは、2021年9月にTBWA\HAKUHODOのシニアアートディレクター 伊藤裕平さんが、とあるツイートを見つけたところから始まった。それは甲子化学工業(大阪市)の南原徹也さんの「年間約20万トン捨てられる卵の殻でプラスチック成形が出来るようになった」という発信。伊藤さんはクリエイティブディレクター 宇佐美雅俊さんに早速内容を共有。普段は広告制作を主に手がける2人だが、「素晴らしい技術なので、ぜひ世の中に広めたいという衝動にかられました」と話す。
早速、甲子化学工業に卵の殻でエコプラスチックをつくる技術を軸にした自主提案をすることになった。
「まずはその技術を『カラスチック』とブランド化する提案をしました。これ自体も気に入っていただけましたが、話を聞く中で、南原さんは単に自社の技術の顧客を増やしたいというだけではなく、世の中で“悪者”にされがちなプラスチック自体の認識を変えたいと熱い思いをお持ちだと知って。僕ら広告会社は広告づくりが主な仕事だと思われがちですが、本来のドメインは価値あるものを世の中に広げることにあります。その原点に立ち返り、南原さんの思いやこの技術を広げるために何ができるか、一緒に考えていきたいと思いました」(宇佐美さん)。
しかし改めて調べていくと、卵の殻をプラスチックに再利用する技術は他社の先行事例が存在していた。そこで白羽の矢を立てたのが、同じく炭酸カルシウムが主成分であるホタテの貝殻だ。PRプランナーの加藤卓さんは経緯をこう話す。
「実は以前から北海道・猿払村との繋がりがあり、ホタテの貝殻の廃棄問題を注視していたんです。猿払村は日本有数のホタテ水揚げ量を誇る村ですが、一方でその貝殻が水産系廃棄物として年間約4万トン(猿払村を含む北海道宗谷地区)も発生していて、環境への影響や堆積場所の確保が地域の社会課題になっています。貝殻を再利用したエコプラスチック製品を、世の中に求められる形で打ち出せれば、甲子化学工業と猿払村双方の課題解決に繋がると考えました」。
TBWA\HAKUHODOは社会課題の解決に向けた先行事例として取り組む形に。「甲子化学工業とも、利益を得るためだけの仕組みではなくプラスチック業界の持続可能なビジネスを探ろうと意見が合致していたので、プラスチックの新しい可能性を証明できるか、社会課題の解決に繋がるのか、という本質的な問いを軸に検討が進みました」(PRプランナー 橋本恭輔さん)。