今号では、36人のコピーライター、プランナーの皆さんに自身の「コピーの作法」をご執筆いただきました。36人のコピーライター、プランナーの頭の中にある「コピーの作法」をどうぞ覗いてみてください。
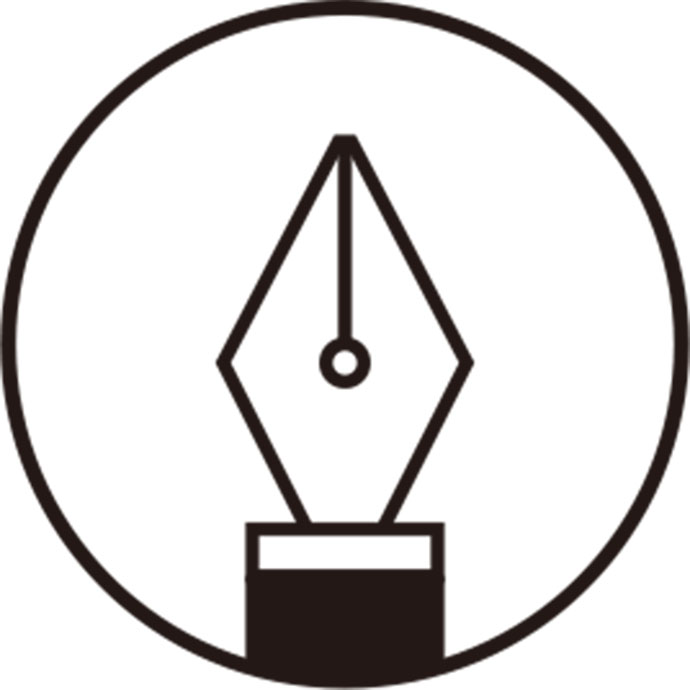
作法というより流儀
中村 禎
あらためて「あなたのコピーの作法とは」と聞かれると、
はて?そんなのあったかいな?と思う。
作法かどうかわからないが、いつも気を付けていることはある。
まず●「広告なんて誰も見たいと思っていない」ことを忘れない。
その商品に没頭し過ぎてしまうと一生懸命になり過ぎて、
こんなに一生懸命書いているんだから読んでくれるはずだ、という錯覚に陥る。
「そもそも、そんな話聞きたいか?」を常に忘れないようにしている。と同時に
「こんな広告、必要か?」とも疑ってみる。「フン、大きなお世話じゃ」と
「あ、一理あるかも」の狭い隙間に入り込む鋭い刃先がないとダメだと思っている。
そして●「ひとりのために書く」ようにしている。
よく、ターゲットは○○層だとかいうが、
ボクはそんな顔の見えない人に向けてコピーは書けない。
家族だったり友人の誰かだったり、先輩だったり、
その人の顔を思い浮かべてその人に向けてコピーを書く。
知っている人だから絶対ウソはつかない。騙したりなんてしない。
ほんとうにいいものじゃないと薦めない。
その人の喜ぶ顔、驚く顔を想像しながら書くようにしている。
そして最後に●「自分のコピーに意地悪なツッコミを入れる」
自分の字で、自分が書いた言葉はみんな正しいように見える。
しかし、それを意地悪な他人の目で見直す。揚げ足を取る。
イチャモンをつけてみる。ほんとにそうか?と疑ってみる。
「そ~んなヤツ、お~れへんやろ~。チッチキチ~」とツッコミを入れる。
そうやってみて、ま、このへんにしといたるわ、となったら清書する。
・・・改めてこうして「自分のコピー作法」を思い返してみると、
案外たくさんあることに気づく。
しかし、この方法を守れば必ずいいコピーが書けるという保証はなく、
ひとつの方法に縛られずあらゆる手を使って
「いいコピー」を目指すしかない。
その「作法」が自分の「流儀」となる頃
「いいコピー」が書けるようになるのだと思う。

1957年福岡県生まれ。大学生の頃から宣伝会議コピーライター養成講座へ通う。JWトンプソンへ営業として入社後、すぐに転職活動を開始。1981年サン・アド仲畑チームへ。コピーライターとしての基礎を学ぶ。1988年、より多くの試合経験を積むために電通へ移籍。現在に至る。
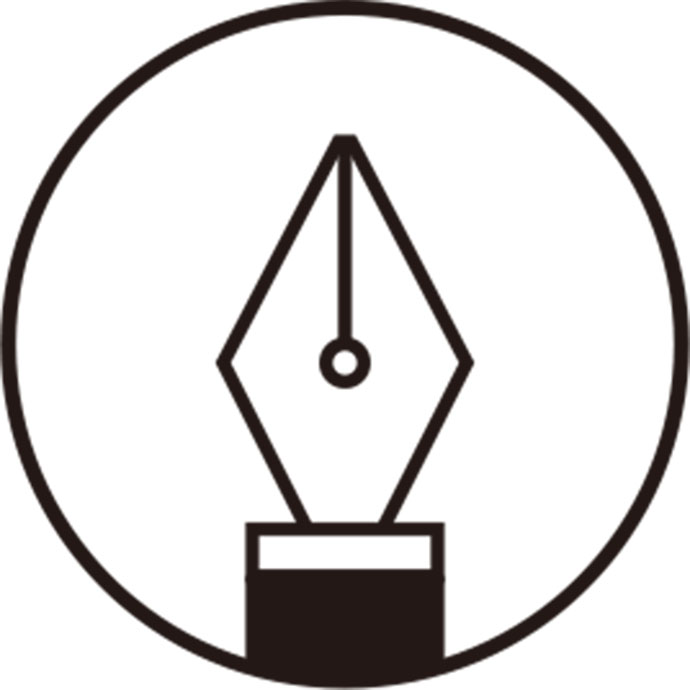
私のコピー作法
中山佐知子
作法という以前の問題であり、コピー以前の問題でもあるのですが、
かなり以前から日本語があやしくないですか。
10年以上も昔のTV番組を動画サイトで見ていたら ...
