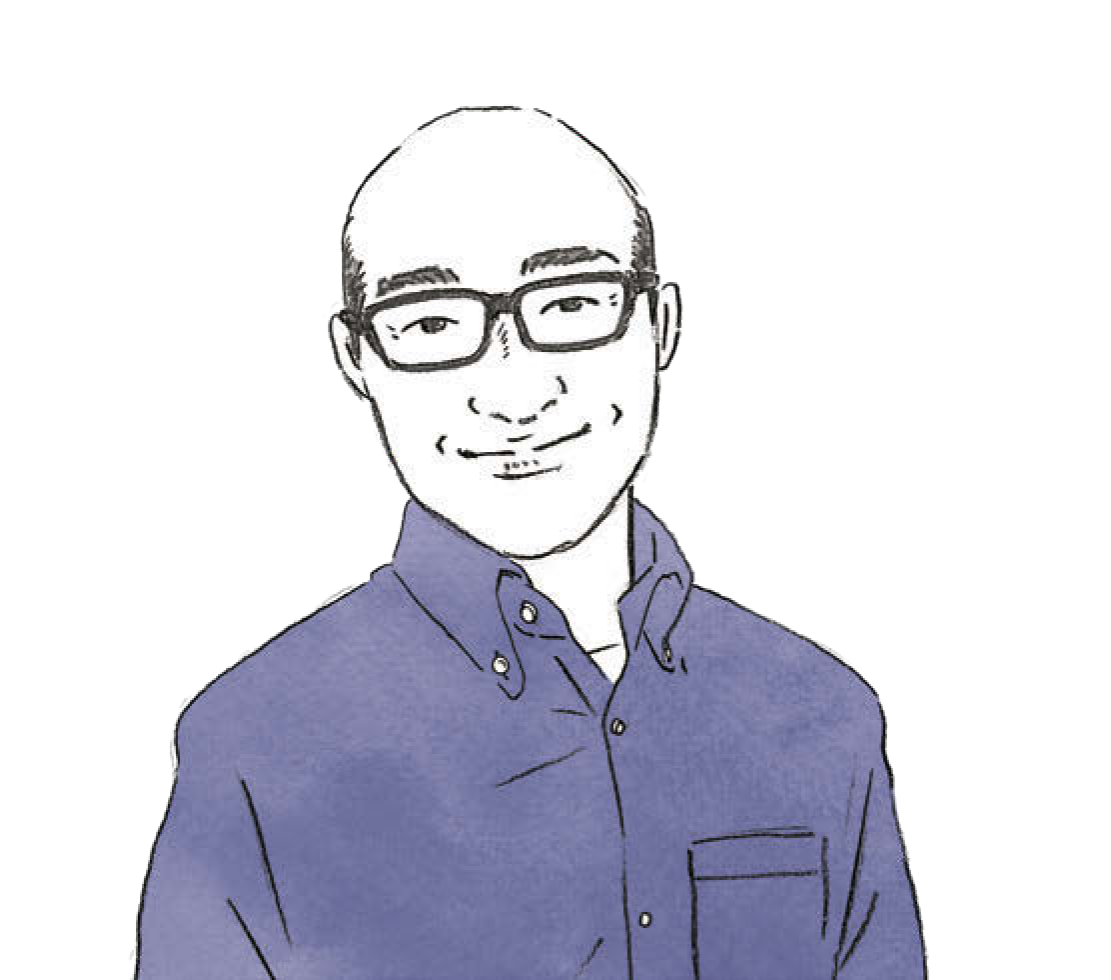帰属意識の強さが寄付への動機を高めた
前回、西南戦争の余波で慶應にも廃塾の危機があったこと、そして廃塾を回避できたのは、「共同行為」により資金調達に成功したからという話に触れた。その後も慶應は必要に応じて資金調達を実施。その背景には、「タダ乗り」※を防ぐために、仲間意識や帰属意識をつくる仕組みがあったと考えられる。また多額の募金をすると、慶應を卒業していなくても事後的に「特選塾員」と認定され、共同体メンバーになることができた。ビジネスをする際に期待される便益は大きく、長期的便益を得るために募金をする誘因が生まれる。
※「タダ乗り」とは、慶應出身者が慶應が存続するコスト(募金)を負担せず、「塾員」であるという利益だけを享受している状態のこと。
当時、慶應には幼稚舎の上に、正科と別科があった。それぞれ習熟段階別にクラスがあり、一定の成績に達すると、上位クラスに進級する。際立った特徴は、幼稚舎から最上級クラスに至るまで、全員の成績が「勤惰表」という冊子にまとめられ、塾生全員に配布されていたこと。
当時は最上級クラスから卒業する塾生は1年に平均して20名程度の時代。規模が小さいので...