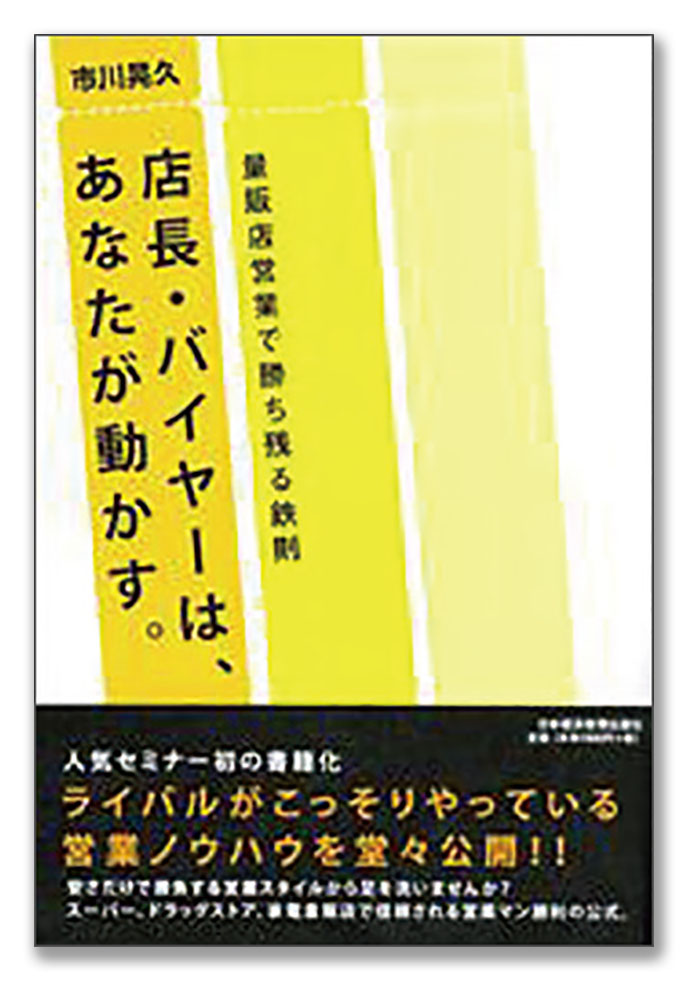
「店長・バイヤーは、あなたが動かす。―量販店営業で勝ち残る鉄則」
市川晃久著 日本経済新聞出版社刊
著者はバイヤー経験のある企業コンサルの代表取締役。私が説明する広域営業を"量販店営業"という表現で非常に優しく書いているので読みやすい。
支店や営業所を全廃?!求められる新しい視点
チェーン・ストア化によって大規模化した流通企業は、巨大な販売力を背景に強力なバイイング・パワーを持つようになっていく。こうした流通企業に対して、消費財メーカーはいかに向き合い、自社商品を売り込むべきか。一貫してメーカーの立場から、マーケティング・チャネル戦略を研究してきた東洋大学の住谷宏教授が近年、最も注力する研究テーマが「バイイング・パワーと消費財メーカーの対応戦略」だ。
住谷氏が戦略のひとつとして提案しているのが「支店・営業所体制の撤廃」だ。大手メーカーは各地に支店や営業所を配置して、ノルマや売上げは支店や営業所単位で設定する。「しかし、支店単位で管理をすると、商圏内にあるローカルチェーンの存在が大きくなってしまう。商圏における、売上比率が10%を超えると相手側の力が強くなり、無茶な要求をされても、目先の業績を考えて対応せざるをえなくなる。支店単位で考えると、こうした事態に陥りかねない。支店制度を廃止して、例えば、営業本部を東日本と西日本に設置すれば、商圏が大きくなりローカルチェーンの比率はぐっと下がる。分母はできるだけ大きくすべき」。
実際に支店制度を廃止したメーカーも出始めているという。だが「日本では難しい面もある」と住谷氏。CSRで地域活性化の委員を務めるような場合に"支店長"の肩書を求められることが少なくないからだ。「メーカーは考え方を変え、組織を改革することが求められている。組織改編を率先して行っている企業には ...
