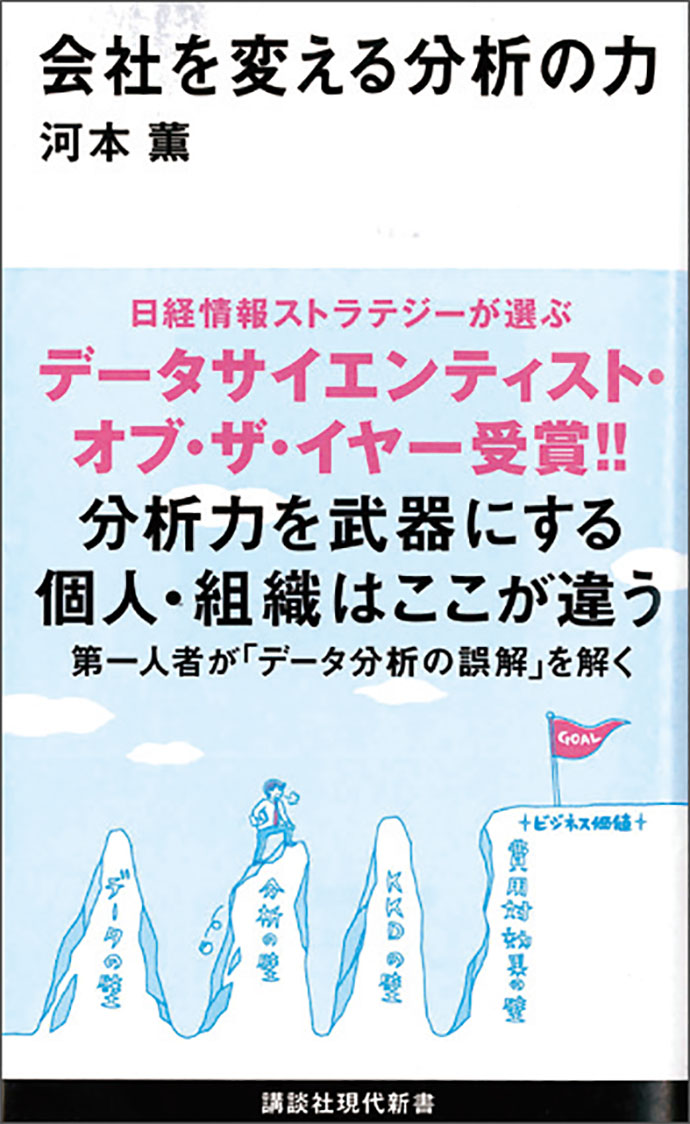
会社を変える分析の力河本 薫/著
木村教授のお薦め本は、河本薫著『会社を変える分析の力』(講談社現代新書)。「企業の人たちが知っておくべきデータとの向き合い方が分かりやすく解説されている」(木村教授)。
プラントエンジニアからマーケティング研究者に転身
一般消費者も自らが情報を発信し、その情報が購買行動に大きな影響を与え合う時代。消費者同士が複雑にネットワーク化された現在の環境下において、どのように新製品が普及していくのか、そのモデルを予測するのはこれまで以上に難しいテーマと言える。
そんなテーマを選び、研究活動を行うのが立正大学・経営学部の木村浩教授だ。プラント設計に携わるエンジニアとして、石油の元売り事業者に入社するも、入社後に通っていた慶應大学ビジネススクールにて、池尾恭一教授と出会い、マーケティングに開眼。実業界から転身し、マーケティング研究者としての道を歩んできた。
「当時、働いていた石油産業では、化石燃料だけに頼るビジネスモデルからの転換が求められており、新事業・新製品開発が大きなテーマだった。そこで新製品の普及モデルに関心を持つようになった」。
それまで、文系の学術テーマには触れてこなかった木村教授。指導教員の池尾教授より、「ロジャーズの普及モデル」の話などを聞き、新製品普及の数理モデル構築に関心を持ち、ビジネススクール修了後も、このテーマに取り組んできた。「それまでの社会学領域の普及モデルは、伝染病の普及予測のモデルがベース。人と人とが接触すると、〇%の確率で製品が普及・伝播するという単純化されたもので、各消費者の『態度』までは変数に取り入れられていなかった」と話す。
企業の実務に活かせるようにするには、価格や広告など ...

