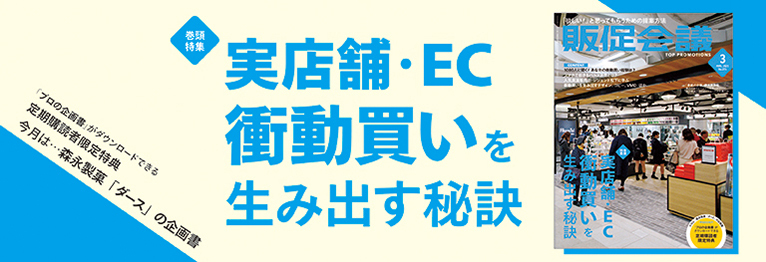衝動買いというと店頭、オフラインをイメージする場合が多い。しかし、いまやスマートフォンによって、商品を知る、購入する接点が常にそばにある。そういった環境下で起こる新しい消費行動「パルス消費」についてレポートする。
生活者を取り巻くメディア環境は大きく変化し続けている。中でも顕著なのは膨大に増える情報量だ。
そのような中での新しい消費行動として、Googleは「パルス消費」を提唱している。パルス消費とは、人々が商品やサービスにかかわる様々な情報を常に探索している途上で、とある商品・サービスに対し潜在的に期待しているメッセージに「出会った」と感じた時に、直感センサーが発動し購入を決定する、という行動のことである。
認知と行動がほぼ同時
このような変化の裏にはスマートフォンの存在がある。商品・サービスの情報を得られる場所と、商品・サービスそれ自体を購入できる場所の両方が同じデバイス上にあることで、消費者はこれまでよりも圧倒的に自由に探索することができるようになっている。
そうなると、当然人々の商品・サービスの選び方は変化してくる。Googleが過去実施したいくつかの調査によると、今は、ユーザーの購買決定プロセス「AIDMA(認知・関心・欲求・記憶・行動)」の最初のA(認知)と最後のA(行動)がほぼ同時に発生していることが多くなっているという。例えば、何を買うかを決めずにお店(オンライン・オフライン問わず)へ行くという人や、それまで名前を聞いたことがない商品を買うことも躊躇しないという人が、2018年の調査時点ですら図1のような結果が出ている。
そこで、Googleはこのような一見無計画な買い物行動を「パルス消費」と名付けて、「衝動買い」の言い換えではなく、オンライン上の消費行動を理解するための汎用的なフレームワークであるとしている。
さらに、パルス消費は、アフォーダンス、つまり明示的にも暗示的にもその商品・サービス自体やそれにかかわる各周辺領域で発されるメッセージに対して消費者が心理的に反応して起こるものであるとしている。その心理的な反応を「直感センサー」として、6つに...