.png)
人材・サービス業
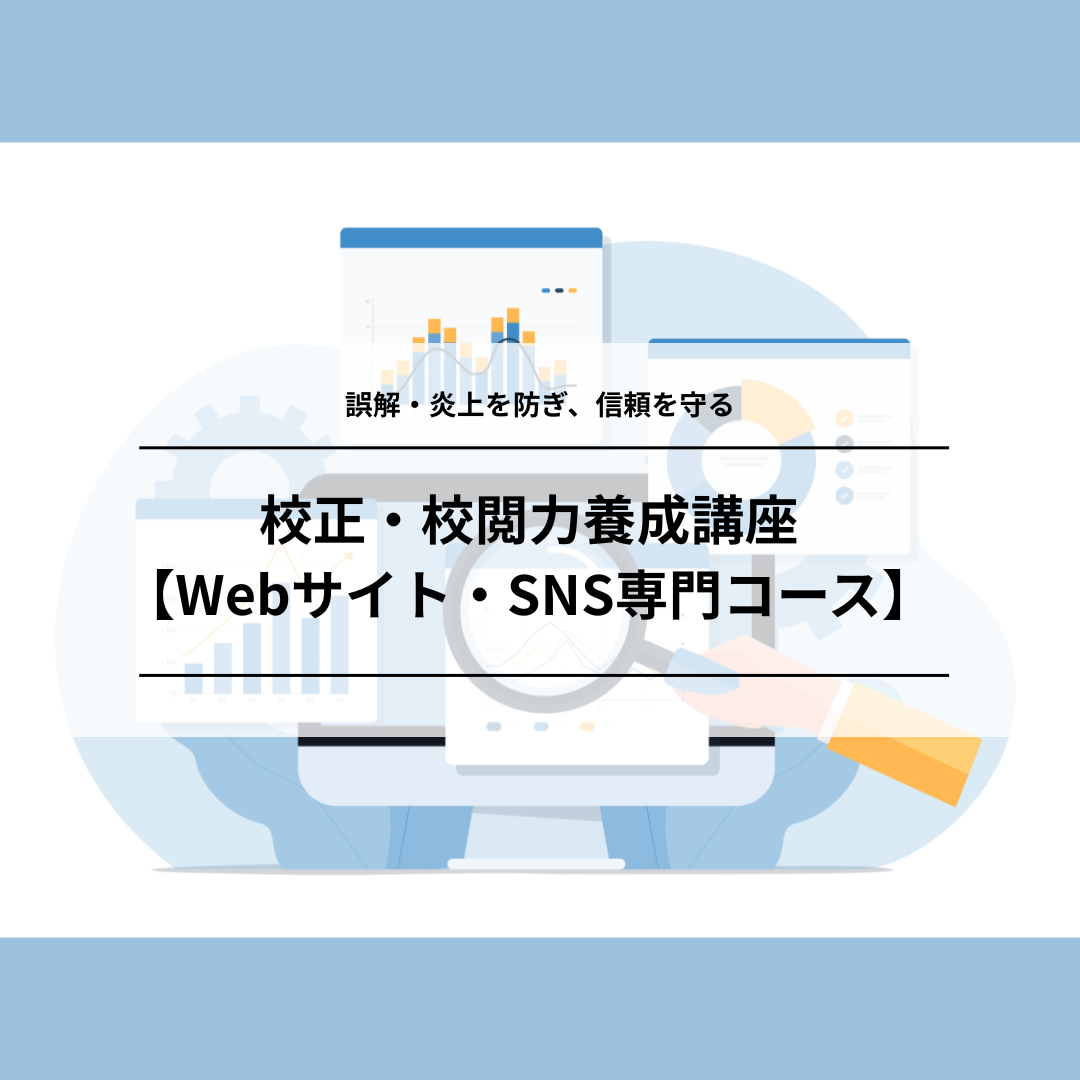
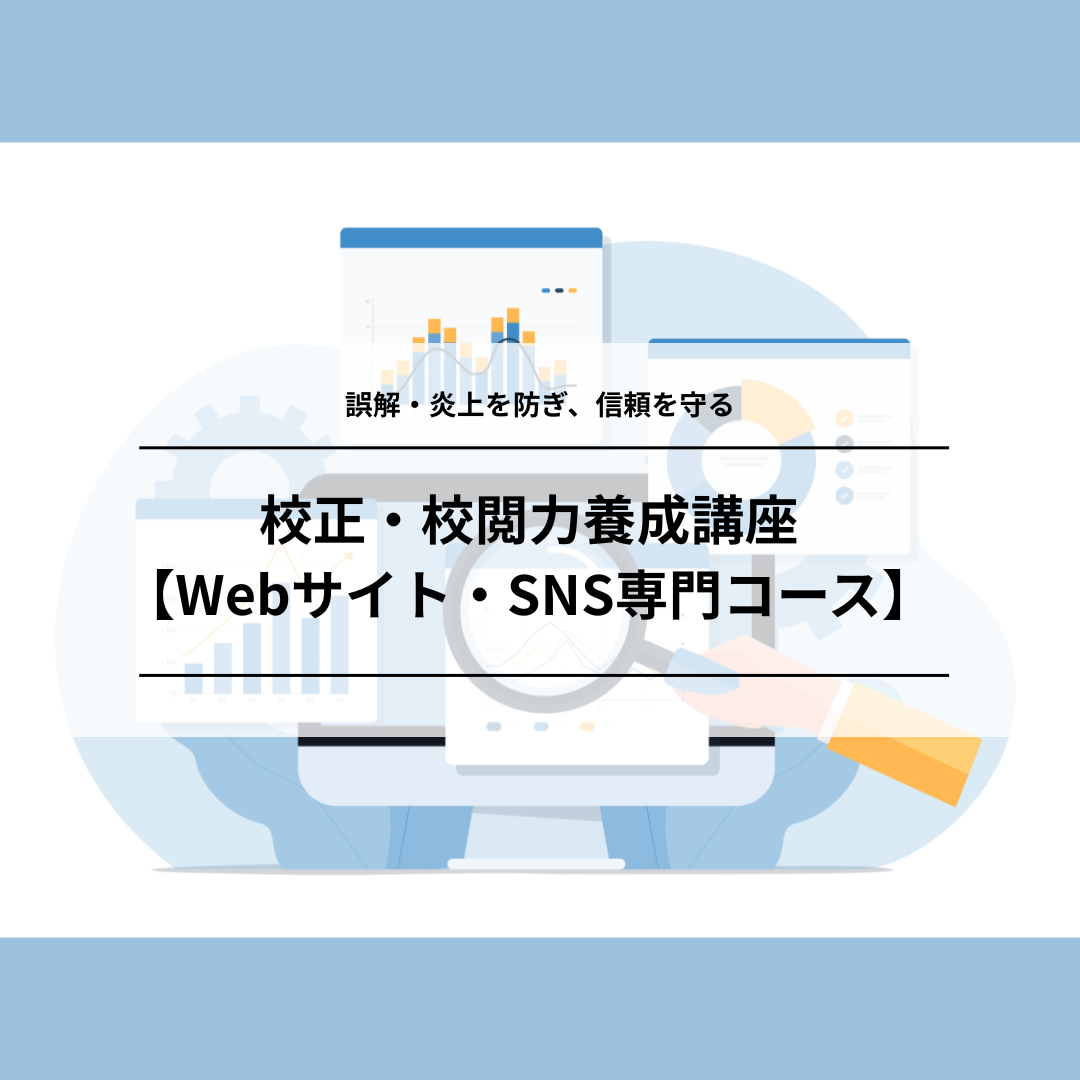
Webで情報発信をする、すべての担当者のための
SNSやWebサイトなど、誰でも簡単に発信できる時代。一方で、誤字脱字や事実誤認、思わぬ炎上につながる表現リスクも増えています。この講座では、紙媒体とは異なるWeb文書ならではの校正・校閲の視点を学び、組織として信頼される情報発信の土台をつくります。「ただのミス防止」ではなく、「伝える力を守る」ための、実践的な知識とスキルを身につけましょう。
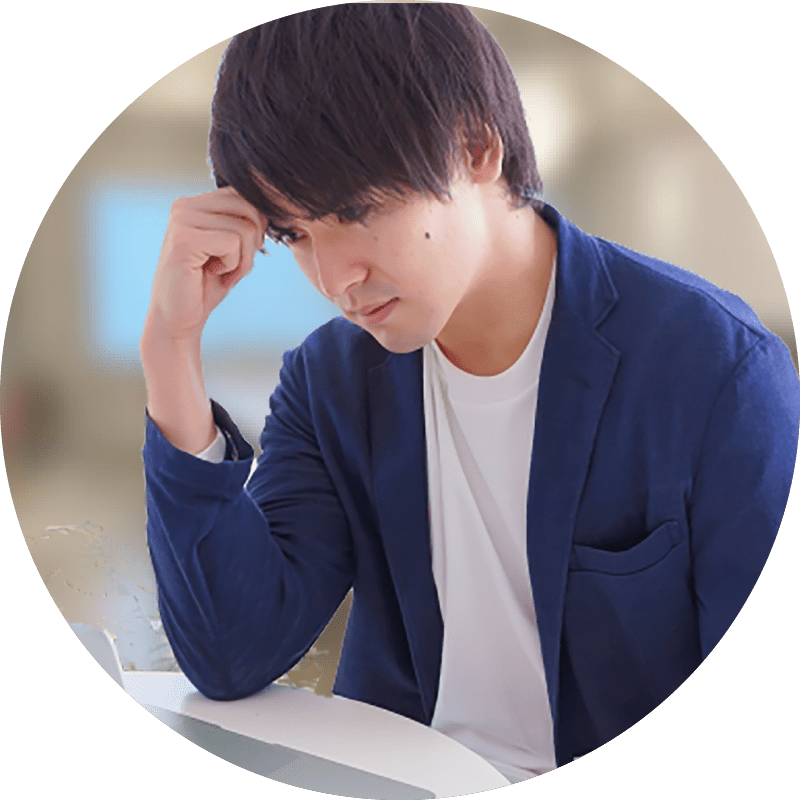 scene #1 | Webは常にスピードが求められるため軽い確認しかできていない |
 scene #2 | 媒体ごとの違いや記者の関心に合わせた対応ができていない |
 scene #3 | 社内にWeb特化の校正者がいないのでなんとなく行っている |
 scene #4 | SNSの炎上や誤情報の拡散が気になって同じような投稿ばかり |
 scene #5 | 文章は正しいのに、意図がズレて読者に誤解される |
 scene #6 | 校正業務を外注しているが運⽤ルールやリスクの管理体制などに不安がある |
そもそも「知らないもの」には対処のしようがない。
知るべきは、Web・SNS独自のリスク把握とその対処法。
発信ミスを防ぎ、信頼を築く。
Web・SNS時代の校正・校閲力を体系的に習得します。
「公開直後に誤字が見つかった」「SNS投稿が意図せず炎上してしまった」――WebやSNSを使った情報発信が日常的になる一方で、ちょっとした見落としが信頼の毀損や法的リスクに直結するケースが増えています。従来の紙媒体とは異なり、即時性・拡散性・媒体ごとの表示差といったデジタル特有の特性が、校正・校閲の難易度を高めているのが現状です。
本講座では、こうした背景をふまえ、WebコンテンツやSNS投稿における校正・校閲の基本から、実務で役立つチェック観点、さらにはミスを防ぐ仕組みづくりまでを体系的に学びます。まず、紙との違いや画面表示における注意点、チェックすべき技術的・法的ポイントを整理。次に、数値や固有名詞の整合性、表記ルールの統一、炎上リスクのある表現などを見極める視点を磨いていきます。また、近年利用が進むAIツールや自動チェック機能の特徴と活用法も紹介し、限られた時間でも効率的かつ高精度な確認作業を実現できる方法を習得します。
「なんとなく目を通す」ではなく、「目的に応じて必要なチェックを行う」姿勢とスキルを身につけ、発信力と信頼性の両立を目指しましょう。
WebサイトやSNSなど、デジタルメディアの特性に合わせた校正・校閲の方法を体系的に学びます。パソコンやスマートフォンなど表示媒体の違いによる見え方やレイアウトの変化を理解し、画面上での誤りや見落としを防ぐ実践的な技術を身につけることができます。
数値や固有名詞、用語の整合性チェックをはじめ、著作権、薬機法、差別表現などWeb・SNS特有の法的トラブルに関する基礎知識をしっかりと習得。これにより、情報の正確さと適切な表現を担保し、トラブルや炎上を未然に防ぐリスクマネジメント力を養います。
AIツールをはじめとした最新のデジタル技術を活用し、校正・校閲の効率化を図ります。ツールの特性や使いどころを理解することで、時間短縮と高品質なチェックの両立を目指せるスキルを身につけられます。
WebサイトやSNSに掲載する文章の校正・校閲は、信用の構築やコスト削減などにつながる大切な作業です。まずは企画から校了までのWeb校正校閲の流れを把握し、実際に原稿などをチェックする際の具体的な作業内容を学びます。また、Web校正・校閲で役立つ表記統一マニュアルや文章の執筆要綱の作成方法、パソコン上での校正・校閲方法も身につけます。さらに、ネット上だからこそ避けるべき差別用語・不快用語や気を付けたい話題についても紹介します。
WebサイトやSNSに掲載する文中には、新聞記事や書籍などからの情報の引用があったり、Webサイトのリンクの貼り付けやSNSとの連携があったりと、自社サイトで完結しないことがほとんどです。また、イベント写真やイメージ画像、動画などの著作物を使用することも多々あります。知らぬ間に法に抵触し、「修正」「お詫び掲載」だけにとどまらず、金銭問題や訴訟に発展するケースもあります。本講座では、著作権、肖像権など「権利に関する法律」と薬事法、消費者法など「掲載内容に関する法律」などのWebにまつわる法律を、Web担当者が知っておくべきポイントに絞ってわかりやすく解説。医療系メディアの実例なども交えながらリスクマネジメント方法を学びます。
デジタル環境では、膨大な情報量や更新頻度の速さが求められる中で、校正作業の効率化が不可欠です。本講座では、AI校正ツールやチェック支援ツールなど、実務で活用されている最新技術を取り上げ、その基本的な使い方から効果的な導入方法までを紹介します。ツールの精度や限界を理解しながら、人の目で補完すべきポイントを見極めるバランス感覚を養い、属人化せずに再現性のある作業フローを構築する視点を身につけます。従来の人力によるチェックだけに頼らず、ツールと連携することで、業務全体の生産性と品質を高める実践的な方法を学びます。
.png)
人材・サービス業
.png)
個人受講
.png)
Webディレクター
カリキュラム | |
|---|---|
時間 | 講義内容 |
約120分 | デジタル校正で注意する点とは? 【基礎知識編】 ・校正の基礎知識 ・Webコンテンツの校正ポイント ・Webコンテンツの校閲ポイント 【デジタル校正編】 ・表示媒体の違いを把握 ・表示媒体の違いを比較した実験 ・画面校正で注意すべきポイント ・表示媒体の違いのポイント ・見落としを防ぐポイント |
約60分 | Web文書の校正・校閲実践 ・Web文書校正の2つの目的 ・Web文書校正の実務における4つのポイント ・数値、固有名詞、用語、体裁の整合性チェックを実践しよう ・デジタル校正について ・AIツールの活用 |
約120分 | Web文書にまつわる法的トラブル ・ Webで注意すべき「著作権」 ・その他の注意すべき法的 問題 ・差別的なメッセージ ・SNSでのバイトテロ ・Web上のトラブルへの法的対応 |
概要 | ||
|---|---|---|
受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 | |
受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |
受講料金 | 1名受講 | 59,000円(税込64,900円) |
100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |
オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 | |
割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 | |
受講対象 | ・WebサイトやSNSで情報発信を担当している広報・編集・ライター職の方 ・自治体や企業の広報担当者(住民向け、生活者向けに情報を発信する方) ・Webコンテンツ制作に関わるディレクター・制作進行管理者 ・社内外に発信する文章のチェック・校閲を担う立場の方 ・誤解や炎上リスクを抑え、正確で読みやすい文章を書きたいと考えている方 | |
注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |
・1名単位でのご受講は「1名受講」
・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」
・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。