.png)
メーカー 広報
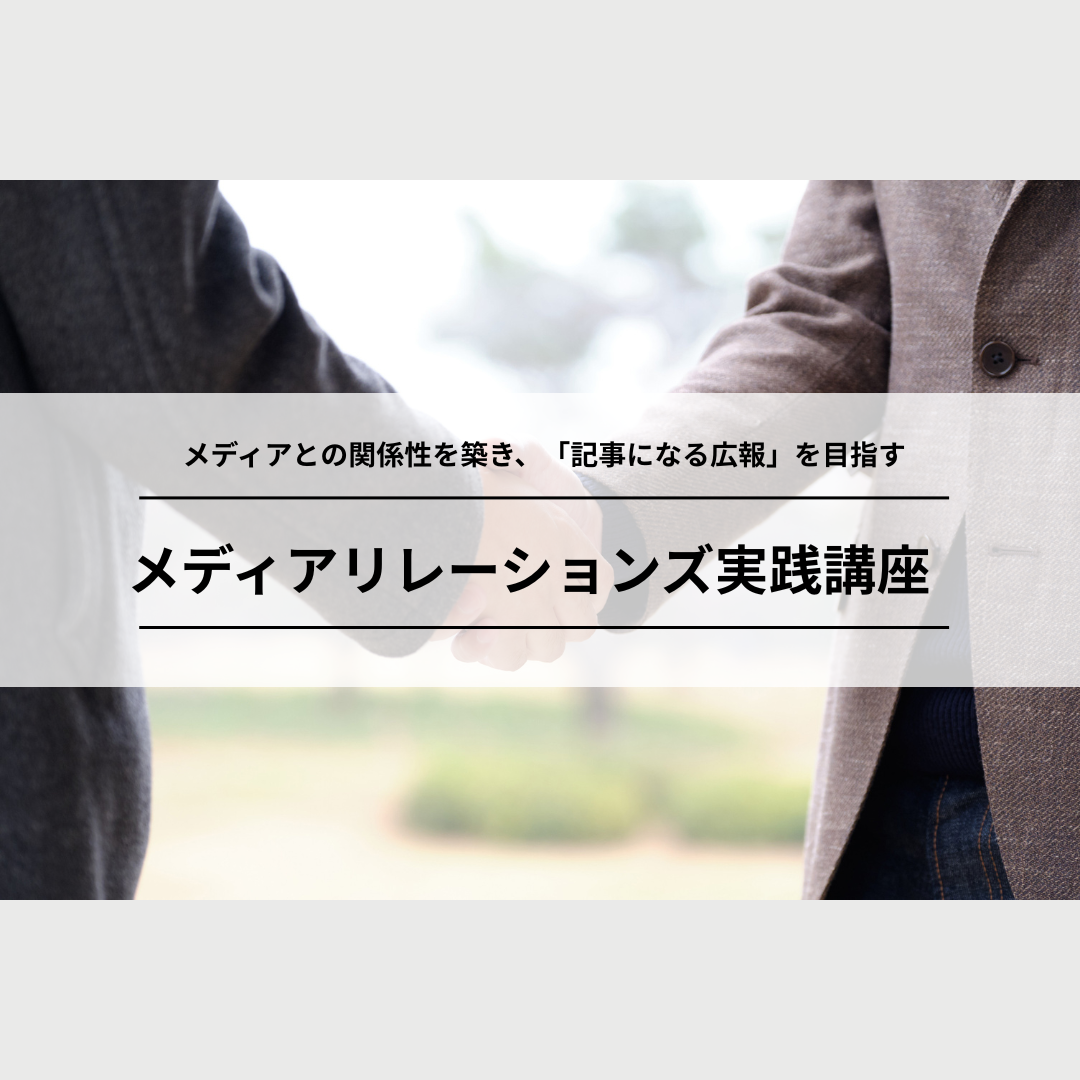
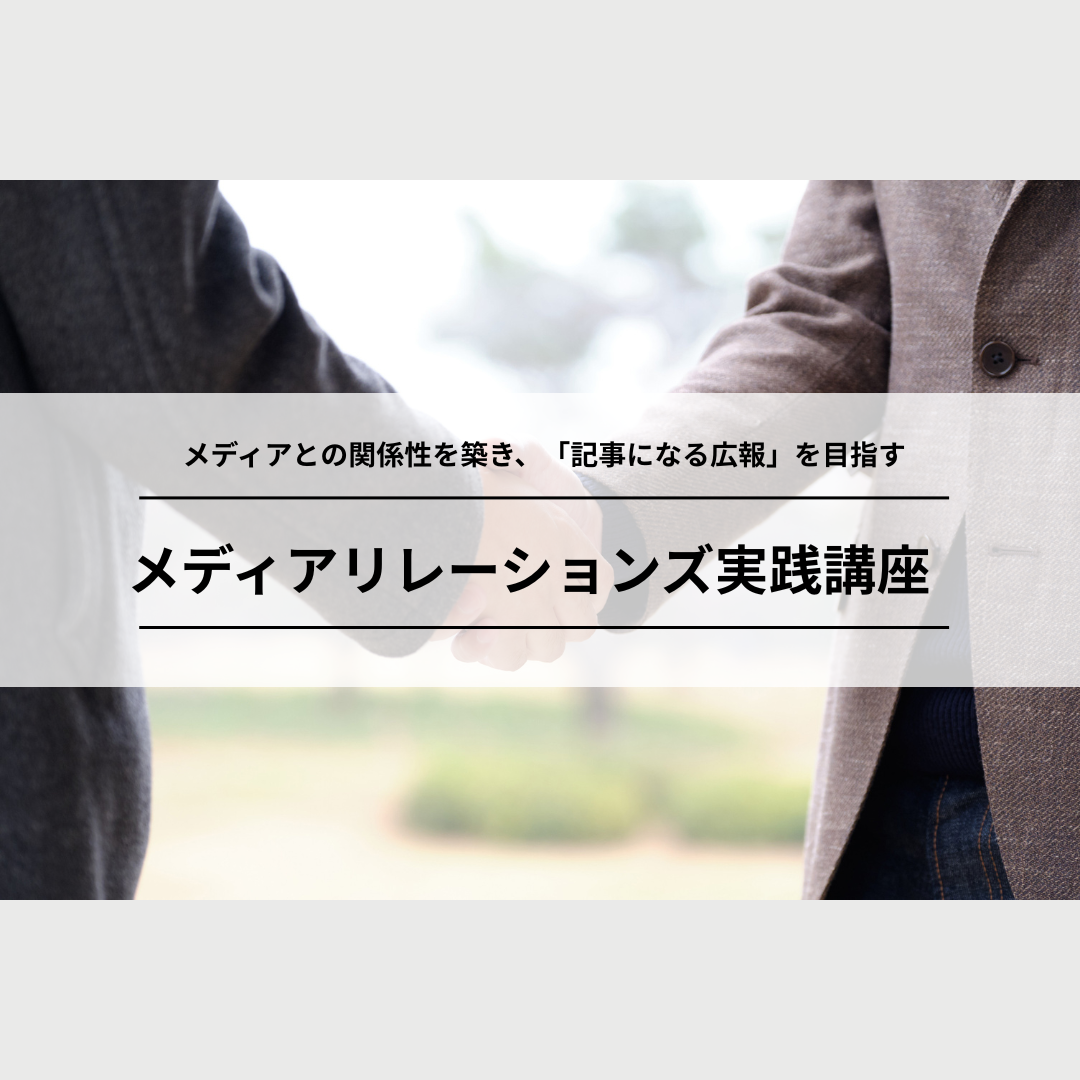
いつでも視聴できる「オンデマンド配信」
一見アプローチしづらい記者は、日々何を考え、何に喜ぶのか。
トライする前に、主要メディアのキーマンにその答えを学ぶ
情報があふれ、誰もが発信者になれる時代。メディアもまた、紙からWEBへ、速報性から深掘りへと変化を続けています。
そんな中で、広報担当者に求められるのは、単にプレスリリースを送ることではありません。メディアの特性と記者の視点を深く理解し、「取り上げたくなる情報」として設計し届ける力です。
本講座では、新聞・雑誌・WEB、それぞれの現場を知るメディア経験者から、今の時代に通用するメディアリレーションズの実践知を学びます。媒体の構造や記者の思考回路、情報の扱われ方、関係性の築き方などを、具体例とともに解説。
広報実務の基礎から一歩進んで、「届ける」だけでなく「響かせる」「関係を育てる」広報へ。今あらためて求められる“本質的なメディア対応力”を磨く講座です。
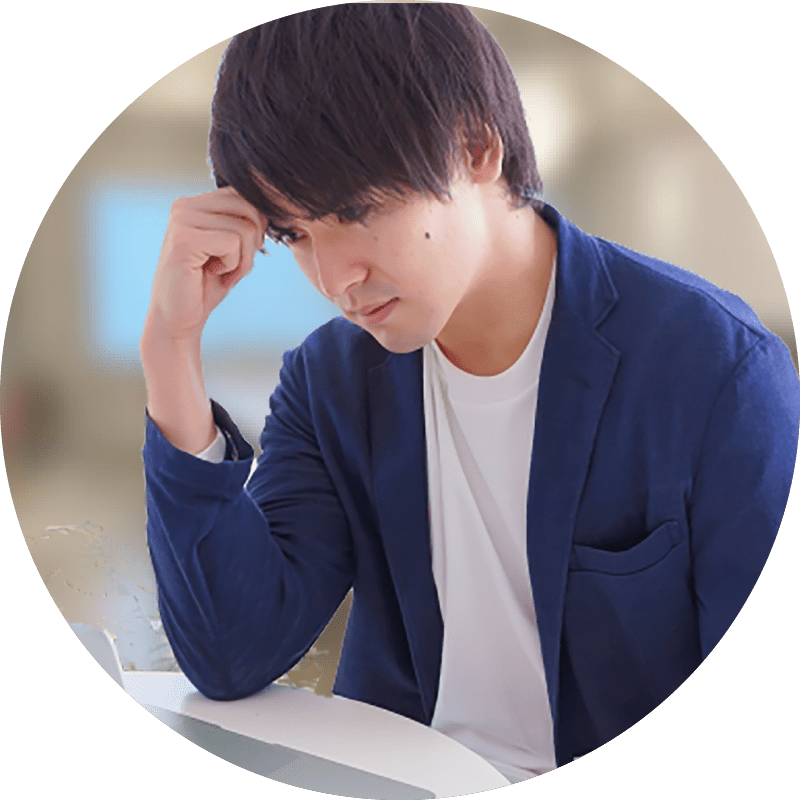 scene #1 | リリースを出しても、なかなか取り上げてもらえない |
 scene #2 | 媒体ごとの違いや記者の関心に合わせた対応ができていない |
 scene #3 | 情報発信が一方通行でメディアとの関係構築に課題を感じている |
 scene #4 | メディアへのアプローチに関してPR会社に全て任せきりになっている |
 scene #5 | 新聞・雑誌・WEBなどメディア特性を踏まえた広報戦略を立てたい |
 scene #6 | 製品に関する情報は、開発部門が作ったリリースのまま記者に伝えている |
メディアとの関係作りのコツを学びメディアへの露出を最大限に上げる!
変化するメディア環境で成果を上げる、実践的メディアリレーションズを理解する
情報発信の形が多様化し、メディアとの関係性の築き方も変わり続ける今、広報担当者には単なる情報伝達を超えたスキルが求められています。本講座では、メディアリレーションズの本質を理解し、実務に活かせる具体的な知識と技術を段階的に習得することを目的としています。
まず、メディアリレーションズの基本や記者クラブの仕組み、新聞・雑誌・WEBなど各メディアの特性と構造を丁寧に押さえ、広報対応の基盤を築きます。次に、記者や編集者の思考法や取材のプロセスを具体的に学び、メディアごとに求められるアプローチ方法や効果的なプレスリリースの設計ポイントを理解します。さらに、情報の伝え方やタイミング、記者との間合いの取り方など、実践的なテクニックを身につけることで、一過性では終わらない継続的な関係構築の手法を学びます。
これらを通じて、メディアの視点に立った広報戦略を描き、記者に届く・取り上げられる情報発信を実現。広報活動の成果を確実に高めるための実践力を、理論と現場の両面から体系的に身につける講座です。
メディアとの関係の中で、最もお互いのコミュニケーションを妨げているのは、一般企業同士の取引とメディアとの慣習の違いです。そこで、メディアとの接触以前に押さえておくべき「しきたり」ともいえる原則を学びます。
メディアに情報を届ける際、ただ知らせるだけでは十分ではありません。大切なのは、メディアが「伝えたい」と感じる構造で情報を設計することです。社会との接点がどこにあるのか、どんな人や場面が登場するのか、その情報がなぜ今必要なのか——そうした要素を丁寧に描き出すことで、メディアの取材意欲を自然と引き出すことができます。広報が目指すべきは、プッシュ型の情報提供ではなく、メディアが自ら取り上げたくなる“伝えたくなる仕立て”をつくることです。
新聞、雑誌、WEBなどの各メディアのキーパーソンが、講師として直接講義します。メディアとしての立場から、自社の形態、新規アポイントに対する応対事情など、外からでは知ることができない業界内の「暗黙のルール」を学べる講義を展開します。
近年、企業の広報における取り組みの中に、メディアの実際の購読層である消費者の関心を持てるように社内の情報を統合する動きがあります。いわばメディアと協力した報道を生み出すことが着目されているのです。本講座では、実際に企業広報の働きかけによって特集やブームを生み、さらにメディア上でのPRに成功した事例を学びます。
メディアとの関係構築は、一般企業同士のビジネス的な関係とは異なるルールや慣習が存在します。本講座では、メディア特有の“しきたり”や価値観を理解し、誤解や行き違いを防ぐための基本的な考え方を学びます。その上で、自社の規模や体制に応じた最適な対応方法を整理し、単なるマニュアル対応を超えた信頼構築の土台を築きます。
一方的に情報を届けるのではなく、メディアが取り上げたくなるネタをどう作り、どう仕立てるかが、広報の力量を左右します。本講座では、新規性・社会性・時事性などの要素を踏まえて、取材につながるコンテンツの条件を理解。記者が思わず手を伸ばしたくなる「情報設計」と「取材設計」の視点を学び、自社ならではの“伝えたくなるストーリー”のつくり方を習得します。
単発の露出だけで終わらせないためには、記者や編集者との関係性を育てていく視点が欠かせません。本講座では、新聞・雑誌・WEBなど各メディアの特性や現場の事情を理解し、そのうえでどう関係性を深め、継続的に情報発信につなげていくかを学びます。アプローチの温度感やタイミング、記者の本音などを知ることで、より信頼される広報担当者を目指します。

総合PR会社プラップジャパンを経て、2015年、関連PR会社のブレインズ・カンパニー社長に就任。 自治体・企業・団体などの広報PRに幅広く従事し、業種や領域を問わずメディアリレーションを駆使した実効性の高い広報PRを実践。不祥事後の信用回復を目指すリカバリー広報でも実績を持つ。 広報PR歴39年。国土交通省、ネスレキットカット、コカ・コーラ、マクドナルド、P&G、メルセデスベンツなどを担当。近年、顧客に寄り添う「伴走型広報」を推進。各方面からの依頼で広報講座講師、外部委員も務める。

1991年、読売新聞社入社。経済部などで税財政、通信業界、エネルギー業界を中心に取材。経済部デスク、論説委員、編集局次長を経て、2023年6月から現職。

1981年生まれ。2004年慶應義塾大学文学部卒業、日本放送協会(NHK)入社。記者として甲府放送局に勤務。06年プレジデント社へ。プレジデントオンライン副編集長、編集長を経て、24年7月から現職。

1983年3月8日生まれ。慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、2005年に毎日新聞社に入社。 東日本大震災の被災地となった福島では、避難者の心と身体の健康の課題などを担当した。 退職後、シンガポールに転居。日系出版社でビジネス誌編集者として勤めたのち、東南アジア各国からの女性移民労働者を支援するNGOで広報職員として勤務。 2016年に帰国し、ハフポスト日本版に入社。ジャーナリズムの知識とグローバル感覚の両方を生かしながら、ジェンダー平等の問題や働きかた、男性育休などのテーマで、キャンペーン報道をリードしてきた。2018年から副編集長、2021年から現職。2児の母。
.png)
メーカー 広報
.png)
機械 経営企画
.png)
公益法人 広報
カリキュラム | |
|---|---|
時間 | 講義内容 |
第1部 | メディアリレーションズの基本 ・メディアリレーションズにおける心構え ・メディアアプローチ方法 ・記者クラブの特徴 ・媒体ごとの特性 ・メディア視点を身につける ・社会インサイトとの接点を持つ ・メディアリレーションズと広報対応 |
第2部 | メディアの考え方を知る ・新聞の現在 ・ネット・ネイティブの時代 ・紙の新聞の特性 ・新聞記者とは ・さまざまな担当分野 ・記者の思考法 ・記者との付き合い方 ・良いプレスリリース ・記者との間合い ・経済の現状と見通し |
第3部 | メディアの考え方を知る ・雑誌市場の状況 ・パブリックリレーションズと広報 ・プレスリリースの役割と重要性 ・雑誌編集の実務・企画術 ・雑誌とWEBメディアの違い ・なぜタイトルが重要なのか |
第4部 | メディアの考え方を知る ・WEBメディアから選ばれる情報とは ・読まれるネタの切り口 ・リリースの発信方法、タイミング ・一度の取材で終わらない関係性のつくり方 |
概要 | ||
|---|---|---|
受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から14日間視聴可能。 | |
受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |
受講料金 | 1名受講 | 59,000円(税込64,900円) |
100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |
オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。 ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。 ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。 | |
割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 | |
受講対象 | 企業および団体の広報担当者 | |
注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |
・1名単位でのご受講は「1名受講」
・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」
・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。