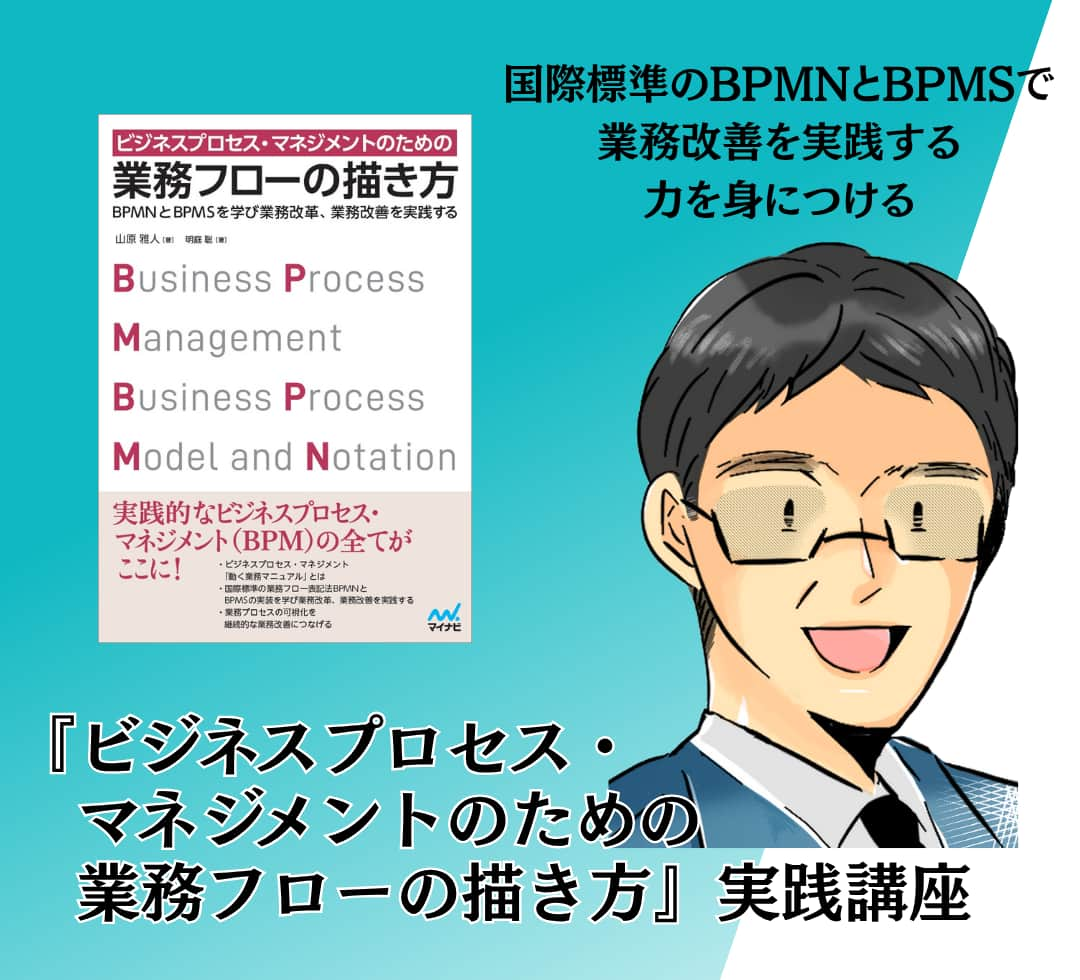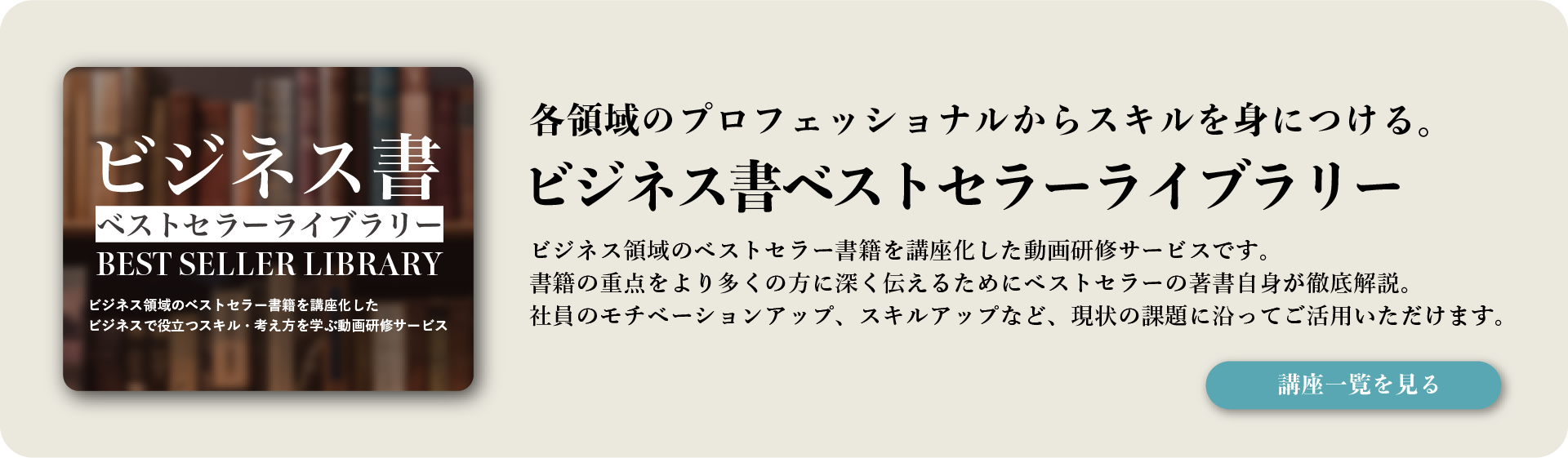書籍『ビジネスプロセス・マネジメントのための業務フローの描き方』
(山原 雅人,明庭 聡/株式会社マイナビ出版 刊)
“描くだけ”では実現しないPDCAサイクルが回る業務改善を実践する力を習得する
BPMは国際標準の業務フロー記述法であるBPMNとBPMSというITツールを使った業務改革・改善のマネジメント手法です。
BPMNがBPMSに実装されて業務フロー通りに動く“動く業務マニュアル“の実例を紹介することで、本講座では業務フローを描く先にあるゴールを理解することができます。
BPMNが実務者の道具となり改善人材を育成し変化に強い組織作りたい方に最適な講座です。
この講座で得られるもの
業務改善が進まない本当の理由と解決法―継続的改善へ導く視点
誰もが理解できる業務フロー設計スキル―経営層・現場・ITが共通言語で理解できるフローを描く力
改善が回り続ける仕組み―PDCAが回り続けるBPMの改善サイクルの理解
システム開発会社に依存しない改革アプローチ―変化に合わせて進化する柔軟な改善手法
BPMNの記述による現場主体での業務改革・改善の実施により後戻りが発生しないシステムによる自動化
このような方に最適な講座です。
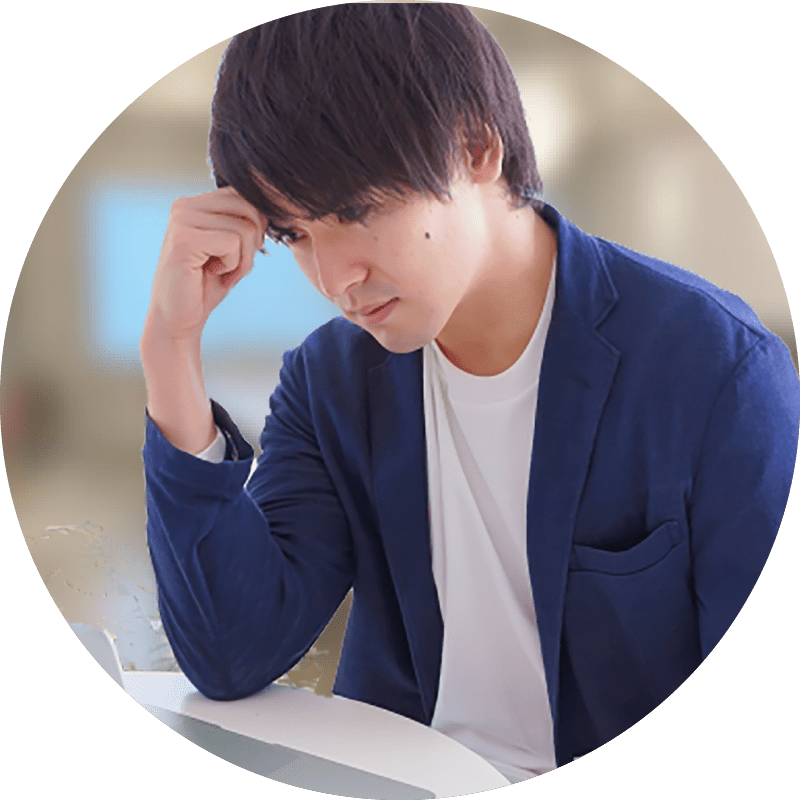 scene #1 | 業務フローを作成してみたものの、実際の改善に結びつかず「形だけの見える化」で終わってしまっている |
 scene #2 | DX推進を任されたが、自社の業務が部門ごとにバラバラで、標準化できず、改善や効率化が部分最適に留まっている |
 scene #3 | 部署や立場ごとに使う言葉が異なり、部門間の合意形成が噛み合わず、合意形成が進まないことに課題感を感じている |
 scene #4 | 新しいシステムを導入しても、現場の業務が変わらず、改善が長続きしないことに限界を感じている |
 scene #5 | 環境変化に即応できる“変化に強い組織”をつくりたいが、そのための仕組みや実践手法が分からない |
受講対象
- 業務改善やDX推進を担う部門の責任者・担当者
- 経営企画や経営層直下の改革プロジェクトメンバー
- システム導入や業務標準化を任されている情報システム部門の担当者
- 部署横断で業務プロセスを整理・合意形成しなければならない管理職
- クライアント企業に業務改善やDX支援を行うコンサルタント・シンクタンク関係者
- 将来的に“業務改善×DX”を武器にキャリアを築きたい若手リーダー層
講座のポイント
01 業務改善を“描くだけ”で終わらせない
多くの企業で行われている「業務フロー作成」は、形だけの見える化で終わりがちです。本講座では、BPMが単なる業務フローの記述ではなく、改善を仕組みとして回す“動的なマネジメント手法”として理解できます。継続的に成果を出せる業務改革の本質を学べます。
02 誰でも読める業務フローを設計する力
経営層・現場・ITがそれぞれ異なる言語を話していては改善は進みません。現場内での改善議論、合意形成・IT部門との共通認識のための共通言語となるBPMNの基本のキをお伝えします。
03 現場で“動く業務マニュアル”を構築する
BPMN図をBPMSに実装すれば、業務フローは静的な絵ではなく、改善を回し続ける“動く業務マニュアル”となります。本講座では、従来のIT導入との違いを理解し、小さく始めて確実に成果を積み重ねる改善アプローチを体得します。
講座で学ぶこと
01 業務改善が進まない理由を理解し、仕組みに変える
「業務フローを描いたのに改善が止まる」「新システムを入れても効果が出ない」──その原因はBPMを誤解していることにあります。本講座では、BPMの正しい定義を学び、改善が“仕組み”として回り続ける組織をつくる方法を習得します。
02 国際標準BPMNで共通言語を持つ
BPMNは世界中で使われる業務フローの記述法です。経営層、現場、ITが同じ図を見て議論できるため、部門横断の合意形成が加速します。現場内での改善議論、合意形成・IT部門との共通認識のための共通言語となるBPMNの基礎ルールを学びます。
03 BPMSを活用し“動く仕組み”を実装する
従来の業務改善は一度の取り組みで終わりがちですが、BPMSを活用すれば業務フローは改善され続けます。本講座では、BPMN図をBPMSに実装するプロセスを理解し、スモールスタートで成果を積み重ね、変化に強い組織をつくる力を身につけます。
講師紹介
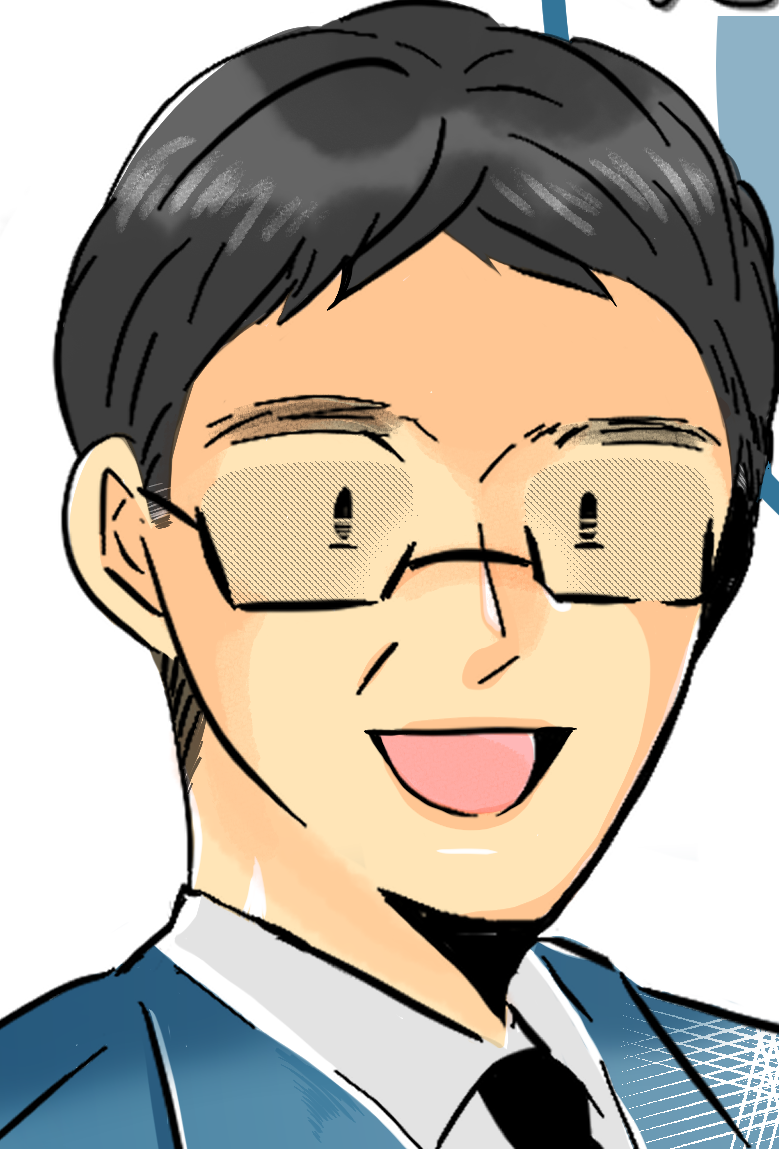
一般社団法人BPMコンソーシアム
代表理事
山原雅人
1961年生、大学卒業後、食品会社の生産部門に入社し業務改善全般に関して興味を持つ。経営コンサルタント、システム開発などを経験後、IT部門長として採用された企業でシステムの導入前の業務分析にBPMNを使用したことからBPMを知る。 2013年Bruce Silver著「BPMN method and style」を翻訳、BPMNを使った多数の記述分析経験を活かし2018年「業務改善、見える化のための業務フローの描き方」を出版。2019年(一社)BPMコンソーシアム設立、多数のBPM導入支援経験を持つ。
カリキュラム
時間 | 講義内容 |
|---|---|
第1部 10分 | 導入 •自己紹介、セミナーの目的 •「業務フローを描くだけでは見える化ではない」 •本日のゴール:「BPMを改善人材育成の仕組みとして理解する」 |
第2部 60分 | BPM概要 1.BPMとは •国際標準の業務フロー表記法のBPMNとBPMNをベースに実装し業務フローを稼働させるBPMSを使った技術に基づいたマネジメント手法 2.BPMに関するノイズ •「業務フローを描けば終わり」ではない •KPI管理との違い •「システム導入=BPM」ではない •誤解がなぜ生まれるのか 3.BPMNとは •誰でも理解できる表記法 4.PDCAが回るBPM改善ステップ •1プロセスを導入する6ステップと使用開始期限について PDCAを「仕組みとして」回すのがBPM 5.BPMSとは •「BPMN図がBPMS上で動く」イメージデモ •BPMSの誤解 6.従来のITシステム導入との違い •固定化された仕様 vs 継続的に変わる仕組み 7.BPMはスモールスタート •人材育成共に拡大をしていく |
第3部 60分 | BPMとBPMN 1.BPMN仕様が作られた目的 •世界共通のビジネス記述言語 •経営層・現場・ITにおいて共通言語として使用できる 2.BPMN図の描き進め方 •業務を知っている人が集まって描く 3.粒度と階層化について •どのようにして階層化させるか(階層に意味を持たせると混乱する) •ハンドオフでアクティビティの粒度が決まる 4.ビジネスアジリティの向上とBPMN •変化に即応できる仕組み •BPMNを現場が維持していることの重要性 5.レベル1とレベル2の違い •図で比較説明 |
第3部 60分 | BPMNにおける業務フローの基礎的な記述について 1.BPMNの記述ツールについて •無償、有償ツールの紹介(Camunda、Visioなど) 2.BPMNの基礎演習 •レベル1の基本的ルール抜粋 •わかりやすいBPMN図を描くポイント •BPMN仕様を守って描くためのスタイルルール |
第3部 10分 | まとめ •BPMは「図を描くこと」ではなく「人を育て、変化に強い会社を作る仕組み」 •BPMNとBPMSは「静的な図」ではなく「動く業務マニュアル」 •小さく始めて改善を繰り返すことが成功のカギ |
理解の手順
「業務フローを描く」ことを超え、BPMを組織的に活用できるようになることを目指します。
BPMの全体像を理解し、業務改善が「仕組み」として回る仕掛けを学びます。
そのうえで、BPMNという世界共通の記述法を用い、誰もが理解できる業務フローを描けるようになるプロセスを体験します。
単なる図ではなくBPMS上で稼働する「動く業務マニュアル」としての意義を理解し、従来のITシステム導入との違いを押さえます。
最後に演習を通じて、業務改善に必要な基礎スキルを習得し、すぐに現場で活かせる力を養います。
講座概要
受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から14日間視聴可能。 視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。 |
|---|---|
受講料金 | 20,000円(税込 22,000円) |
550,000円(税込 605,000円) | |
受講のご案内 | 【実施上の注意】 本講義は、オンライン配信講義となりますご受講はお申込み者限りとしており、複数名での受講の場合、人数分のお申込みが必要です。お申込者には、宣伝会議IDを通じて視聴環境をご提供しております。同一IDでの複数人での視聴・社内上映などは固くお断りしております。 【受講上のご案内】 ・講義は宣伝会議オンライン上でご視聴いただきます。該当期間内に宣伝会議マイページの「オンライン講座を見る」に進み、動画をご視聴ください。 ・視聴の際は、申込者ではなく実際に受講される方のマイページ登録が必須となります。 ・本講義には質疑応答はございません。 【レジュメについて】 講義資料はご視聴頂くマイページからPDF形式でダウンロードしていただきます。 |
注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 |
オンデマンド研修について |
|
割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 |
- 1名単位でのご受講は「1名受講」
- 部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」
- 体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。
チケットを利用する
この講座をシェア
この講座を見た人はこんな講座も見ています
- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/