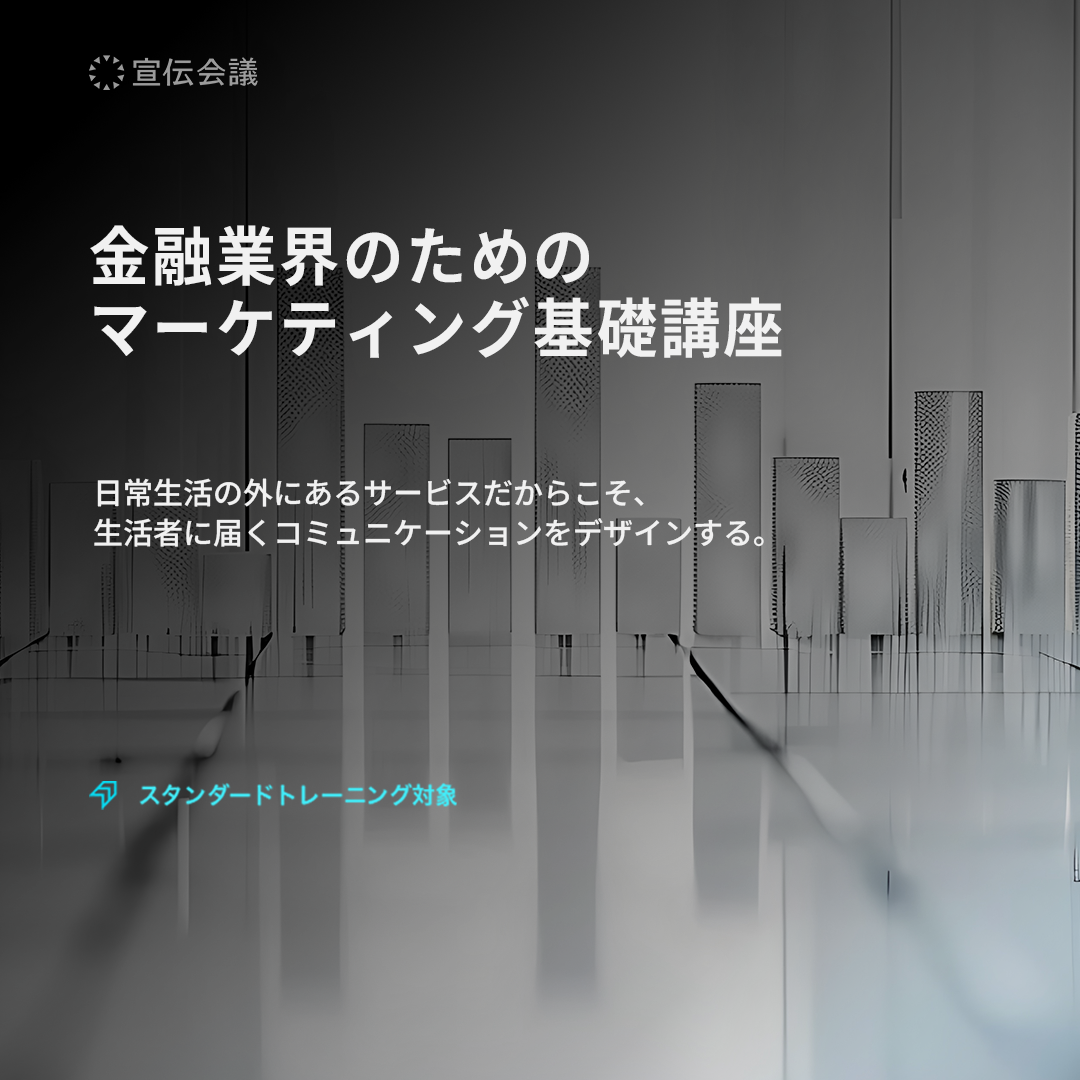開講の背景
金融商品ならではの難しさは、「日常生活の外にある」サービスであるということです。
一般の商材が武器にしている「好き・嫌いによるニーズ」を金融商品は生み出せないこと、また購入頻度の低さから、他者サービスからブランドスイッチを起こさせ自社に引き入れることが難しいことなど、高い特殊性が壁として立ちはだかっています。
さらに金融商品は、顧客にサービスの詳細スペックをしっかりと理解をしてもらわなければならない中で、「複雑で面倒」という潜在意識もあり、十分に理解してもらう遥か手前で、顧客は関心を失います。そのため、ニーズが顕在化した少ない顧客の奪い合いが起きてしまいます。また、ここ数年はマーケティング経験豊富な異業種参入が相次ぎ、市場環境も激変しました。加えて2021年11月開始の金融サービス仲介業制度などのように、顧客の利便性を考えた規制緩和も続々と行われています。
そこで今必要なのは、大きく2つです。1つは「顕在化したニーズ」を持つ顧客が確実に自社を選択肢に入れるためにデジタルを絡めたアプローチ手法を作り出すこと。もう1つは将来の顧客である潜在ニーズに対して、自社の持つサービスの有効性をデジタルチャネルを前提としつつ、どこで、どのように伝えれば、サービスの利用者になってくれるか、その道筋と訴求点を研ぎ澄ますことです。
これらの実現には、プロダクトアウトの発想ではなく、マーケティングの視点が随所に必要になってきます。つまり、顧客の金融サービスに対する期待をつぶさに観察し、それを基に自社の価値を再定義する必要があります。これは、従来の金融サービスをデジタルに置き換えるのではなく、商品・サービス・システムを含め、顧客がストレスを感じないオンライン完結型を目指している先行事例から学ぶことができます。
そこで宣伝会議では、業界の商品特性や商習慣を熟知しながら、マーケティングの実務も行っている講師から、効率よく要所を学べる「金融業界のためのマーケティング基礎講座」を開催します。
学ぶポイント
01.顧客思考をマーケティング4Cに沿って理解する
金融庁から度々指摘の入る「顧客本位の業務運営」を実現するために、本講座ではマーケティング4Cに沿って顧客理解を深めます。4Cとは、従来の金融サービスでよく見られた、企業が商品・サービスを考え市場に売り込むプロダクトアウトではなく、顧客のニーズからはじまるマーケットインの考え方です。
商品スペックでは違いを打ち出せないと感じつつ、そこに注力せざるを得ない状況から脱却するために、顧客のニーズから考え始める必要があります。このマーケティング思考を身に付ける過程で「商品自体に新しさは無いのになぜか顧客が満足するサービス」と「お得と思うのに売れない商品」の違いが理解できます。
02.新型金融サービス躍進の構図をマーケティング視点で説明できるようになる
この数年で店舗を持たない金融サービスが増えています。全く新たな組織を立ち上げたり、従来型のサービスをデジタル上で受ける事ができるようにしたり、それぞれに特徴が存在します。
ここで差が付くのは、そのサービスが「顧客にどのような価値を提供しているか」から考えている企業です。単にDX化の名目の下、自社のサービスをデジタル化しただけでは、企業都合の変更に過ぎません。そこでマーケティング思考で、新たな取組みを行う先進企業から、従来の訴求価値から何を変えたのかを学びます。
03.顧客の関心が高まったタイミングを逃さないマーケティング施策を理解する
企業が行うプロモーションが響かないのは顧客の検討状況と異なる情報発信を行っているためです。一般の商品であれば、ニーズでは無く、好き嫌いで消費行動を起こす事が出来ますが、金融商材は認識の中にまず置いてもらう必要があります。しかし多くの企業が、「そもそも顧客は金融サービスに無関心」という前提を見てみぬふりをし、玄人しか違いの分からない商品スペックや、企業イメージの訴求という、漠然とした発信しかできていません。
関心が高まったタイミングを捕捉し、適切なコンテンツを配信する事で、これまで以上に顧客の認識の中においてもらう事が出来ます。そのために必要な金融商材ならではのデジタルマーケティングの考え方を、金融業界で実践してきた講師からポイントを絞ってお伝えします。
04.お金に対する一般消費者の意識変容を施策に活用する
iDeCo・NISAなどの優遇制度や「老後2000万円問題」などにより、徐々に消費者も資産貯蓄から、運用へと目が向き始めてきています。その際、本当に気にしなければならないのは、競合商品ではなく、「複雑」「面倒」と思われている消費者心理です。これを取り除くためには、顧客がお金に対してどのようなイメージを持っているのかを認識して、情報発信する必要があります。
講座では実際の事例を参考に、お金に対する普遍的な人間の心理をおさえた上で、顧客の貯蓄や投資に対する意識に寄り添ったコミュニケーションについて習得します。
受講対象
・都市/地方銀行の宣伝販促、広報PRなどのマーケティング関係者
・非金融業界から新規参入を目指す担当者
・これらへ提案を行う広告関連会社
カリキュラム
時間 | 講義内容 |
約80分 | お客様のメリットから考える金融業界のマーケティング |
約90分 | 顧客のタイミングを逃さない施策の組み方 |
約90分 | 顧客心理の理解こそがマーケティング思考の第一歩 |
講師紹介

株式会社みんなの銀行
取締役副頭取
永吉 健一氏
1995年、(株)福岡銀行入行。経営企画部門に在籍し、経営統合からふくおかフィナンシャルグループ設立、その後のPMI業務に注力。2016年、企業内ベンチャーとして、新しい金融プラットフォームを提供するiBankマーケティング(株)を起業。また、国内初のデジタルバンク『みんなの銀行』の立上げをリードし、2021年にサービス開始、取締役副頭取に就任。

racco合同会社代表
横田 幸平氏
1974年生まれ。racco合同会社代表。元ジャパネットたかた執行役員。97年ダイエーOMC入社、以降ソニーファイナンスインターナショナル、NTTドコモ、ジャパネットホールディングスと各社でキャッシュレス分野での新商品・新サービス開発、マーケティングに従事。代表作の「dカードGOLD」は業界トップクラスの会員数840万人。現在はビジネスアナリストとして大手流通グループのDX推進に携わる。

株式会社電通デジタル
エクスペリエンス部門
ビジネスディベロップメント事業部長
兼統合デジタルマーケティング部門
プロデュース1部
宮下 敬志氏
食品メーカーの販売促進会社、外資系広告代理店、損害保険会社を経て2016年9月に電通デジタルに入社。事業会社と支援会社の双方を通じてマーケティングコミュニケーション(調査・企画・宣伝・販促など)や新規開拓営業を実践。直近では自社の教育研修プログラム策定、新規リードマネジメントを担当。

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ
ストラテジック・プランニングセンター
Fintechカテゴリーチーム
プランニング・ディレクター
宮田 達哉氏
・ストラテジック・プランナーとして金融、エネルギー、家電、トイレタリー、食品、旅行・レジャー、ラグジュアリーブランドなど幅広い業種のマーケティング・コミュニケーション戦略立案に携わる。 ・金融カテゴリーの業務キャリアは20年。 ・生命保険、自動車保険、銀行、証券会社、クレジットカード会社など、金融カテゴリーで戦略構築に関わったクライアント数は約50社。 ・新銀行の立ち上げ支援業務に関与。ビジネス戦略の立案経験も。
お申し込み
・1名単位でのご受講は「1名受講」
・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」
・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。
料金プラン
1名単位でのご受講におすすめ
講座概要
宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信。
お申込日から14日間視聴可能。
視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。
宣伝会議オンラインにログイン後、マイページの「オンライン講座を見る」に進むとご視聴いただけます。
レジュメなどの講義資料は、動画視聴画面からPDF形式でダウンロード可能です。
受講には、実際に視聴される方のマイページ登録が必要です。申込者とは別の方が視聴する場合は、個別にお申し込みください。
※同一IDでの複数人視聴・上映などは禁止されています。
※本講義には質疑応答はありません。
※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。
※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。
※教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。
※オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。
詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。
人数無制限・年間割引プランもございます
部門研修を計画するチケットを利用する
この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。
法人割引窓口の設定方法はこちら
この講座をシェア
この講座を見た人はこんな講座も見ています
- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/