講座について
社案内やブランドブック、採用案内など、自社のブランドイメージを構築するためのツールはどの企業にも存在します。
しかし、時代に合っておらず逆にイメージを下げている、営業が持っていく際に「古臭くてすみません...」と枕詞をつけて会社案内を使っているなど、うまく効果を発揮するツールになっていない現状があります。
そこで本講座では、リニューアルを考えている広報担当の皆様や、依頼を受ける制作側の方々に、自社のブランドらしさを表現し、統一した印象を与えるための制作物のディレクションノウハウをお伝えします。
受講対象者
- デザインを外部に依頼する広報・経営企画・総務の方
- ブランドをデザインに落とし込みたい広告関連会社の方 など
カリキュラム
時間 | 講義内容 |
115分 | デザインに落とし込む前に整理するブランド |
230分 | 効果的なブランドの体現方法 |
お申込み
オンデマンド配信講座
開講日 | 期間はご希望日から14日間です。 |
受講価格 | 59,000円(税込 64,900円) ※申込金5,000円(税込 5,500円)を含みます |
補 足 | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約7割引(12,500円)におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 |
注意事項 |
|
オンデマンド研修(人数100名まで)
開講日 | 期間はご希望日から14日間です。 |
定 員 | 100名 |
受講価格 | 550,000円(税込 605,000円) |
補 足 | ※視聴期間の延長、受講者の増加についてはお問い合わせください。追加料金にてご対応可能です。 |
注意事項 |
|
チケットを利用する
この講座をシェア
この講座を見た人はこんな講座も見ています
- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/
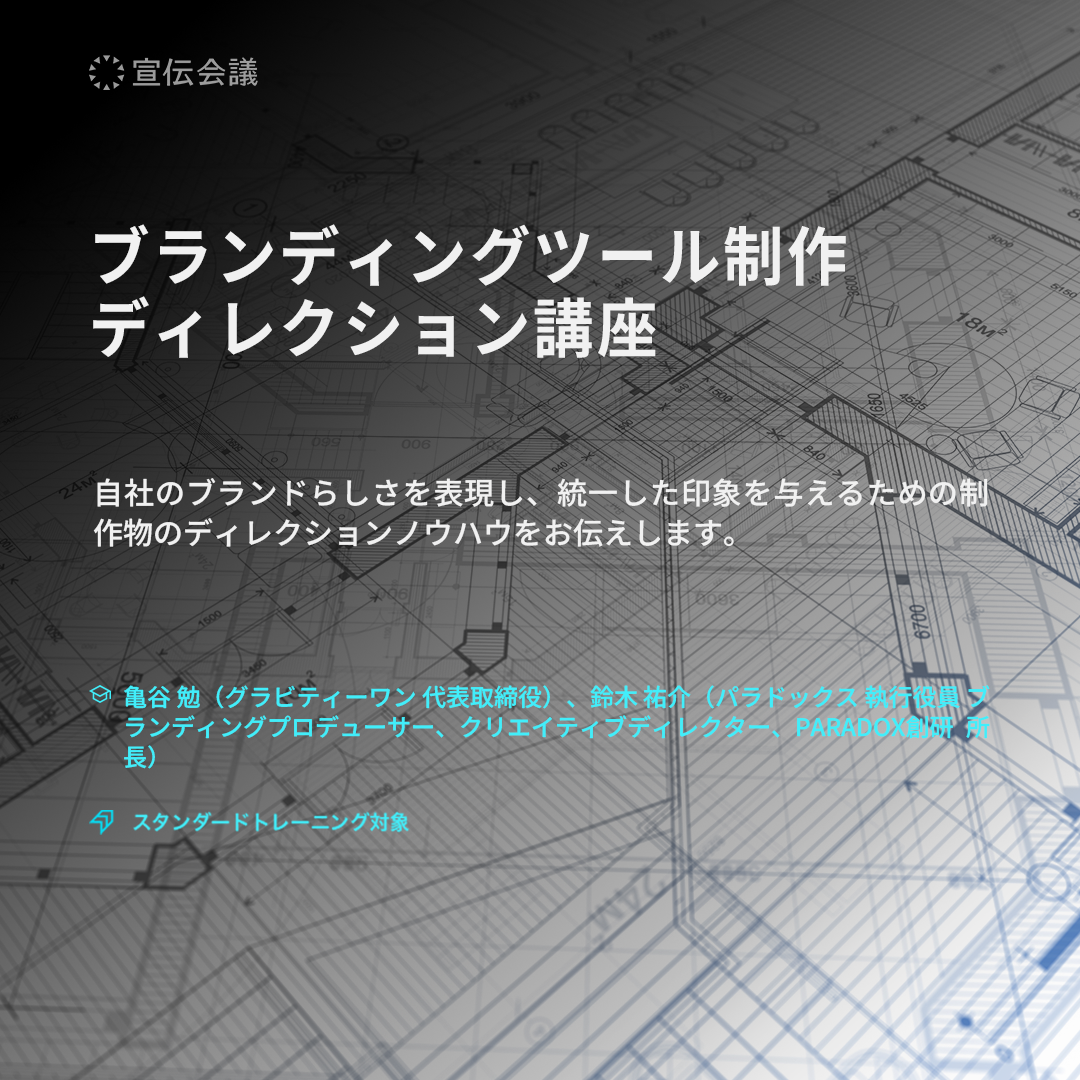
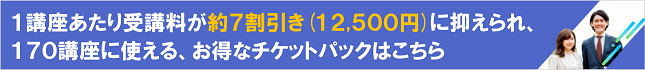
.png)