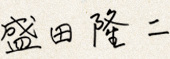川越市の市制九十周年を記念した文化事業のお話を伺ったとき、「小説甲子園のようなイベントを催しませんか」とぼくは事務局に提案した。今の高校生はいったいどんな小説を書くのか。高校生のときに生まれて初めて小説を書き、それがデビュー作となった作家として、そのことに興味以上のものがあるからだ。
それはもう四十年以上も前のことだ。学生運動がピークを迎えた一九六九年、ぼくの母校の県立川越高校では、生徒有志が校則を見直す検討委員会を立ち上げ、連日のように集会が開かれる中で、「政治活動の自由」や「服装の自由」を高らかに謳う「生徒憲章」が制定され、授業では現代哲学や公害研究などの自主講座が始まった。そんな激しく揺れ動いた母校を舞台に十六歳の夏、ぼくは五十枚の短編『糠星』を書いた。それが学習雑誌「高二時代」のコンクールで一等になり活字になった。ささやかな出発点だ(その短編は光文社文庫『あなたのことが、いちばんだいじ』に収録されています)。
そんな経緯から川越市主催「高校生小説大賞」の選考委員長の任をお引き受けすることになったのだが、これが実に胸躍る体験だった。
今の高校生はどんな言葉で物語を紡ぎ、自分なりのリアルを表現しようとしているのか。四十年前の高校生とどこが違って、何が変わらないのか。そんなことを考えながら読み進めたのだが、まずは応募作品のレベルの高さに驚いた。若者の活字離れが嘆かれるようになって久しいが、むしろ大人の活字離れの方が深刻なのでは?と思えるほどだ。人物設定から場面転換、伏線の張り方まで、よく考え抜かれている。
パラレルワールドやタイムトラベルといったアイディアを巧みに使った短編に良作が多かったが、「家族の崩壊」という重たいテーマに果敢に挑んだ作品を最優秀賞に選んだ。文章は武骨で素朴だが、安易なハッピーエンドを求めず、現実的な着地点を粘り強く追求した力作だ。
小説を書き始めることは誰にでもできる。ところが、途中で必ず物語の壁にぶつかる。その壁をなんとか乗り越えようとする。あきらめずに文章と格闘するうちにいつしか壁を乗り越えて、ラストの一行にたどり着く。一篇の小説を書き上げた高校生は誰もが、そのことの難しさと、脱稿したときの言い知れぬ喜びを実感したと思う。その脳内麻薬のように魅惑的な喜びに思いを馳せながら高校生の小説を大量に読み続けるうちに、ぼくは十六歳当時の自分に何度も対面していたのだろう。四十年の時を経て『糠星』の続編を猛然と書きたくなり、「日経新聞」電子版で一九六九年の高校紛争をモチーフにした長編『いつの日も泉は湧いている』の連載を始めたのだった。
当時の高校生は自分たちの力で世の中を変えることができると信じて闘った。その時代をもう一度生き直してみることで、現在の閉塞した日本社会に生きる高校生にエールを送れないかと考えて書き始めたのだが、やはり物語の壁に何度もぶつかり、ラストの一行にたどり着けないのではないかという不安と相変わらず闘いながら、この半年間ずっと十六歳の主人公に寄り添い続けている。

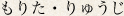
- 1954年東京生まれ。90年のデビュー作『ストリート・チルドレン』(光文社文庫)で野間文芸新人賞の候補に、92年『サウダージ』(角川文庫)が三島由紀夫賞の候補になる。「ぴあ」の編集者を経て96年より作家専業。
『二人静』で第1回Twitter文学賞を受賞。
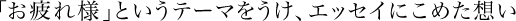
最近、集中力がなくなった、と痛感します。机に向かってもグスグズしてなかなか仕事に取りかかれない。これも老化現象の一つなんでしょうが、高校生小説大賞の選考委員を引き受けて、高校生たちの瑞々しい作品に接したときはまるで違った。50篇ほどの応募作を朝から深夜まで休むことなく一気に読み通したんです。
そのときのぼくはいつか作家になることを夢見ていた高校生の頃を思い出していたわけではありません。高校時代の自分にすっかり戻っていたんです。このエッセイではそんな自分に「お疲れ様」と。
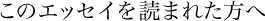
小説を書きながら、その一方でぼくは、早稲田大学や淑徳大学で、小説の書き方を教えています。その仕事を引き受けるのは、もちろん経済的な理由もありますが、それよりも作家を目指す生徒たちと接することで「書かずにいられない創作衝動」を肌で直接感じ取れるからです。講義の日は必ず彼らからエネルギーをもらって帰ります。
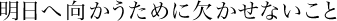
読書とお酒とフットサルは欠かせません。