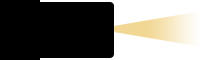
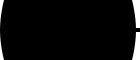
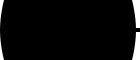
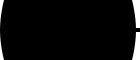
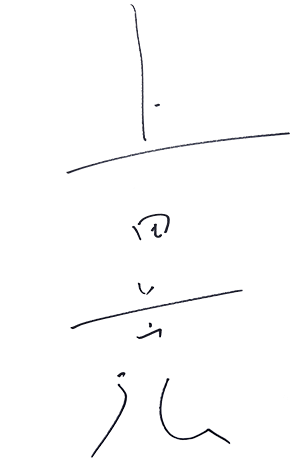
昔からよく散歩をする。昼夜を問わず、場所を問わず、シチュエーションを問わず。仕事中の息抜きで歩くこともあるし、息抜きとは逆に、今気にかかっている案件や小説について考えを深めるためにも歩く。
旅行中にだって僕は散歩する。知らない土地、知らない国……、と言いつつ、インターネットで検索すれば大まかな情報が手に入る。その国がどういう風にできあがって、人々がどんな神話を持っているか、民族的・外見的特徴だって前もって把握することもできるだろう。けれどやはり、始めて来た空間に自分が含まれているという感覚はいつも新鮮で、旅行中の散歩の楽しみの多くはそこにある。宿泊地が住宅街の近くだったなら、夕飯時に民家から漂う炊事の匂いが、夕闇に浮かぶ家の灯りとともに、何年も経った後に、ふっと思いだされることがある。一口に散歩と言っても、これは非日常の散歩。
でも今は日常の散歩の話をしよう。僕がプロの作家になる前のことだ。心構えとしては、発表する場所があろうがなかろうが関係ない、とにかく良い作品を書ければそれでいいのだ、と考えるべきだとは思っていたが、机に向かっていると、妙な焦りが生まれることがあった。それは直接的には発表の場を得られるかどうかという不安だったが、多くの時間を費やしているこの創作活動がはたして意味のあることなのかどうかという、もっと漠とした範囲の広い不安でもあった。
迷路を歩き続ける感じだ。その迷路には出口があるかもしれないし、ないのかもしれない。商業施設の巨大迷路ならば、必ず出口が用意されているという安心感があるけれど、僕がーそしておそらくは誰もが、否応なしに放り込まれる迷路がそんなふうに親切設計にできている保証などないのだ。目的なり目標なりがあるのだとすれば、そこへ到達できる道があるはずだと一旦は信じてみるしかない。
もちろん、目的達成のみに貴重な時間を消費するのは拙いことで、一瞬一秒の過程を慈しむことが本当の豊かさなんだろうと、論理的にはわかっていた。けれど若かりし頃の僕は、こうありたいと思う像と実像との乖離に苛まれて、時にそのことで頭がいっぱいになり、他のことは何も考えられなくなった。
そんな時もやはり散歩に出た。350mlのビールか、お金がない時は発泡酒を買って、それを飲みながらあてもなく歩く。風景を見て、風景を忘れて思索にふけり、思索に疲れてまた風景を見て……、とそんな風に繰り返していると、自分を苛んでいた想いが玉葱の一番外側の皮みたいにぺりぺりと剥がれていく。そして僕はむき出しになる。薄皮に包まれている間は、全体がその皮の茶色が玉葱の色だけれど、剥がれてしまえば別の色、皮は実のところ取るに足らないくらい薄くって、玉葱本体は水気があって肉厚だ。
いつの間にか公園の中を歩いていた僕は、その中の小高い丘まで歩く。そこからは東京の街の灯りがよく見える。二つのタワーが見えて、繁華街の光の塊、マンションの灯りなんかがその間を埋める。その一つ一つが人間がいなければ灯っていない人工の、つまりは自然には生まれない光だ。自然の素晴らしさを謳うものは多いけれど、薄皮の内側に様々な想いをため込んだ人々が作り出す不自然なはずの光に、僕はなぜか安らいだ気持ちになる。
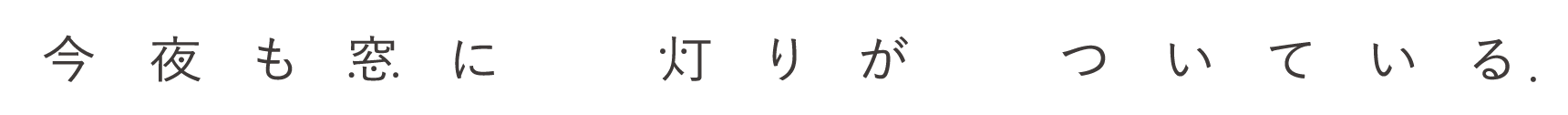

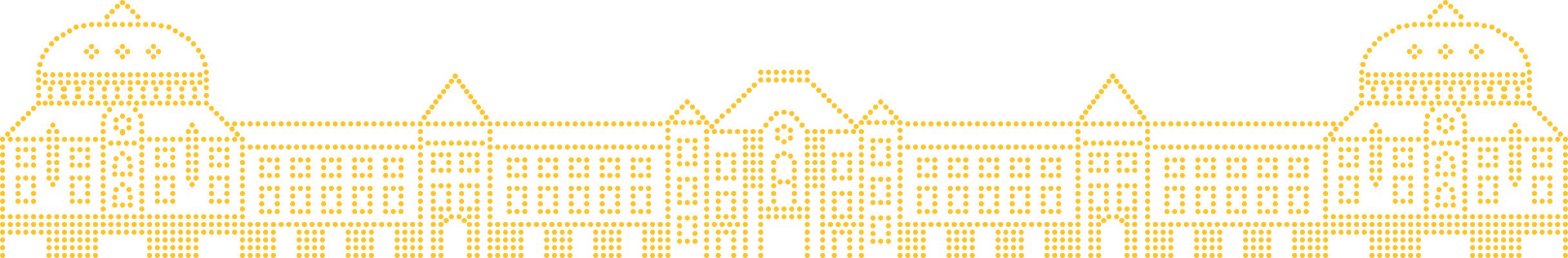
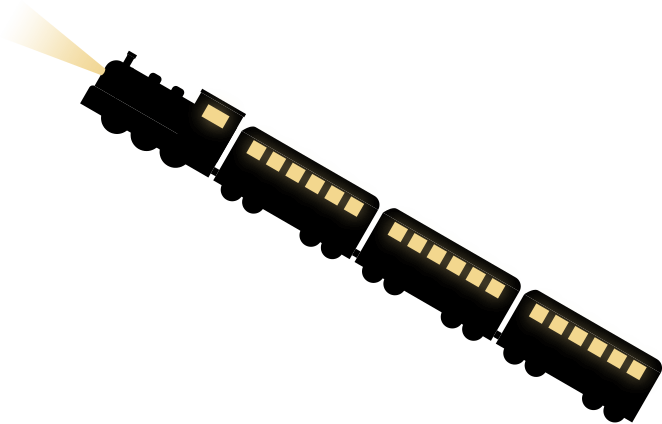

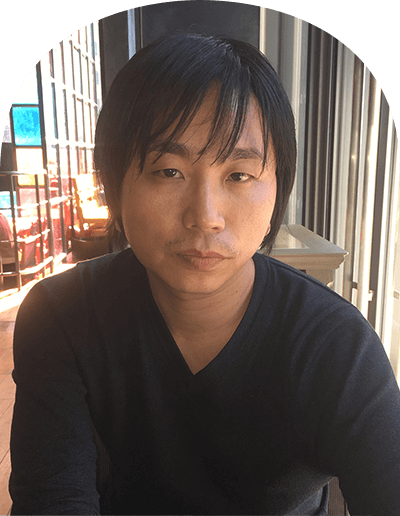
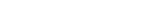

言い方を変えれば「不自然」さの象徴にも思えますが、それを見る時の安らぎを想いながら書きました。
多分誰にでもあるだう、ふっと浮かぶいつかの散歩中の風景を思いだしてくれると嬉しいです。