
昨年春から、芸術大学で建築を学んでいる。先日、期末の作品提出と試験があった。4ヶ月になる娘を左腕に抱き、右手で図面を描く日々。一日が24時間以上あればいいのにと願わずにはいられないほど課題量が多く、髪を振り乱しながら必死だった。そんなとき、真っ先におろそかになるのは食事で。課題と格闘しながら、片手で食べられる簡単なものばかりつまむ私を見かねて、買い物と料理は夫が担当してくれた。でも、せっかく作ってくれた食事を一緒にとる余裕すらなく、会話も自ずと少なくなる。何かを必死に追いかけている一方で、大切な何かを少しずつ削っているような、そんな気がして。
怒涛の試験期間をどうにか乗り越えた、ある晩の帰り道。通り沿いのマンションの一室に、ちょうど明かりが灯るのが見えた。部屋の主が帰ってきたのだろうか。明かりはシアーなカーテンに透け、まるで夜道に灯った提灯のよう。これから家族団欒の食事の時間かなあ、なんてぼんやり考えていると、ふと、キルギスを旅した時のことを思い出した。
国連WFPの活動でキルギスを訪れたのは、2015年の冬だった。旧ソ連の面影を残したキルギスの田舎の景色は、どこかうら寂しくて。私たちは小さな村のお宅にお招き頂いていた。まだ夕方だというのにあたりはすっかり暗い。ぐんと気温が下がり、体が芯から冷えていた。足元は雪でつるっとすべりそうで、注意して玄関先まで歩いていくと、小さな窓から明かりが漏れているのに気づいて、不思議とほっとしたのを覚えている。
室内に入ると、左手に台所があり、老婆が大きな鍋で羊とジャガイモを煮込んでいた。ゆらゆらと白湯気がたっぷり立ち上り、鍋の上には裸電球が一灯、ぶら下がっている。外から見えたのはこの電球の明かりだったのだろう。台所では、老婆の孫だろうか、小さな男の子が二人、梅ジュースを分け合って飲んでいた。私をちらりと見て気恥ずかしそう。すると
「いっぱい食べていってね、美味しくできたから」
と、老婆がにっこり。シワが深く刻まれたその笑顔は、私の故郷・沖縄にいる祖母に似ていた。そういえば、祖母も私が帰省するたびにソーキを鍋いっぱいに煮込んで待っててくれる。部屋は、鍋の湯気で温まり、羊脂の甘やかな香りでいっぱいになっていた。
いつの間にか、奥の居間には、おじいちゃんやおじさんも勢ぞろい。さっきの男の子二人もいる。家族の輪に私も入れてもらった。小さな皿によそったスープは、肉よりじゃがいもの方がゴロゴロと多い。特別なものは何もなくても、その優しい出汁は、冷えた体に沁み渡って。食は人をつなぐ。家族の食卓を一緒に過ごさせてもらったことが嬉しかった。小さな裸電球の明かりは温かく、滋味深い味と日々の暮らしを照らしていた。
窓明りの向こうには、なんでもない日常の風景がある。明かりの中にいるとわからないけれど、それは世界に二つと無い、かけがえのない家族の時間だったりする。そして外から見て初めて、それが羨ましいほど温かくて優しいことに気づくのかも。マンションの窓明りを見ながら〝私も早く家に帰ろう〟そう、思った。夫にお礼、まだちゃんと言えてなかった。帰ったら、いつものお鍋でも作って、さあごはんにしよう。
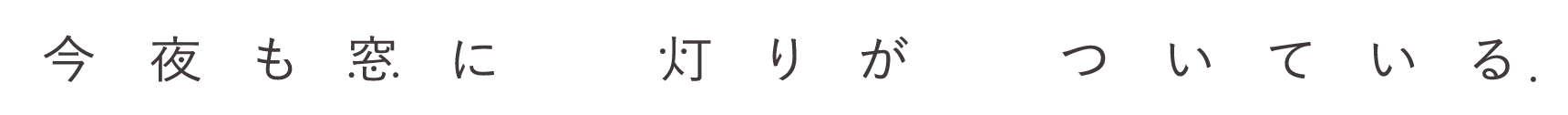
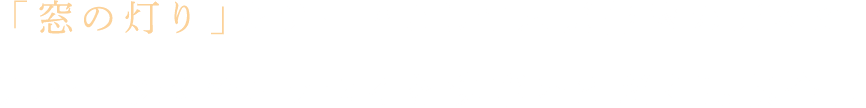

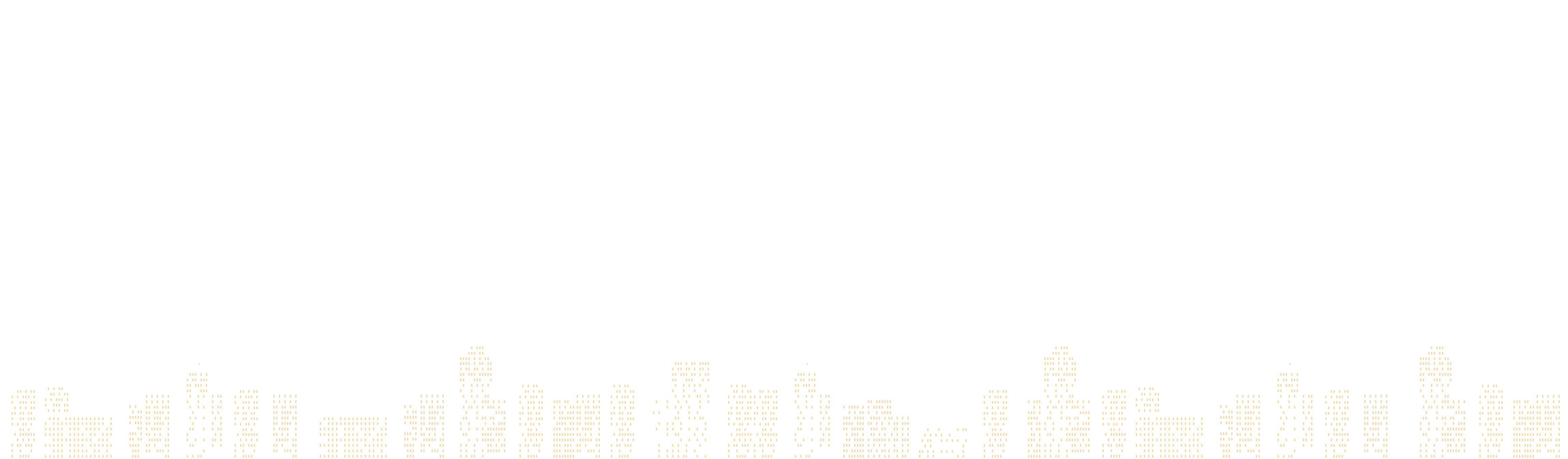




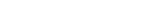


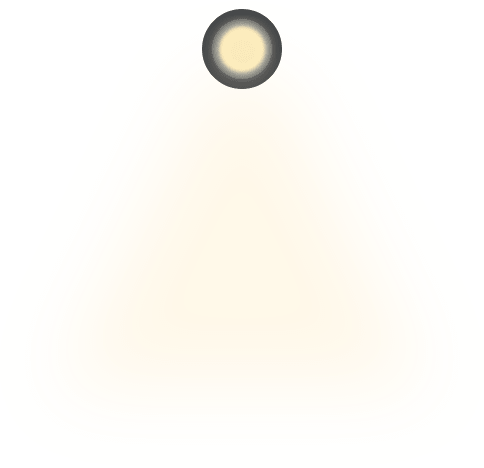
日々の暮らしのなかに、小さくてもかけがえのない幸せがあるはず。立ち止まったまま停滞しているようにみえる時間も、実は、そんな幸せや美しさに気づくためにあるのかもしれません。
ゆるっと、まるっと、楽しんで参りましょう!
六晶石ほっとパット
与謝野晶子『乱れ髪』
シャトーデュボワのプレミアムエッセンシャルオイル