
すごく好きな窓がある。
内側を光で満たして走る、夜の電車の窓だ。
乗るよりも、外から眺める方がいい(鉄道会社の人すみません)。出来れば車両は満員より、からっぽかと思うほど空いていて、時々ぽつり、ぽつり、と人影が頼りなく見えるくらいがいい(重ね重ねすみません)。
こうした条件に合う電車が見られるのは終電間際の、路線の終点に近い郊外の駅、ということになるだろうか。
そんな駅がある町に住んでいる。
仕事部屋の窓を開けると、数キロ離れた位置に駅から伸びた高架橋が見える。夜間は幾度となく、小さな四角い窓の灯りを数珠つなぎにした電車が橋を渡り、より闇の深い山の方へと走り去る。
移動していく窓の灯りを見ながら、いつも奇妙な気分になる。
あれは本当は、光る窓が移動しているのではなく、車両内部の形をした光が移動しているのだ。当たり前だけど。
そして町だとか、道路だとか、ビルだとか、駅舎だとか、そうした構造物をすべて取り払い、目の前の景色から光と闇だけを抽出した状態を想像する。まだ灯りが点いているマンションやビルの一室は、その部屋の形の光が宙に浮いている。まるで光の水槽のように。
残業中の静かな部屋、宵っ張りがゲームをしている部屋、恋人同士の喧嘩が終わらない部屋は皓々と光り、子供の寝かしつけや夫婦の営み、泊まりに来た友人と毛布を被って内緒話をしている部屋はオレンジがかった豆電球の色をしている。私たちの意識は光の水槽のなかでのみ、形を持ってぴんぴんと遊ぶことが出来る。
一つ、二つ、その日の用件を終えた部屋の灯りが消える。同じ数だけ、意識も消える。眠気が差せば瞼が落ちるのと同じで、永遠に光り続ける窓はない。毎夜、部屋を暗くし、意識の消滅を受け入れる際、私たちは世界にお別れを言っているのだと思う。さようなら、また明るくなったら、きっと会いましょう。そんな風に。
そうして暗さを深めていく町を、みずみずしい光をいっぱいに溜め、軽快に走り抜けていく夜の電車は、とても素敵だ。光の形で言ったら蛇だろうか、むかでだろうか、それとも連結されたようかんだろうか。明るいものは暗くなる、そんな約束事に知らないふりをして、闇の届かない場所を目指して走っているような、いじらしさすら感じる。
子供の頃から夜の電車を見ると、あれに乗りたい、と思った。乗って、どこかに行きたい。間もなく眠り、途絶えてしまう自分の夜ではなく、あのぴかぴかと光る水槽で運ばれた先の、眠りが訪れない未知の時間を生きたい。
それは、新品の本を開く瞬間の高揚と期待に似ている。受け入れてしまったものから抜け出して、遠くへ。なにも諦めなくていい、未知の領域に辿り着きたい。
その日の運行を終えた電車は車両基地へ運ばれ、検査を受けて眠りにつく。電車だっていずれ光を手放すのだと、大人の私はちゃんと知っている。でも、今ここにないものがどこかにある、それを辿り着きたいという願いが、確かな無限に繋がっていることもまた、知っている。
私たちはそれぞれの窓の灯を点し、願いを切符に換えて、今日も、終点のない電車に乗る。
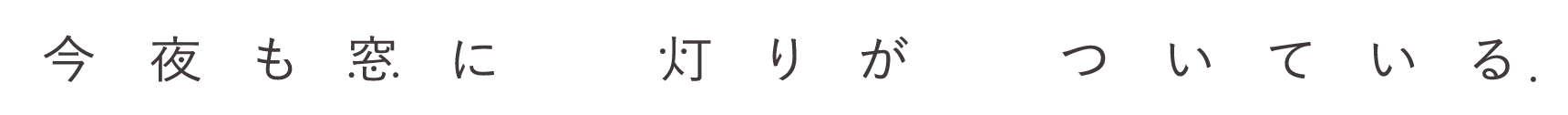
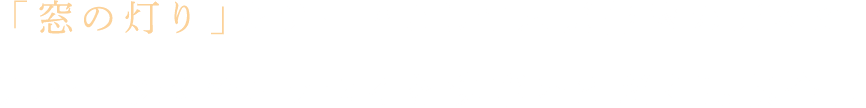

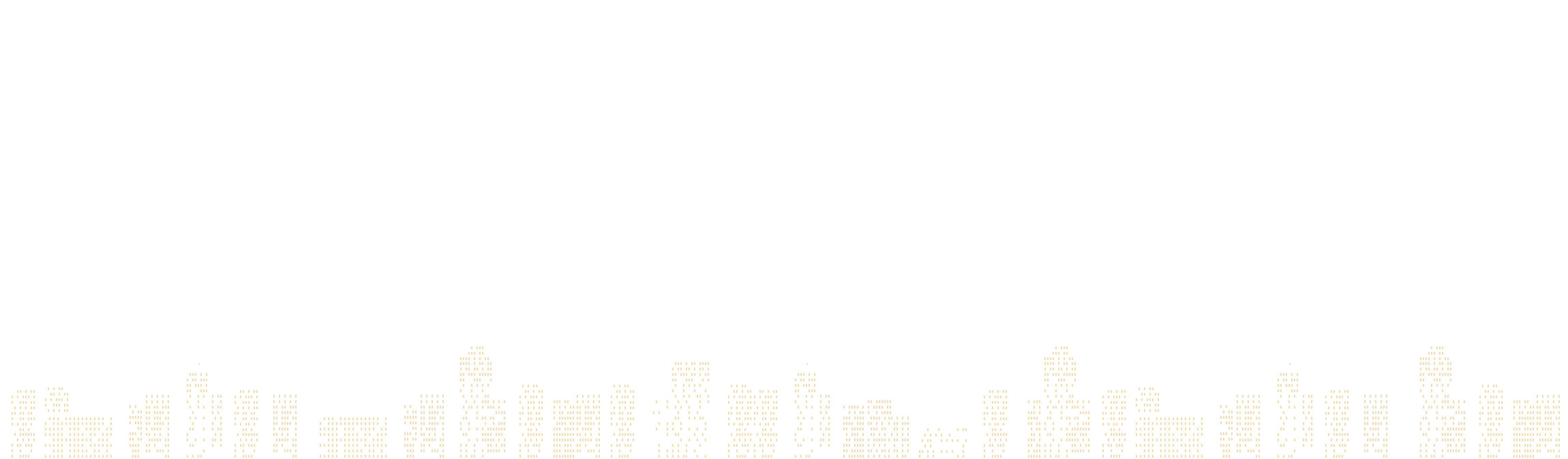




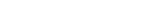


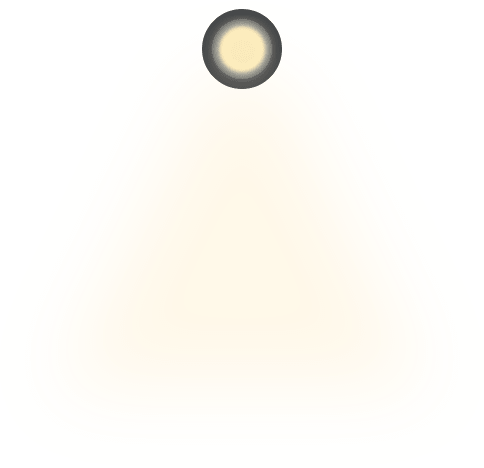
仕事中は基本的に一人なので、ぼんやり孤独な気分でやっていることが多いのですが、「窓の灯り」について考えるうちに、仕事に没入している時はだいたいみんな頭の中は一人だよな、でも良い仕事が成された時は色んな人と成果を分け合えるんだよなと、夜のあちこちに仲間がいるような、嬉しい気分になりました。
読まれた時間は、夜でしょうか。たぶん私もまだ起きています。お互い体に気をつけて、休める日は早めに寝ましょう。
眠りたいときに落ち着くための音楽を何曲か、ウォークマンに入れています。