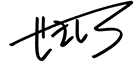
光を最も意識するのは正月だ。厳密に言えば大晦日から元日にかけて。初日の出の光ではない。小林幸子の衣装の光でもない。アパートの窓の灯りだ。
年が暮れていくにつれて、厄除け大師のCMの数と反比例するようにアパートの灯りは減っていく。帰省する住人が増えるからである。
大晦日の夜。自宅へと帰る道すがら、一軒のアパートを見る。ひとつだけ灯りがついている部屋がある。あの部屋の住人は帰省しなかったのだ、なんてことを考える。
少し歩くとさっきよりも綺麗なアパートがある。今度は灯りがふたつ。どちらの部屋の住人も東京で年を越すのだ。
立派なマンションを見上げる。灯りはいくつもついている。ファミリーが多いのだろう。ここがもはや故郷なのかもしれない。
住所を言う時に恥ずかしくなりそうな名前のコーポがある。そこは灯りがひとつついている。あの部屋の住人も帰省しないのか。
ふと、別の考えがよぎる。あの灯りはただの消し忘れかもしれないと。住人は帰省しているのに、灯りだけが煌々とついているパターンだ。電気代がもったいない。せめてエアコンは消してありますようにと願わずにはいられない。帰宅した時にエアコンの消し忘れを知るなんて、絶望でしかない。
数歩進むと、別の考えも浮かび上がる。もしかすると住人は死んでいるかもしれない。事件なのか事故なのか今は知る由もないが、のちのち私が目撃者として「大晦日の夜は電気がついてました」と証言することになる可能性はある。ならばある程度正確な時間を覚えておこうと時計を見る。23時。2003年の大晦日なら、曙はボブサップに倒されている頃で、紅白では長渕剛が歌ってた頃だ。
やっと自分のアパートに着く。1階も2階も窓の灯りはひとつもなく、この建物には自分一人しかいないことを知る。私はもう何年も帰省していないのだ。
高校生の時、親族の葬儀があった。私は高校の制服で出席した。大人達は喪服で、男性はスーツが多かった。それが当たり前だと思っていたら、スーツではない人が堂々と現れた。明らかに普段着と思われる服装で、髪の毛は長く、ヒゲもまた長かった。その風貌はまるでキリストのようだった。普段着だから休日のキリストか、近所のコンビニに行くようなキリストといったところか。あるいは夜中にドンキホーテに行くようなキリストでもある。お寺での葬儀にキリストというミスマッチさは奇妙であったが、それよりTPOに応じた服装をしない大人がいることが奇妙だった。なんだかみっともなく思え、こんな大人にはなりたくないと思ったことをはっきりと覚えている。
しかし、いつの間にか私はその人に近づいていた。社会人にならず、消去法でもの書きになり、風貌もイメージしていた大人とはかけ離れていた。スーツなど買ったことがない。冠婚葬祭はスーツを借りる。しかし靴は借りれず、黒いスニーカーをできるだけ革靴のように見せて切り抜けている。
灯りのないアパートは孤独しかなく、寂しさを呼び起こした。しかし今からの帰省は無理だ。
この後、他の住人が帰ってくるかもしれない。灯りがひとつでもあれば仲間がいると安心するはずだ。そんなことを考え、私は灯りをつけたまま寝ることにした。

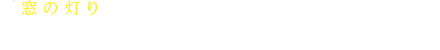


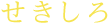

二番目に意識する光は、夜のビジネスホテルで光っている自動販売機で、400円くらいで缶ビールが売られているのが好きです。
私はネクタイを締めることができなくて、交番に行って締めてもらったことがあります。そんな人物のエッセイです。是非、反面教師にしてください。
バナー広告で出てくる怖そうな漫画を買って読んでいるうちに寝ます。