二年ほど前の秋だったか、とても不思議なものを見た。
浅草のマンションに仕事場があるのだけど、夕刻になんとなく窓辺に立つと、遠くのオフィスビルの窓の一つが、強烈な光を放っている。なんというかそれは、一見して人工的なものでないとわかるような、ものすごく明るい、橙がかった光だった。
まず、火事だと思った。しかし、その階にある他の窓はみんな暗いし、煙も見えない。つぎに、夕陽が反射しているのかもしれないと思った。しかし、そのビルは僕の仕事場よりも西側に立っていて、つまり夕陽はビルの向こうにあるはずで、ガラスに映るわけがない。
オフィスの中で、いままさに惑星が誕生しつつあるか消滅しつつあるような、とにかくとんでもない眩しさの光だった。僕は自分の鼻先を部屋の窓ガラスに押し当てて、その光に見入った。
やがて光は少しずつ様子を変えていった。光の中心が、だんだんと右へ動いているらしい。それにつれて光量も弱まっていき、窓の輪郭がはっきりと見えてきた。
そこで、ようやくわかった。
正体は夕陽だった。
といっても窓に反射していたわけではなく、夕陽そのものだったのだ。どういうことかというと、ビルの向こう側を太陽が通過し、その太陽と、ビルの西側の窓と、僕が見ていた東側の窓と、さらには僕が鼻先をくっつけているマンションの窓が、ぴったり一直線に並んだのだ。だから、太陽の光がビルを突き抜けて僕の目まで届き、建物の向こうにあるはずの夕陽が見えたというわけだった。
やがて光はすっかり消えた。ほんの短い偶然だった。窓辺に立ったまま、僕はむかし読んだ「きん色の窓とピーター」という絵本を思い出していた。
貧しい農家の息子ピーターは、いつも仕事を終えると、遠くの丘を眺めた。そこには一軒の家が建っていて、その家は、まるで宝石のように金色に輝く窓を持っていた。ピーターはその美しさに夢中になり、毎日、夕刻になるとその窓を眺めた。あれは家ではなく、お城かもしれない、綺麗なお姫様が住んでいるに違いない、などと空想しながら。ある日、とうとうピーターは決心し、丘の向こうへと出かけていく。しかし驚いたことに、そこにあったのは彼の家と同じような貧しい百姓家だった。戸口から出てきた少女に、ピーターは金色の窓の話を聞かせた。すると少女は、それなら自分も毎日見ているわと、遠くの丘を指さしてみせた。金色に輝く美しい窓を持つ家が、そこにもあった。それは、ピーターの家だった。
ほんの短い、奇跡のような光景を僕に見せてくれたあのオフィスで働く人たちも、自分たちの見慣れているその窓が、あんな芸当をやってのけたことなど、きっと知らないのだろう。
自分のあずかり知らぬところで、あなたも誰かに奇跡を見せているかもしれない--などと借り物のような締めくくり方をすることには抵抗があるが、本当にそんなふうに思えた体験だった。もう一つついでに気恥ずかしいことを書かせてもらうと、あの体験で僕は少し自信がついた。創作物には批判がつきもので、正直なところ、その批判ばかりが聞こえてしまうし、いつまでも記憶に残ってしまうけれど、僕の小説を読んで、なにがしかの感動をおぼえてくれる人も、たぶんどこかにいるのだ。
1975(昭和50)年、東京都生まれ。
2004(平成16)年『背の眼』でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、デビューする。
独特の世界観を持つ作家として、大きな注目を集めている。
2007年『シャドウ』で本格ミステリ大賞、2009年『カラスの親指』で日本推理作家協会賞を受賞。2010年『龍神の雨』で大藪春彦賞を、『光媒の花』で山本周五郎賞を受賞する。2011年『月と蟹』で直木賞を受賞。
ほかに、『向日葵の咲かない夏』『片眼の猿』『水の柩』『光』『ノエル』『笑うハーレキン』『貘の檻』『透明カメレオン』などの作品がある。

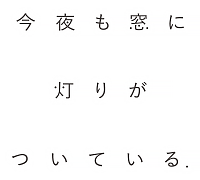
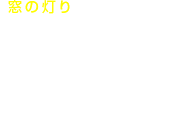
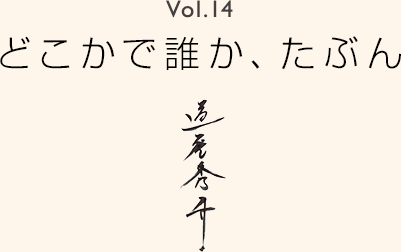


童話の教訓というものは、実体験とのコラボによって初めて効果を発揮するのかもしれません。
部屋の窓から、いろんな季節のいろんな時間に外を眺めてみると、面白いことが起きるものですね。
自信を取り戻させてくれる思い出です。